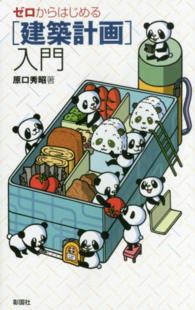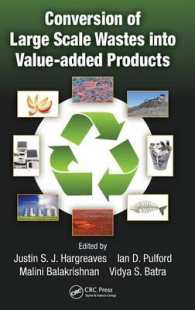出版社内容情報
★エネルギー技術において重要な地位を占める「材料技術」に焦点をあて現状と今後の課題を詳述!
★水素の製造技術,貯蔵技術,インフラストラクチュア,燃料電池と社会システムを形作る技術を網羅!
--------------------------------------------------------------------------------
「はじめに」より
水素エネルギーの研究開発が本格的に始められたのは,1970年代のいわゆる石油ショックが契機とされる。それ以来,浮き沈みはあるが水素エネルギーの研究が進められて久しいが,現在ほど,その実現性が確信されていたことは無かったであろう。水素エネルギーは燃焼しても水しか生成しないクリーンな燃料であることは論を待たない。また,水素エネルギーは,特に燃料電池自動車において車載燃料として利用され,高いエネルギー効率とクリーンな排気を同時に達成できると想定されている。そのため,我が国を始め,世界の各国で燃料電池および水素エネルギーに関する研究開発が盛んとなっている。
我が国では,水素エネルギーに関する国家プロジェクトは1974年から,途切れることなく進められてきた。最初は「サンシャイン計画」および「ニューサンシャイン計画」の基で研究開発が進められてきた。1993年度から10ヶ年間,「WE-NET」計画による総合的な水素エネルギーの研究開発が進められた。WE-NET計画当初は,海外の再生可能エネルギーで大量かつ大規模に製造した水素エネルギーを我が国へ輸送し,発電用燃料に使おうとするものであった。 しかしながら,1996年にダイムラー・ベンツ社(当時)およびトヨタ自動車(株)による燃料電池自動車のデモンストレーションなどにより,燃料電池自動車への期待が一挙に高まった状況に対応するように,WE-NET計画は,現状への対応へと舵を切り水素ステーションの開発と実証など注目すべき成果を挙げた。
しかしながら,燃料電池自動車の普及を促進するために,規制緩和等が早急に必要であるとの社会的要請から,WE-NET計画は当初計画より一年早く終了し,規制緩和に必要な技術的検討を主たる目的とする「水素安全利用等基盤技術開発」が2003年度より開始された。現在,規制緩和に必要な様々な検討が一段落し,「水素安全利用等基盤技術開発」は,2005年度より自動車用および定置用燃料電池に関する規制再点検及び標準化のための研究開発「水素社会構築共通基盤整備事業」と燃料電池用水素に係わる実用化技術の研究開発を加速するための「水素安全利用等基盤技術開発」に分けてプロジェクトを再編成する事となっている。
水素エネルギーは二次エネルギーであり,様々な一次エネルギーから製造されるエネルギー媒体である。すなわち,自然界には水素エネルギーは事実上存在しないので,水素エネルギーをそのままの形で採取することはできない。水素エネルギーは,電力と同様に,我々が何らかの利得を得るために製造するものであることを理解することが基本中の基本である。
水素エネルギーに関する重要な観点の一つが,二次エネルギーを燃料と二分する電力と相互に変換が可能な点にある。水素エネルギーは燃料電池による発電で水素から電力が,電気分解による水素製造により電力から水素へと容易にエネルギー変換される。水素エネルギーのような燃料と電力を比較すると,燃料は一般に貯蔵および輸送が効率的に行えることに特徴がある。そのため,貯蔵・輸送可能な水素エネルギーを活用した電力貯蔵などが今後の重要な技術開発課題の一つとされている。
水素エネルギーは,一つの技術ではなく,水素にまつわる様々な技術要素から構成されている総合的なエネルギーシステムであることが特徴である。すなわち,水素エネルギーについて議論するに当たっては,製造,輸送貯蔵,利用などの個別要素技術についての研究開発はもちろんのこと,水素エネルギーの特徴を活かすためのエネルギーシステムのあるべき姿に始まり,エネルギー効率,エネルギーコスト,安全の確立,標準の制定などの多くの観点から,充分かつ総合的な検討が必要とされることに留意されたい。
水素エネルギーは,現在,ロケット推進の燃料以外,エネルギーとしてはほとんど実用化されておらず,実際に社会に導入されるまでには,多様かつ数多い個別要素技術の課題を順次クリアしていくことが第一段階として必要となろう。中でも,材料技術はエネルギー技術においては最も重要な地位を占めており,「材料の革新無くしてエネルギー技術の革新は無い」とも言える鍵となる技術である。本書ではタイトルにもあるように,「材料技術」に焦点をあてて,水素エネルギーに必要な材料技術の現状を詳述すると共に,今後の課題について述べることを第一の目的としている。
前述の水素エネルギーのもう一つの特徴である,特定の個別技術ではなく,様々な技術を総合した社会システムである点については,本書では,水素の製造技術,水素の貯蔵技術,水素エネルギーのインフラストラクチュアおよび水素エネルギーの応用技術について,我が国におけるそれぞれの分野の最高の専門家からの寄稿を得た。現状を俯瞰するには最適の書と言えよう。また,全体としてのトーンをそれぞれの専門家の独自の観点を損なうことなく,調和をとるように心がけたつもりである。
本書が,まさに正念場を迎えている水素エネルギーについて関心を持っておられる読者諸兄姉の座右の書となることを念じている。また,今世紀に生きる人類が資源・エネルギーと環境の時には相容れない厳しい制約条件の中で,持続可能な社会を築くために必要かつ不可欠な技術開発の参考になれば幸いである。
2005年4月 秋葉悦男
--------------------------------------------------------------------------------
秋葉悦男 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 統括研究員
兼 水素エネルギーグループ グループ長
安田勇 東京ガス(株) R&D本部 水素ビジネスプロジェクトグループ 技術開発チームリーダー
寺村謙太郎 東京大学 大学院工学系研究科 博士研究員
堂免一成 東京大学 大学院工学系研究科 教授
若山樹 (独)産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門 細胞ナノ操作工学研究グループ 特別研究員
三宅淳 (独)産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門 総括研究員
小貫薫 日本原子力研究所 大洗研究所 核熱利用研究部 熱利用技術研究グループ グループリーダー
塩沢周策 日本原子力研究所 大洗研究所 所長
美濃輪智朗 (独)産業技術総合研究所 循環バイオマス研究ラボ 主任研究員
柳下立夫 (独)産業技術総合研究所 循環バイオマス研究ラボ 主任研究員
嘉藤徹 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 燃料電池グループ 主任研究員
高野俊夫 JFEコンテイナー(株) GSE事業部 事業部長
矢田部勝 岩谷瓦斯(株) 液体水素・水素エネルギープロジェクト 理事
;液体水素・水素エネルギープロジェクト部長
藤井博信 広島大学 自然科学研究支援開発センター 物質機能開発部 特任教授
市川貴之 広島大学 自然科学研究支援開発センター 物質機能開発部 助手
田中秀樹 千葉大学 大学院自然科学研究科 多様性科学専攻 相関物質先端科学講座 助手
金子克美 千葉大学 理学部 化学科 教授
藤島武蔵 近畿大学 理工学部 応用化学科 助手
山内美穂 九州大学 大学院理学研究院 化学部門 助手
北川宏 九州大学 大学院理学研究院 化学部門 教授
角掛繁 日本重化学工業(株) 金属事業部 機能材料グループ グループリーダー
岡野一清 水素エネルギー協会 理事
松岡美治 岩谷産業(株) 水素エネルギー部 シニアマネージャー
家入裕治 (財)エンジニアリング振興協会 技術部 水素プロジェクト室 研究主幹
高木靖雄 武蔵工業大学 工学部 環境エネルギー工学科 教授
伊藤靖彦 三洋電機(株) 技術開発本部 PEプロジェクトビジネスユニット リーダー
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 水素エネルギーの現状と課題(秋葉悦男)
1. はじめに
2. 我が国の水素エネルギー研究開発国家プロジェクト
2.1 サンシャイン計画
2.2 ニューサンシャイン計画
2.3 水素安全利用等基盤技術開発
3.水素エネルギーを取り巻く環境
3.1 水素エネルギーとエネルギーネットワーク
3.2 水素エネルギーの今後
4. 水素エネルギーに関する技術課題
5. まとめ
第2章 水素製造技術
1. 炭化水素からの水素製造技術(安田勇)
1.1 はじめに
1.2 燃料電池向け水素製造技術
1.3 改質反応
1.3.1 水蒸気改質反応
1.3.2 部分酸化方式(部分燃焼方式)
1.3.3 自己熱改質(オートサーマル方式)
1.3.4 水蒸気改質反応の操作因子
1.4 CO変成反応(シフト反応)
1.5 脱硫
1.5.1 水添脱硫方式
1.5.2 常温脱硫方式
1.6 精製
1.6.1 PSA法
1.6.2 選択酸化(preferential oxidation :PROX)法
1.6.3 膜分離法
1.7 最近の開発動向
1.7.1 定置用PEFC向け水素製造技術
1.7.2 燃料電池自動車向け水素ステーション
1.7.3 水素分離型改質システム
1.8 新たな水素製造技術の取り組み
1.8.1 水素透過膜の高性能化
1.8.2 CO2回収による非平衡改質
1.8.3 熱分解
1.8.4 プラズマ分解
1.8.5 酸素透過膜メンブレンリアクター
1.8.6 メタン芳香族化による直接改質
1.9 おわりに
2. 水の光分解(寺村謙太郎,堂免一成)
2.1 はじめに
2.2 水の光分解反応のメカニズム
2.3 水の光分解反応の歴史と最近のトピックス
2.4 おわりに
3. 光合成微生物による水素製造技術(若山樹,三宅淳)
3.1 はじめに
3.2 光水素製造に使用可能な資源量
3.2.1 太陽光
3.2.2 バイオマス
3.3 光水素製造が可能な光合成微生物
3.3.1 光合成微生物の活用
3.3.2 菌体機能の活用
3.4 光合成微生物による光水素製造を可能にするシステム
3.5 光水素製造の実現性
4. 水の熱化学的分解(小貫薫,塩沢周策)
4.1 はじめに
4.2 熱化学水素製造法
4.3 ISプロセスの反応構成
4.4 ISプロセスの研究開発
4.4.1 閉サイクル水素製造のための研究開発
4.4.2 効率的な水素製造のための研究開発
4.4.3 腐食性プロセス環境で用いる装置材料・機器の検討
4.5 おわりに
5. バイオマスからの水素製造(美濃輪智朗,柳下立夫)
5.1 バイオマスとは
5.2 バイオマスからの水素の生産
5.3 二酸化炭素吸収ガス化
5.3.1 二酸化炭素吸収ガス化の原理と特徴
5.3.2 バイオマスの二酸化炭素吸収ガス化
5.3.3 今後の展望
5.4 バイオマスからの生物学的水素生産
5.4.1 水素発酵
5.4.2 水素・メタン二段発酵
5.4.3 グリセロールの水素発酵
5.4.4 水素生産菌と生物電池
6. 高温水蒸気電解(嘉藤徹)
6.1 高温水蒸気電解の特徴
6.2 構成材料とセル構造
6.3 SOEC開発課題
6.4 SOECの開発事例
6.4.1 DornierによるSOEC開発
6.4.2 その他のSOEC開発
6.5 最近の開発動向
6.5.1 高温ガス炉等対応高温水蒸気電解
6.5.2 バイオガス等を利用した高効率水素製造
6.6 今後の開発展望
第3章 水素貯蔵技術と材料
1. 高圧水素(高野俊夫)
1.1 はじめに
1.2 高圧水素貯蔵方式の自動車への適用事例
1.2.1 FCVへの適用
1.2.2 水素燃焼式自動車への適用
1.3 FCV用容器の開発の現状
1.3.1 天然ガス自動車燃料装置用容器の構造
1.3.2 アルミ合金ライナーC-FRP容器の製造プロセス
1.3.3 プラスチックライナーC-FRP容器の製造プロセス
1.3.4 CNGV用容器をFCVに適用するための課題
1.3.5 FCV用高圧水素容器の要求性能
1.3.6 更なる高圧化に向けて
1.4 燃料電池自動車の高圧水素燃料ユニットの開発
1.4.1 高圧水素燃料系の技術課題
1.4.2 70MPa燃料電池自動車用高圧水素燃料系評価プロジェクト
1.5 高圧水素供給インフラの開発
1.5.1 超高圧水素容器を採用した新水素貯蔵・輸送システム
1.5.2 国内における水素輸送システムの現状
1.5.3 海外における水素輸送システムの現状
1.5.4 水素輸送用大型高圧水素容器
1.5.5 水素充てん所蓄ガス器用大型高圧水素容器
1.6 規制緩和への取組み
1.7 おわりに
2. 液体水素(矢田部勝)
2.1 はじめに
2.2 液体水素利用の特徴
2.3 液体水素製造の実際
2.3.1 原料水素の精製
2.3.2 オルソ水素、パラ変換
2.3.3 水素液化プロセス
2.3.4 液体水素貯蔵と供給
2.3.5 液体水素の製造と供給で注意すべきポイント
2.4 今後の展開と課題
第4章 水素貯蔵材料
1. 水素貯蔵材料の現状と課題(秋葉悦男)
1.1 はじめに
1.2 水素貯蔵材料に期待する理由
1.3 水素貯蔵材料に期待されている性能
1.4 水素貯蔵材料の反応の形式
1.4.1 吸着(Adsorption)
1.4.2 吸蔵(Absorption)
1.4.3 化学反応(chemical reaction)
1.5 水素と原子の化学的結合
1.6 まとめ
2. 合金系材料(秋葉悦男)
2.1 はじめに
2.2 合金系材料の特徴
2.3 合金系材料の分類
2.4 水素吸蔵合金の用途
2.5 水素貯蔵用水素吸蔵合金開発の実例
2.5.1 BCC系水素吸蔵合金
2.5.2 Mg系水素吸蔵合金の開発
(1) ラーベス相構造をもつMg系合金
(2) Mg系BCC構造合金の開発
2.5.3 高圧水素と水素吸蔵合金を組み合わせた水素タンク(ハイブリッドタンク)
2.6 まとめ
3. 無機系材料(藤井博信,市川貴之)
3.1 はじめに
3.2 アラネート系材料
3.3 アミド・イミド系材料
3.4 ボロ・ハイドライド系材料
3.5 おわりに
4. 炭素系材料(田中秀樹,金子克美)
4.1 はじめに
4.2 超臨界水素と吸着,吸収,吸蔵
4.3 炭素材料の種類と構造
4.4 一般炭素材の細孔構造と分子ポテンシャル構造
4.5 ナノチューブ類の細孔構造と分子ポテンシャル構造
4.6 水素吸着にみる量子効果
4.7 超臨界気体の吸着
4.8 炭素材料への超臨界水素吸着
4.9 化学吸着による超臨界水素吸着
5. 高分子系材料(藤島武蔵,山内美穂,北川宏)
5.1 はじめに
5.2 高分子金属錯体への水素吸蔵
5.2.1 プロトン共役酸化還元特性に基づく水素吸蔵
5.2.2 ルベアン酸系銅配位高分子における水素吸蔵特性
5.2.3 水素ドーピングに伴う物性変化
5.3 ポリマー被覆金属ナノ粒子の水素吸蔵
5.3.1 ポリマー被覆金属ナノ粒子の合成
5.3.2 ポリマー被覆金属Pdナノ粒子の水素吸蔵特性
(1) ポリマー被覆金属Pdナノ粒子の構造
(2) ポリマー被覆金属Pdナノ粒子の水素吸蔵特性
5.3.3 ポリマー被覆Ptナノ粒子の水素吸蔵特性
5.3.4 ポリマー保護Niナノ粒子の水素吸蔵特性
5.4 おわりに
6. 水素貯蔵材料を用いたタンク(角掛繁)
6.1 水素吸蔵合金タンク
6.1.1 小型水素吸蔵合金タンク
6.1.2 水素自動車用水素吸蔵合金タンク
6.1.3 定置式水素吸蔵合金タンク
6.2 高圧型水素吸蔵合金タンク
6.3 その他の水素貯蔵材料を利用したタンク
第5章 水素エネルギーのインフラストラクチャー
1. 水素ステーション(岡野一清)
1.1 はじめに
1.2 水素ステーションの水素源
1.3 水素ステーションのシステム
1.3.1 水素ステーションのシステム
1.3.2 各方式の水素ステーションのシステムと特徴
(1) 圧縮水素貯蔵型
(2) 液体水素貯蔵型
(3) 燃料改質型(天然ガス、LPG、石油系燃料、メタノール)
(4) 水電解型
1.3.3. 水素ステーションの供給能力と標準化
1.4 水素ステーション用機器
1.4.1 燃料改質装置
1.4.2 水電解装置
1.4.3 水素精製装置
1.4.4 圧縮機
1.4.5 蓄圧器
1.4.6 ディスペンサー
1.5 水素ステーションの運転
1.6 水素ステーションの安全対策
1.7 水素のコスト
1.8 我が国における水素ステーションの開発
1.8.1 WE-NETプロジェクトにおける水素ステーションの開発
1.8.2 JHFCプロジェクトにおける水素ステーションの開発
1.9 世界各国における水素ステーションの開発
1.10 水素インフラの構築とその課題
1.10.1 海外の動向
1.10.2 我が国における水素インフラ構築の課題
1.11 今後の展望
2. 水素の安全技術(松岡美治)
2.1 はじめに
2.2 水素の特徴と安全に対する考え方
2.3 水素ステーションの基本構成
2.4 水素ステーションの準拠法
2.5 水素ステーションにおける安全技術
2.5.1 水素脆化と適正材料の選択
2.5.2 水素の拡散特性と漏洩防止
2.5.3 着火源の防止
2.5.4 着火時の防消火
2.5.5 インターロックシステム
2.6 おわりに
3. 水素技術の国際標準(家入裕治)
3.1 はじめに
3.2 国際規格・ISO (International Organization for Standardization)について
3.3 我が国における水素技術関連国際標準化活動
3.4 海外における水素関連国際標準化活動
3.5 ISO/TC197(水素技術)について
3.5.1 ISO/TC197の概要
3.5.2 組織,活動中のWG項目(活動経緯・審議中の規格)
(1) 組織-ISO/TC197国内対応体制
(2) 発行・文書化済みのTC/197項目
(3) 審議中の項目
(4) ISO/TC197の具体的活動
(5) 我が国としての重要WG項目と活動状況
3.5.3 水素技術・標準化の今後の検討項目
3.6 国際標準化活動における我が国の課題
第6章 燃料電池への応用
1. 自動車用燃料電池開発の現状と課題(高木靖雄)
1.1 固体高分子形燃料電池PEFCの特徴
1.2 固体高分子形燃料電池PEFCの構成と構造
1.2.1 電解質膜
1.2.2 電極層と電解質膜の集合体
1.2.3 ガス拡散層
1.2.4 バイポーラープレート
1.2.5 自動車用燃料電池における水素の車載方法
1.3 固体高分子形燃料電池PEFCの性能と技術課題
1.3.1 基本性能と過電圧
1.3.2 現時点におけるPEFCの性能
1.3.3 今後の技術課題
1.4 わが国における自動車用水素燃料供給インフラ普及の現状
1.5 各国の燃料電池自動車実証試験の現状
1.6 おわりに
2. 家庭用燃料電池の現状と課題(伊藤靖彦)
2.1 はじめに
2.2 家庭用PEFCコージェネレーションシステム
2.2.1 システムの概要
2.2.2 燃料電池スタック
2.2.3 システムの運転方法
2.3 実用化に向けた課題
2.3.1 技術開発課題
2.3.2 規制緩和と標準化
2.4 おわりに
目次
水素エネルギー研究の現状と課題
水素製造技術
水素貯蔵技術と材料
水素貯蔵材料
燃料電池への利用〔ほか〕
著者等紹介
秋葉悦男[アキバエツオ]
(独)産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門統括研究員兼水素エネルギーグループグループ長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。