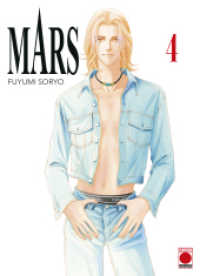出版社内容情報
☆急成長するDVDレコーダー市場。その技術の根幹をなす相変化光記録材料を総括!
☆次世代光ディスクとして注目のBlu-ray DiscおよびHD DVDの規格と要素技術!
☆5年後、10年後を目指した100GB〜TBクラスの超高密度光記録技術の研究開発動向!
☆相変化電子メモリーの開発動向も掲載!
【はじめに】
光記録技術と材料の進歩は真に目覚ましく,特に相変化記録材料の進展,短波長レーザの開発とが相まってビデオレコーダの大成功に繋がりました。然し,現在市販されているDVDの記録容量は4.7GBと小さく,次世代は30GB,更に第3世代には100GBの記録容量の開発が熱望されています。
思い起こしますと,1970年にECDのS.R.Ovshinskyによってカルコゲナイド膜の光記録が提案されて以来30年に渡る長い研究の結果,やっと2003年になって製品化の花が開きましたが,30GB,100GBの相変化光ディスクを世に出すには更に難しい問題が山積しています。
次世代光記録技術と材料のこの本を出版する理由は,1970年の提案以来30年の長く苦しい開発期間を要したDVDまでの研究・開発過程を明白にし,更に100GBまでの研究期間を短縮するために最良の道程を示唆するためです。そのため,DVD開発に従事されている各社の相変化記録の専門家の皆様にお願いして,第�編第1章に相変化光ディスク技術の現状と題して執筆をお願いしました。
第1編編第2章には,フラッシュメモリを基本とする半導体メモリカード(SDメモリカード等)に替わって,より大容量のメモリカードを目指す一方式として話題になっている相変化電子メモリ(PCRAM:Phase Change RAM)を執筆して頂きました。この相変化電子メモリも,1970年にS.R.Ovshinskyによって提案されたもので,30年近く冬眠していましたが,光記録材料の進歩により見直されたECDより新しい機能を付加してOUM(Ovonic Unifired Memory)として再提案されています。然し,この新しいメモリ(PCRAM)にも強敵が存在し(FRAM:強誘電体メモリ,MRAM:磁気メモリ),その将来性については予断を許しませんが,光ディスク材料の進歩と相まってDVDのように新しい市場を獲得して欲しいものです。
第1編編第3章には,ブルーレーザー光ディスク技術として,30GBを目指す新しい開発ターゲットを執筆して頂きました。この開発ターゲットも,2から3年の短い期間での完成を期待しています。
第2編は超高密度光記録として,100GBへの道程の方式:近接場光,3次元多層,単分子光等,の全く阿多rしい光記録方式を執筆して頂いています。これらの方式は,5から10年後の活躍が期待されるもので,その基礎的な研究が熱望されるものです。
これらの内容は執筆者のご協力により,意図した以上に充実した内容になっています。執筆者のご努力に厚くお礼申し上げると共に,光記録,電子材料の更なる発展の一助となれば幸いです。
2004年1月 奥田昌宏
【執筆者一覧(執筆順)】
奥田 昌宏 大阪府立大学 名誉教授
寺尾 元康 日立製作所 研究開発本部 ストレージテクノロジー研究センター 研究主幹
影山 喜之 (株)リコー 研究開発本部 光メモリー研究所 光メモリー材料研究センター 所長
柚須圭一郎 (株)東芝 研究開発センター 記憶材料デバイスラボラトリー 研究主務
小林 忠 (株)東芝 デジタルメディアネットワーク社 コアテクノロジーセンター 光ディスク開発部 主務
太田 威夫 Energy Conversion Devices,Inc., Optical and Electronic Memories Vice President
堀井 秀樹 Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム シニアエンジニア
J.H.Yi Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム
J.H.Park Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム
Y.H.Ha Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム
S.O.Park Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム
U-In Chung Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム
J.T.Moon Samusung電子(株) メモリ事業部 半導体研究所 工程開発チーム
保坂 純男 群馬大学 工学研究科 ナノ材料システム工学専攻 教授
山上 保 ソニー(株) ブロードバンドネットワークカンパニー・オプティカルシステム開発本部 BD開発部門 3部 統括部長
井出 達徳 NEC メディア情報研究所 主任研究員
本田 徹 工学院大学 工学部 電子工学科 助教授
森 伸芳 コニカミノルタオプト(株) 光学開発センター 担当課長
松下 辰彦 大阪産業大学 工学部 電気電子工学科 教授
久保 裕史 富士写真フイルム(株) 記録メディア研究所 主任研究員
富永 淳二 産業技術総合研究所 近接場光応用工学研究センター センター長
川田 善正 静岡大学 工学部 機械工学科 助教授
伊藤 彰義 日本大学 理工学部 電子情報工学科 教授
中川 活二 日本大学 理工学部 電子情報工学科 助教授
井上 光輝 豊橋技術科学大学 電気・電子工学系 教授
入江 正浩 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門 教授
【構成および内容】
第1編 相変化記録とブルーレーザー光ディスク
第1章 相変化光ディスク技術の現状
1.相変化光ディスク記録材料概論 ・・・・・・・・・・・・・・・3 奥田昌宏
1.1 はじめに
1.2 相変化光ディスクの記録容量,転送速度と記録材料
1.3 擬合金系材料と共晶系材料
1.4 Sbを多く含む新しい共晶系記録材料
2.GeSbTe系相変化光ディスク記録材料 ・・・・・・・・・・14 寺尾元康
2.1 組成と結晶化特性
2.2 結晶構造および結晶−非晶質の密度比較
3.AgInSbTe系相変化光ディスク記録材料 ・・・・・・・・・18 影山喜之
3.1 はじめに
3.2 相変化光ディスクの記録原理
3.3 AgInSbTe系相変化材料の特徴
3.4 記録層構造
3.5 AgInSbTe系相変化記録材料の応用
3.6 相変化記録材料の展望
4.多値記録相変化光ディスク材料 ・・・・・・・・・・・・・・・30 奥田昌宏
4.1 はじめに
4.2 結晶化差(Partial Crystallization Effect)による多値方式
4.3 記録径差(Mark Size Effect)による多値方式
4.4 半径方向幅変調MRWM(Mark Radial Width Modulation)多値記録
4.5 接線方向幅変調TMMR(Tangential Mark Size Modulation by Recrystallization)多値記録方式
5.多層記録相変化光ディスク記録材料 ・・・・・・・・・・・41 柚須圭一郎
5.1 はじめに
5.2 2層相変化ディスクの構成と作成方法
5.3 2層相変化ディスクの光学設計
5.4 L0層の光学設計
5.5 L1層の光学設計
5.6 2層相変化ディスクの消去特性
5.7 追記型多層ディスク
5.8 おわりに
6.相変化光ディスクの各方式(DVD-RAM) ・・・・・・・・・53 小林 忠
6.1 DVD-RAMディスクの規格
6.1.1 DVD-RAM ver.2.1の基本仕様
6.2 DVD-RWディスクの規格
6.2.1 DVD-RW ver.1.1の基本仕様
6.3 DVD-Rディスクの規格
6.3.1 DVD-R for General ver.2.0の基本仕様
7.相変化光ディスクの各方式(DVD+RW) ・・・・・・・・・・69 影山喜之
7.1 はじめに
7.2 DVD+RWフォーマットの特徴
7.2.1 DVD-ROMとの物理互換
7.2.2 ロスレスリンキング(DVD-ROM追記の実現・バックグランドフォーマット)
7.2.3 高周波ウォブルと位相反転方式によるアドレス
7.2.4 DVD+VRフォーマット
7.3 DVD+RWの記録方法
7.3.1 記録ストラテジー
7.3.2 OPC (Optimum Write Power Control)
7.4 DVD+RWメディア
7.4.1 メディアの構造
7.4.2 記録層材料
7.4.3 DVD+RWメディアの記録特性
7.5 おわりに
第2章 相変化電子メモリーの開発
1.ECD社における相変化電子メモリ−の開発動向 ・・・80 太田威夫
1.1 はじめに
1.2 アモルファス材料のオボニックスイッチングおよびメモリー現象
1.3 オボニックスイッチング材料
1.4 相変化光ディスク材料
1.5 Intel-Ovonyx が開発した180nm デザインルールOUM 4Mbit デバイス
1.5.1 デバイスの構造と駆動
1.6 今後の相変化不揮発性メモリーOUM の開発方向
1.7 おわりに
2.Samsung電子における相変化メモリ(PRAM)の開発現況 ・・・95
堀井秀樹,J.H.Yi,J.H.Park,Y.H.Ha,S.O.Park,U-In Chung,J.T.Moon
2.1 高速,低消費電力型不揮発性メモリの必要性
2.2 PRAMのメモリ・セルの基本構造と動作原理
2.3 PRAMデバイスの試作
2.4 デバイス シミュレーション
2.5 高抵抗 Ge2Sb2Te5膜の開発
2.6 N-doped GST膜を適用したPRAMの電気特性
2.7 まとめ
3.超高密度記録のための相変化チャンネルトランジスタの可能性 ・・・109
―1つのトランジスタで,メモリ格納とスイッチオンオフ制御― 保坂純男
3.1 はじめに
3.2 現状の固体素子メモリ(1トランジスタ1メモリ素子)
3.3 相変化チャンネルを持つ新しいメモリトランジスタ
3.3.1 メモリ機能
3.3.2 チャンネル電流制御機能
3.4 試作相変化チャンネルトランジスタ
3.5 ソースドレイン電流電圧特性の測定
3.5.1 不揮発メモリ特性
3.5.2 相変化チャンネル電流制御
3.6 おわりに
第3章 ブルーレーザー光ディスク技術
1.Blu-ray Disc技術の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 山上 保
1.1 はじめに
1.2 記録密度と容量
1.3 高密度記録
1.3.1 高密度化手法
1.3.2 カバー層
1.3.3 ごみ,傷,指紋耐性
1.4 記録信号フォーマット
1.4.1 変調方式 17PP
1.4.2 誤り訂正方式
(1)ロングディスタンスコード
(2)バーストインジケーター
(3)性能
1.4.3 アドレス方式
1.5 今後の展開
2.HD DVD技術の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 井出達徳
2.1 はじめに
2.2 HD DVDで採用された大容量化技術
2.3 HD DVD-ROM
2.4 HD DVDリライタブル
2.4.1 ランドグルーブ記録
2.4.2 L-H媒体
2.4.3 青紫色対応記録膜
2.4.4 WAPアドレス
2.4.5 記録再生特性
2.5 おわりに
3.帯青紫色半導体レーザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150 本田 徹
3.1 はじめに
3.2 GaN系III-V族半導体の材料特性とデバイス
3.2.1 III-V窒化物の結晶構造と格子定数
3.2.2 結晶歪みと自発・圧電分極の影響
3.2.3 GaN,GaInNの光学利得
3.3 GaN系III-V族半導体の結晶成長
3.3.1 GaN系III-V窒化物の基板選択
3.3.2 GaN系窒化物材料の結晶成長
3.4 素子構造に関する問題
3.4.1 活性層およびクラッド層の設計・製作
3.4.2 電極と電流注入
3.5 今後の問題点
3.6 おわりに
4.ブルーレーザーディスク用ピックアップレンズ ・・・・・160 森 伸芳
4.1 はじめに
4.2 レンズ設計
4.2.1 Blu-ray専用対物レンズ
(1)仕様
(2)温度特性
(3)色収差
4.2.2 補正光学系の設計
(1)球面収差補正光学系
(2)色収差の補正
4.2.3 互換光学系
(1)互換対物レンズの仕様
(2)波長選択素子(WSE)
4.3 試作結果
4.3.1 Blu-ray専用対物レンズ
4.3.2 球面収差補正光学系
4.3.3 互換対物レンズ
4.4 まとめと今後の課題
5.ブルーレーザー対応酸化物系追記型光記録膜 ・・・172 松下辰彦
5.1 はじめに
5.2 Zn-In-Ga-O系酸化物の結晶構造
5.3 WO3の結晶構造
5.4 RFマグネトロンスパッタ法で作製した光記録膜
5.4.1 Zn-GZO-IZO光記録膜
5.4.2 Zn-In-Ga2O3 光記録膜
5.4.3 In-Ga2O3 光記録膜
5.5 レーザーアブレーション法で作製した光記録膜
5.5.1 ZGO光記録膜
5.5.2 Ga2O3 -In2O3光記録膜
5.5.3 ZnO- In2O3光記録膜
5.5.4 WO3光記録膜
5.6 おわりに
6.有機色素を用いたブルーレーザー追記型光ディスク・・・203 久保裕史
6.1 はじめに
6.2 色素系ブルーディスクの媒体構造と製造工程
6.3 ブルーディスク用の有機色素
6.4 0.1mm厚カバー層
6.5 スタンパと成形基板
6.6 色素系ブルーディスクの性能評価と記録再生機構
6.7 おわりに
第2編 超高密度光記録技術と材料
第4章 近接場光を用いた超高密度光記録 富永淳二
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219
2.近接場光 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220
3.近接場光を応用した初期の光記録技術 ・・・・・・・221
4.21世紀の近接場光記録へ向けた挑戦 ・・・・・・・223
4.1 散乱型SNOMとその応用
4.2 光学非線形薄膜を応用した近接場光記録
第5章 3次元多層光メモリ 川田善正
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
2.多層記録光メモリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
3.短パルスレーザーによるデータの記録 ・・・・・・・・232
3.1 2光子吸収による3次元記録
3.2 光メモリにおける2光子過程
4.顕微光学系によるデータ再生 ・・・・・・・・・・・・・・235
4.1 反射型共焦点光学系によるデータ再生
4.2 微分コントラスト顕微光学系によるデータ再生
5.フォトンモード記録媒体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
6.多層構造を有する記録媒体を用いた光メモリ ・・239
7.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244
第6章 磁区応答3次元光磁気記録 伊藤彰義,中川活二
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
2.光磁気記録とその特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
3.多層多値光磁気記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
4.波長多重再生方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
5.2記録層の2波長多重再生と1波長再生 ・・・・・249
6.3記録層の2波長再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250
7.MAMMOSの多層化の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・250
8.再生パワー変化によるMAMMOSの多層化 ・・・253
第7章 ホログラム記録と材料 井上光輝
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256
2.ホログラムストレージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257
2.1 ホログラフィ
2.2 デジタル・ホログラフィの原理
2.3 記憶容量とデータ転送レート
3.デジタル・ホログラフィ記録装置 ・・・・・・・・・・・260
3.1 ホログラム記録装置の実際
3.2 スタンフォード・プラットフォーム
3.3 コリニア・ホログラム光記録装置
4.ホログラム記録材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
5.まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
第8章 フォトンモード分子光メモリと材料 入江正浩
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・268
2.フォトクロミック分子材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・269
3.近接場光メモリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271
4.単一分子光メモリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276
内容説明
次世代光記録技術と材料のこの本を出版する理由は、1970年の提案以来30年の長く苦しい開発期間を要したDVDまでの研究・開発過程を明白にし、更に100GBまでの研究期間を短縮するために最良の道程を示唆するためです。
目次
第1編 相変化記録とブルーレーザー光ディスク(相変化光ディスク技術の現状;相変化電子メモリーの開発;ブルーレーザー光ディスク技術)
第2編 超高密度光記録技術と材料(近接場光を用いた超高密度光記録;3次元多層光メモリ;磁区応答3次元光磁気記録;ホログラム記録と材料;フォトンモード分子光メモリと材料)
著者等紹介
奥田昌宏[オクダマサヒロ]
大阪府立大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。