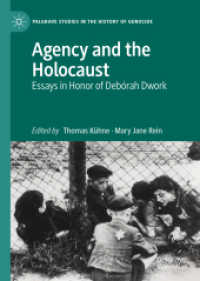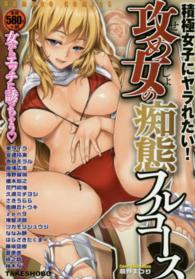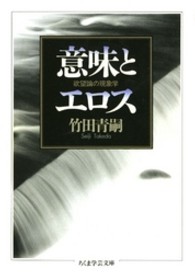出版社内容情報
★ バイオレメディエーション(環境修復)の実際!
★植代謝利用、植物の環境ストレス耐性向上技術の開発!!
★植物による有用物質生産技術の展望!!
【は じ め に】
バイオテクノロジーは,21世紀のキーテクノロジーである。バイオテクノロジーは,生命そのものに関する科学の急激な進歩に基づく巨大な技術革新である。それだけに,バイオテクノロジーは,広範な分野で飛躍的な変革をもたらす力を有しており,また,これまでの技術・産業では解決できなかった課題を解決し,われわれの社会生活を抜本から変革する潜在力を有している。
バイオテクノロジーの期待されている応用分野としては,医療・健康,食料,環境・エネルギーなど人間にとって極めて基礎的で大きな影響を与える分野がある。20世紀に起きた様々な科学技術の進歩にもかかわらず,これらの分野ではいまだ重大な課題が山積しており,バイオテクノロジーは,この現状を打破する大きな潜在的な力をもっていると期待されている。
本書は上記課題のうち,バイオテクノロジーと環境修復,有用物質生産を中心として,弊社で発行している雑誌,『BIO INDUSTRY』と『ECO INDUSTRY』の2001年から2003年にかけて掲載された関連する論文を編集して纏めたものである。 バイオテクノロジーと環境,地球再生に向けた植物バイオテクノロジーなどに関心を持たれるすべての方々に本書をお薦めする。
なお本書の編集に当たって,論文内容は雑誌発表当時のものに加筆をしておりません。ご了承願います。
2003年4月 (株)シーエムシー出版 編集部
【執筆者一覧(執筆順)】
今中 忠行 京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 教授
高井 研 海洋科学技術センター 極限環境微生物フロンティア研究システム 地殻内微生物研究領域 グループリーダー
稲垣 史生 海洋科学技術センター 極限環境微生物フロンティア研究システム 地殻内微生物研究領域 研究員
跡見 晴幸 京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 助教授
中村 聡 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 生命プロセス専攻 教授
岩崎 一弘 (独)国立環境研究所 生物多様性の減少機構の解析と保全プロジェクト 分子生態影響評価研究チーム 主任研究
員
橋本 顕子 (独)国立環境研究所 化学物質環境リスク研究センター 健康リスク評価研究室 NIESポスドクフェロー
福田 雅夫 長岡技術科学大学 工学部 生物系 教授
加藤 純一 広島大学大学院 先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻 教授
李 宣沃 広島大学大学院 先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻 博士課程後期
大竹 久夫 広島大学大学院 先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻 教授
満谷 淳 福山大学 生命工学部 海洋生物工学科 助教授
岡村 和夫 清水建設(株) 技術研究所 主席研究員
森川 弘道 広島大学大学院 理学研究科 数理分子生命理学専攻 教授
齋藤 貴 神奈川工科大学 工学部 応用化学科 教授
福居 俊昭 京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 助手
酒井 重男 酒井技術士事務所 所長
吉田 昌弘 鹿児島大学 工学部 応用化学工学科 助手
上村 芳三 鹿児島大学 工学部 応用化学工学科 助教授
横山 勝一 大協(株) 専務取締役
畑中 千秋 北九州工業高等専門学校 物質化学工学科 教授
幡手 泰雄 鹿児島大学 工学部 応用化学工学科 教授
黒田 浩一 京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 博士課程
植田 充美 京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 助教授
佐藤 伸 京都大学 木質科学研究所 バイオマス変換研究室 博士後期課程
渡辺 隆司 京都大学 木質科学研究所 バイオマス変換研究室 教授
西田 友昭 静岡大学 農学部 森林資源科学科 教授
門倉 伸行 (株)熊谷組 技術研究所 環境技術研究部 部長
竹田 三恵 (独)産業技術総合研究所 環境調和技術研究部門 非常勤職員
金原 和秀 (財)鉄道総合技術研究所 生物工学研究室 室長
早川 敏雄 (財)鉄道総合技術研究所 生物工学研究室 主任研究員
志村 稔 (財)鉄道総合技術研究所 生物工学研究室 主任研究員
潮木 知良 (財)鉄道総合技術研究所 生物工学研究室 研究員
京谷 隆 (財)鉄道総合技術研究所 生物工学研究室 副主任研究員
大坪 嘉行 理化学研究所 微生物学研究室 基礎科学特別研究員
永田 裕二 東北大学大学院 生命科学研究科 助教授
新名 惇彦 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授
幸田 勝典 (株)豊田中央研究所 第37研究領域 研究員
柴田 大輔 (財)かずさDNA研究所 植物遺伝子第2研究室 室長
山川 清栄 バイオテクノロジー開発技術研究組合 研究員
河内 孝之 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 助教授
河津 哲 王子製紙(株) 研究開発本部 森林資源研究所 上級研究員
小山 博之 岐阜大学 農学部 助教授
水谷 正子 サントリー(株) 先進技術応用研究所 研究員
落合 美佐 サントリー(株) 先進技術応用研究所 研究員
平井 正名 (株)豊田中央研究所 第37研究領域 特命主査
春日部芳久 (株)東洋紡総合研究所 研究員
橘 昌司 三重大学 生物資源学部 教授
石原 光朗 (独)森林総合研究所 きのこ・微生物研究領域 領域長
稲森 善彦 大阪薬科大学 微生物学教室 教授
森田 泰弘 大阪有機化学工業(株) 研究部 主任
野上 正行 名古屋工業大学 物質工学専攻 教授
【構成および内容】
序論 ―地球環境とバイオテクノロジー― 今中忠行
第?T部 地球の極限微生物
第1章 極限環境微生物生態系と特殊微生物の探索 高井 研・稲垣史生
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2.極限環境における微生物生態系と特殊微生物の探索の始まり ・・・5
3.熱水環境における微生物生態系と好熱菌の探索 ・・・・・・・・・・・6
4.地下微生物圏への窓としての熱水環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
5.深部地下環境における微生物生態系と古環境地球微生物の誕生・・11
6.今後の展望とバイオテクノロジーへの発展 ・・・・・・・・・・・・・・・・11
第2章 極限環境微生物の特殊能力の利用 跡見晴幸
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2.超好熱始原菌Thernococcus kodakaraensis KOD1株 ・・・・・・・17
3.耐熱性KOD DNA polymerase ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4.耐熱性DNA ligase ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
5.β-1,4結合を切断する糖質関連酵素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
6.タンパク質変性を抑制するchaperonin ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
7.高効率炭素固定反応を触媒するRubisco ・・・・・・・・・・・・・・・・・22
8.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第3章 極限環境微生物と極限酵素 中村 聡
1.微生物の多様性と極限環境微生物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
2.極限酵素の応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
2.1 好熱菌酵素の応用例
2.2 好アルカリ性菌酵素の応用例
3.極限酵素の機能向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
3.1 耐熱性の向上
3.2 反応至適pHの人工変換
4.将来の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第4章 バイオオーグメンテーションに向けた環境浄化微生物の開発 岩崎一弘・橋本顯子
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
2.水銀浄化微生物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
2.1 水銀除去微生物の作製
2.2 バイアルビンを用いた水銀除去試験
2.3 バイオリアクターによる水銀除去試験
3.揮発性有機塩素化合物分解微生物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
3.1 TCA,TCE分解微生物の分離
3.2 TCA,TCEの分解試験
3.3 揮発性有機塩素化合物分解特性
3.4 TCAおよびTCEの分解経路
4.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第?U部 環境バイオテクノロジー
第1章 難分解性物質の微生物分解 福田雅夫
1.難分解性物質と環境汚染 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
2.分解性微生物の分離 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
3.難分解性物質の分解様式と分解酵素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
3.1 芳香族骨格の分解
3.2 脱塩酸(脱ハロゲン)
4.分解微生物の育種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第2章 微生物による赤潮藻類の殺藻 加藤 純一・李 宣沃・大竹久夫・満谷 淳
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
2.赤潮殺藻細菌と赤潮殺藻ウイルス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
2.1 赤潮殺藻細菌
2.2 赤潮殺藻ウイルス
3.赤潮殺藻細菌の殺藻機構の解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
3.1 Pseudoalteromonas sp.A28株の赤潮殺藻機構の遺伝学的解析
3.2 Pseudoalteromonas sp.A28株の赤潮殺藻物質の精製と解析
3.3 その他の赤潮殺藻細菌の赤潮殺藻物質
4.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
第3章 微生物による汚染土壌の修復実例 岡村和夫
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
2.バイオスティムレーションの事例(軽油汚染浄土の分解) ・・・63
2.1 適用可能性調査
2.2 修復計画
2.3 修復結果
3.バイオオグメンテーションの事例(TCEの分解) ・・・・・・・・・・66
3.1 可能性調査結果
3.2 利用微生物と安全性評価
3.3 浄化システムと運転方法
3.4 利用微生物の調整方法および注入方法
3.5 実証試験結果
第4章 ファイトレメディエーションの新展開 森川弘道
1.はじめに―世界の動き― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
2.環境汚染問題の問題点―東京の排ガスを太平洋に排気できるか― ・・・70
3.移動する環境汚染 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
4.ファイトテクノロジー/ファイトレメディエーション ・・・・・・・・・・74
5.PCBを分解する植物根圏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
6.重金属/放射性元素の吸収除去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
7.有機/無機汚染物の分解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
8.水や揮発性物質のポンプアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
9.環境ホルモンの分解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
10.大気汚染の分解処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
11.窒素酸化物を窒素ガスに変換する植物!? ・・・・・・・・・・・・・・78
12.夢の植物―壁面パネル植栽― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
13.植物を植えるとどれくらいNOxが減るか ・・・・・・・・・・・・・・・79
14.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
第5章 水生植物による内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン化学物質)のファイトレメディエーション 齋藤 貴
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
2.ファイトレメディエーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
3.ファイトレメディエーションの現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
4.浄化機構の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
5.水生植物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
6.内分泌攪乱化学物質のファイトレメディエーション ・・・・・・・・84
6.1 重金属
6.2 ダイオキシン類
6.3 ビスフェノールA
6.4 フタル酸エステル類
7.市場規模,今後の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
第6章 生分解性プラスチックの微生物生産 福居俊昭
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
2.ポリヒドロキシアルカン酸(PHA) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
2.1 Ralstonia eutropha におけるPHA生合成
2.2 Aeromonasu caviae によるPHA生合成
2.3 Pseudomonasu 属細菌によるPHA生合成
3.組替え微生物によるPHA生産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
4.PHAの工業生産と今後の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
第7章 バイオ技術による排水処理と環境浄化 酒井重男
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
2.高度下水処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
3.下水汚泥からリンの回収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
3.1 リン除去細菌
3.2 リンの回収
4.新しい硝化・脱窒システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
5.上向流嫌気性スラッジ・ブランケット(UASB)法 ・・・・・・102
6.高濃度油脂排水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
7.油含有排水処理における酵素利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・103
8.余剰汚泥が発生しない活性汚泥処理プロセス ・・・・・・・104
9.膜利用排水処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
10.水溶性クーラント排水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
11.光合成細菌による浄化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
11.1 有機物,硝酸,リン,硫化水素の同時除去
11.2 ヘドロの浄化
12.バイオレメディエーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
12.1 微生物活性化法(バイオスティミュレーション)
12.2 微生物添加法(バイオオーギュメンテーション)
12.3 固定化微生物によるトリクロロエチレンの分解
12.4 白色腐朽菌による合成高分子の分解
13.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
第8章 固定化脱窒細菌を利用した地下水の硝酸性窒素除去技術の開発
吉田昌弘・上村芳三・横山勝一・畑中千秋・幡手泰雄
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
2.実験方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
2.1 脱窒細菌の培養および脱窒細菌固定化マイクロビーズの調製
2.2 脱窒能力の評価
3.結果および考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
3.1 固定化菌体および非固定化菌体を使用した回分実験
3.2 固定化菌体を使用した連続的な処理実験
4.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
第9章 酵母によるバイオレメディエーション
-重金属イオン検知・吸着・回収リサイクルシステム- 黒田浩一・植田充美
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120
2.新しいバイオ技術―細胞表層工学― ・・・・・・・・・・・・・・120
3.微生物細胞表層への重金属イオン吸着能の賦与 ・・・・・121
4.重金属イオン吸着ペプチドの細胞表層ディスプレイ ・・・・122
5.重金属イオン吸着タンパク質の細胞表層ディスプレイ ・・123
6.検知・回収によるバイオリサイクリングシステム ・・・・・・123
7.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
第10章 白色腐朽菌およびバイオミメティックラジカル反応による加硫および未加硫ゴムの分解
佐藤 伸・渡辺隆司
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
2.白色腐朽菌による加硫天然ゴムの分解 ・・・・・・・・・・・・127
3.白色腐朽菌のバイオミメティックフリーラジカル反応による加硫ゴムの分解 ・・・129
4.加硫ゴムによるリグニンの微生物分解の促進 ・・・・・・・131
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132
第11章 白色腐朽菌およびその酵素によるバイオレメディエーション 西田友昭
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133
2.リグニンを分解する微生物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
3.リグニン分解酵素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135
3.1 MnP
3.2 ラッカーゼ
4.白色腐朽菌による合成高分子の分解 ・・・・・・・・・・・・・135
4.1 ポリエチレンの生分解
4.2 ナイロンの生分解
5.白色腐朽菌によるアントラキノン系染料の脱色と無毒化・・・139
6.環境ホルモン類のエストロゲン様活性の除去 ・・・・・・・141
7.多環式芳香族炭化水素の分解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
8.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
第12章 遺伝子解析技術利用による油汚染土壌の生物処理評価 門倉伸行・竹田三恵
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146
2.遺伝子解析技術を利用した微生物動態解析手法 ・・・・147
2.1 遺伝子解析技術の生物処理への適用
2.2 微生物群集解析の手法
2.3 DGGE法による微生物群集解析
3.汚染土壌の生物処理評価への適用 ・・・・・・・・・・・・・・150
3.1 模擬汚染土壌浄化実験
3.2 実汚染土壌浄化実験?T
3.3 実汚染土壌浄化実験?U
4.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155
第13章 バイオ技術によるPCB処理法 金原和秀・早川敏雄・志村 稔・潮木知良・京谷 隆
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
2.紫外線分解・生物処理法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
3.パイロットプラントの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
4.KC1000の分解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
5.紫外線分解試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160
5.1 紫外線分解の高効率化
5.2 紫外線分解装置の改良
5.3 紫外線照射試験
5.4 IPAのリサイクル
5.5 水酸化ナトリウムのリサイクル
5.6 実証試験結果
6.生物処理試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163
7.安全性評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
8.汚染物処理への生物処理の応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・164
9.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
第14章 遺伝子操作土壌細菌を利用したPCB分解技術の開発 大坪嘉行・永田裕二
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
2.PCBを分解する土壌細菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
3.高効率PCB分解菌の育種への新しいアプローチ ・・・・167
3.1 PCB分解菌の遺伝的発現制御系
3.2 遺伝子操作による高効率PCB分解菌の育種
3.3 作製した株のPCB/ビフェニル分解能の評価
3.4 プロモーターを相同的組換えを利用して組み込む方法の利点
4.今後の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
第?V部 地球再生へ向けた植物バイオテクノロジー
第1章 植物による工業原料生産の意義 新名惇彦
1.禁断の実を口にした20世紀 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177
2.膨大な太陽エネルギー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
3.人類の救世主,遺伝子組換え技術 ・・・・・・・・・・・・・・・178
4.植物による工業原料の生産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179
5.NEDOニューサンシャインプロジェクト・・・・・・・・・・・・・・179
第2章 多重遺伝子導入とDNA連結技術の開発 幸田勝典・柴田大輔
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181
2.多重遺伝子導入の方策と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・181
2.1 交配による複数遺伝子の導入
2.2 逐次に遺伝子導入を行う方法
2.3 共形質転換法
2.4 単一ベクターを利用する方法
3.多重遺伝子導入に適した植物用ベクター ・・・・・・・・・・183
4.DNA多重連結の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186
第3章 シロイヌナズナの遺伝子プロモーターの系統的解析 山川清栄・河内孝之
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188
2.研究の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189
3.均一化cDNAライブラリーの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・190
4.cDNAライブラリーの配列情報解析とローカルデータベースの構築 ・・・191
5.cDNAマイクロアレイ系の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・192
6.マイクロアレイ系を用いた植物器官高発現遺伝子の選抜・・・194
7.器官高発現遺伝子のプロモーター領域のクローニングと一過性発現法による簡易活性検定・・195
8.今後の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198
第4章 遺伝子組換えユーカリによるパルプ資源の増産 河津 哲・小山博之
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200
2.パルプ資源の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200
2.1 紙パルプの生産現状
2.2 森林資源の利用
2.3 世界のパルプ資源の利用状況
2.4 海外での植林の必要性
3.パルプ用材としてのユーカリ新品種開発 ・・・・・・・・・・・202
4.ユーカリの組織培養技術と遺伝子組換え技術 ・・・・・・203
5.新品種開発の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
5.1 パルプ用材の質的改良
5.2 パルプ用材の量的改良
5.3 難溶性リン酸の可溶化能力の付与による酸性土壌耐性
6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207
第5章 ダイズによる高度不飽和脂肪酸の生産 水谷正子・落合美佐
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
2.高等植物による脂質生合成経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・210
2.1 新規脂肪酸合成
2.2 脂肪酸の鎖長延長
3.脂肪酸の質の改変 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
3.1 ラウリン酸生産ナタネ
3.2 高ステアリン酸含有ナタネ
3.3 高オレイン酸生産大豆
3.4 γ-リノレン酸生産植物
3.5 植物における超長鎖脂肪酸の生産
4.ダイズにおいて高度不飽和脂肪酸を生産するための戦略 ・・・213
4.1 真菌類の高度不飽和脂肪酸生合成系
4.2 海洋性細菌やラビリンチュラ類の高度不飽和脂肪酸合成系
5.ダイズによる高度不飽和脂肪酸生産に向けて ・・・・・・215
5.1 γ-リノレン酸の生産
5.2 ジホモγ-リノレン酸の生産
6.今後の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
第6章 病害抵抗性サツマイモの創出 平井正名
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218
2.抗菌ペプチドの特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219
3.病害抵抗性植物作出へ向けての抗菌ペプチドの問題点・・・219
4.抗菌ペプチドの機能改良 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220
4.1 ウサギCAP32(rCAP32)の選定
4.2 rCAP32の抗菌活性の増強
4.3 抗菌ペプチドの安定性の向上
5.抗菌ペプチド遺伝子のシロイヌナズナへの導入と病害抵抗性の評価・・・223
6.今後の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・225
第7章 ポリアミン合成酵素遺伝子による植物の環境ストレス抵抗性の改良 春日部芳久・橘 昌司
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226
2.ポリアミンの生合成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226
3.植物の環境ストレス抵抗性とポリアミン ・・・・・・・・・・・227
4.ポリアミン合成酵素遺伝子の取得と遺伝子発現の低温誘導性の確認・・・228
5.トランスジェニックシロイヌナズナの作成 ・・・・・・・・・・・229
6.遺伝子導入の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230
6.1 導入遺伝子の発現
6.2 内生ポリアミンレベル
7.環境ストレス耐性の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
7.1 冷温および凍結ストレス抵抗性
7.2 塩ストレス抵抗性
7.3 浸透圧ストレス抵抗性
7.4 その他の環境ストレス抵抗性
8.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・233
第8章 木質系バイオマスからキシロオリゴ糖の製造 石原光朗
1.木材のヘミセルロース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・235
2.木材キシランの抽出方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236
3.キシランからキシロオリゴ糖への変換方法 ・・・・・・・・・237
3.1 広葉樹キシランから酵素分解によって生産されるキシロオリゴ糖
3.2 広葉樹キシランから蒸煮処理によって生産されるキシロオリゴ糖
4.糖質と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・241
4.1 機能性食品素材としてのキシロオリゴ糖
4.2 キシロオリゴ糖の植物に対する生長促進機能
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243
第9章 青森ヒバ(ヒノキアスナロ)油の生理活性 稲森善彦・森田泰弘
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245
2.青森ヒバ酸性油の生理活性物質の探索 ・・・・・・・・・・246
3.抗木材腐朽菌活性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
4.殺シロアリ活性および殺屋内塵性ダニ活性 ・・・・・・・・247
5.抗微生物活性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
6.金属プロテアーゼ阻害活性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
7.植物成長阻害活性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
8.試験管内における哺乳類動物のがん細胞に対する細胞障害活性・・・249
9.考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250
10.応用展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251
11.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252
第10章 ヒノキチオールの安定性を飛躍的に高めた抗菌性無機ハイブリッド材料の開発 野上正行
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254
2.ヒノキチオールの無機化合物とのハイブリッド化 ・・・・・254
3.ハイブリッドの耐光性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256
4.ハイブリッド体の耐熱性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256
5.ハイブリッド体の防黴・抗菌性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257
6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259