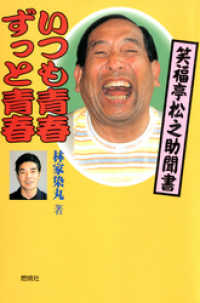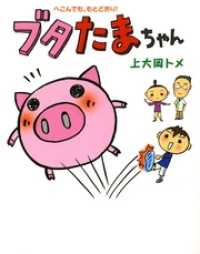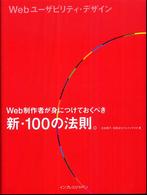出版社内容情報
★強誘電体材料の基礎から応用をこの一冊に集約!!
★第一線研究者による最新研究開発情報!!
はじめに
結晶を対称性で分類すると32要素の点群になる。32種類に分類された誘電体(絶縁体)結晶のうち,21種類は点対称中心を欠く。このうち20種類は圧電性を有していて圧電性誘導体(圧電体)である。圧電性誘電体結晶のうち10種類は自発分極を有していて有極性結晶である。この有極性結晶であることと焦電性結晶であることは同義であり,焦電性圧電性誘電体(焦電体)である。したがって残りの10種類の圧電性誘電体結晶は極性はなく焦電性を示さない。焦電性圧電性誘電体結晶のうちのあるものは電界印加により自発分極の向きを反転できるという性質,すなわち強誘電性を有し強誘電性焦電性圧電性誘電体(強誘電体)である。自発分極を有していて(すなわち焦電体であって)もそれが電界により反転できなければ強誘電体ではない。
強誘電体は強誘電性を持つとともに,焦電性も圧電性も誘電性も合わせもっており,また強誘電性においては通常これらの性質の大きさを示す定数も大きい。このようなわけで強誘電体は優れた焦電材料,圧電材料,誘電材料(キャパシタ材料)として広く用いられる。本書では強誘電体の単結晶,セラミックス,高分子フィルム,薄膜,液晶,コンポジットの製造法ならびにその特性と評価法について述べ,誘電性,焦電性,さらに光学的特性を応用したデバイスについて述べる。積層セラミックキャパシタや弾性表面波デバイス・圧電トランスの急速な発展には目をみはるものがある。
強誘電体を決定づける「(自発分極を有する誘電体であって)自発分極を電界により反転できる」という性質を徹底的に応用したデバイスとして強誘電体薄膜メモリーがある。強誘電体薄膜は誘電体(絶縁体)であるので電界を印可加しやすく,薄膜であるので数ボルト以下の低い電圧で自発分極を反転できる。さらにこれまでの研究により強誘電体薄膜の自発分極の反転速度が極めて速いことも見出された。高速・低電圧で反転可能な自発分極の2つの向きの情報を“0”と“1”に対応させるとランダムアクセス可能なメモリーが構成可能であり,また自発分極は本来,印加電圧を0に戻しても永久にその値が保持されるので強誘電体薄膜は不揮発性のランダムアクセスメモリーとして用いることができる。近年,強誘電体の究極の応用としてFRAM(あるいはFeRAM)や強誘電体薄膜ゲートFETばどが注目される所以強誘電体の定義そのものによる他では得られない特性のデバイスであるからである。PZT薄膜を用いたFRAMは既に広く実用化されており,今後の高集積化が楽しみである。
2002年5月には強誘電体応用に関する世界的に権威のある3つの学会ISAF,ISIF,FMAの合同の会議が奈良で開催される。
2001年12月 塩嵜 忠
執 筆 者 一 覧(執筆順)
塩嵜 忠 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授
小松隆一 山口大学 工学部 機能材料工学科 結晶工学研究室 助教授
竹中 正 東京理科大 理工学部 電気工学科 教授
田實佳郎 山形大学 工学部 機能高分子工学科 助教授
岡村総一郎 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 助教授
竹原貞夫 大日本インキ化学工業(株)液晶材料技術本部 液晶合成グループ グループマネージャー
楠本哲生 大日本インキ化学工業(株)液晶材料技術本部 主任研究員
坂野久夫 日本特殊陶業(株) 嘱託
岸 弘志 太陽誘電(株)総合研究部 材料開発部 部長
大里 齊 名古屋工業大学 工学部 材料工学科 教授
佐藤良夫 富士通(株)ペリフェラルシステム研究所 主席研究員
平間宏一 東洋通信機器(株)デバイスR&Dセンタ
斎藤哲男 元・東洋通信機器(株)デバイスR&Dセンタ
一ノ瀬昇 早稲田大学 理工学部 教授
松尾泰秀 (株)タムラ製作所 モバイルデバイス事業部 セラミックデバイス部
橋口裕作 (株)タムラ製作所 モバイルデバイス事業部 セラミックデバイス部
安達正利 富山県立大学 工学部 電子情報工学科 教授
上羽貞行 東京工業大学 精密工学研究所 教授
高山良一 松下電器産業(株)本社研究部門 主幹技師
Ⅰ 材料の製法,特性および評価
第1章 酸化物単結晶の育成と評価 小松隆一
1.単結晶とその育成法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.CZ育成炉と単結晶育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3.CZ法単結晶育成の実際と育成単結晶の評価 ・・・・・・・・・7
3.1 光学用四よう酸リチウム単結晶育成
3.2 四ほう酸リチウム単結晶の光学評価(紫外領域での波長変換特性)
4.まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第2章 強誘電体セラミックス 竹中 正
1. はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
2.強誘電体セラミックスとペロブスカイト構造 ・・・・・・・・・・・15
2.1 ペロブスカイト構造
2.2 Pbペロブスカイト二成分・三成分系強誘電体セラミックス
3.非鉛系ペロブスカイト構造強誘電体セラミックス ・・・・・・・20
3.1 BaTiO3セラミックス
3.2 KNbO3-NaNbO3系強誘電体セラミックス
3.3 (Bi1/2Na1/2)Ti03系強誘電体セラミックス
4. タングステン・ブロンズ型強誘電体セラミックス ・・・・・・・・32
4.1 (Ba1―x Srx)2NaNb5O15[BSNN]
4.2 BaNa1―x Bix/3Nb5O15[BNBN]
5.ビスマス層状構造強誘電体と粒子廃向型強誘電体セラミックス ・・・・33
5.1 ビスマス層状構造強誘電体(BLSF)
5.2 粒子配向型ビスマス層状構造強誘電体セラミックス
5.3PTGG法による高配向Bi層状強誘電体セラミックス
6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第3章 高分子材料 田實佳郎
1.高分子強誘電体の研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
2.高分子強誘電体の作製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
2.1 はじめに
2.2 合成法
2.2.1 ラジカル重合
2.2.2 蒸着重合
2.3film成形
2.3.1 溶融押し出し成形
2.3.2 溶媒キャスト
2.4 配向制御
2.4.1 一軸延伸
2.4.2 圧延
2.4.3 二軸延伸
2.5poling処理
2.5.1 熱poling
2.5.2 コロナpoling
2.6 工業的な制御技術の実際
3.特性と評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
3.1 はじめに
3.2 D-Eヒステリシス
3.3 スイッチング特性
3.4 圧電性
3.5 相転移
3.6 薄膜効果
3.7 電気光学効果
3.8 光デバイス
4.最近の研究から ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
4.1 二次元強誘電体
4.2 大きな電歪効果
4.3 負性容量
5.おわりに
第4章 薄膜 岡村総一郎
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
2.化学溶液堆積法 (Chemical Solution Deposition; CSD) ・・・74
3. 高周波スパッタリング法 (rf-Sputtering) ・・・・・・・・・・・・・・・78
4.有機金属化学気相堆積法 (Metalorganic Chemical Vapor Deposition; MOCVD) ・・・81
5.パルス・レーザー・デポジション法(Pulse Laser Deposition; PLD) ・・・・・85
6.液体ミスト化学堆積法 (Liquid Source Misted Chemical Deposition; LSMCD) ・・・・・88
7.電気泳動堆積法 (Electrophoretic Deposition; EPD) ・・・・・・90
8.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
第5章 強誘電性液晶 竹原貞夫、楠本哲生
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
2.液晶相と強誘電性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
3.強誘電性液晶材料の構成と要求特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・97
4. 強誘電性液晶の表示モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
5. 素子の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
6.液晶組成物の特性とその評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
7.強誘電性液晶化合物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
8.実用材料の調製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
9.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
第6章 コンポジット 坂野久夫
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
2.圧電コンポジットの構造による分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
3. 3-3型圧電コンポジット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
4.3-1型,3-2型圧電コンポジット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
5. 1-3型圧電コンポジット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
6. 0-3型圧電コンポジット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
7. 3-0型圧電コンポジット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
8. ハイドロホン用材料としての評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
9. 0-3型圧電コンポジットの応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115
10.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
Ⅱ 応用とデバイス
第1章 誘電応用
1.キャパシタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 岸 弘志
1.1 はじめに
1.2 積層セラミックコンデンサの技術動向
1.3 高容量積層セラミックコンデンサ用強誘電体材料の開発
1.3.1 低温焼結材料の開発
1.3.2 リラクサ材料の開発
1.3.3 耐還元性誘電体材料の開発
1.4 高容量Ni電極コンデンサの特性
1.5 おわりに
2.高周波誘電体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135 大里 齊
2.1 はじめに
2.2 マイクロ波誘電体に望まれる特性と応用
2.3 マイクロ波誘電体材料
2.4 材料の設計指針
2.5 今後の展望
第2章 圧電応用
1.弾性表面波デバイス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 佐藤良夫
1.1 はじめに
1.2 弾性表面波デバイス具体的構造と諸技術
1.3 弾性表面波の伝搬モードについて
1.4 圧電材料について
1.5 くし形電極設計技術について
1.6 高耐電力化とアンテナ分波器
1.7 微細パターンプロセスと高周波化
1.8 おわりに
2.フィルタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 平間宏一、斎藤哲男
2.1 はじめに
2.2 帯域通過水晶フィルタの設計
2.3 素子の設計
2.3.1 モノリシック・フィルタ素子の設計
2.4 実用例
2.4.1Chebyshev特性フィルタ
2.4.2遅延平坦フィルタ
2.4.3 HFF-MCF
2.4.4 その他のフィルタ
2.4.5 モノリシックフィルタの発展経緯
2.5 おわりに
3.センサ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172 一ノ瀬 昇
3.1 はじめに
3.2 超音波センサ
3.3 角速度センサ
3.4 赤外線センサ
4.アクチュエータ・超音波モータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185 上羽貞行
4.1 はじめに
4.2 圧電アクチュエータの種類と特徴
4.3 超音波モータの動作原理
4.4 超音波モータの典型例
4.5 超音波モータの特徴と応用例
5.圧電トランス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196 松尾泰秀、橋口裕作
5.1 まえがき
5.2 圧電トランスの原理と構造
5.2.1 原理
5.2.2 構造
5.2.3入出力・保持方法など
5.3 特徴と諸特性
5.3.1 形状
5.3.2 負荷依存性
5.3.3 発熱・非線形
5.3.4 材料
5.4 応用
5.4.1 小電流高圧電電源用
5.4.2 大容量大電流電源用
5.5 あとがき
第3章 焦電・光学応用
1.強誘電体薄膜を用いた焦電型赤外線センサ ・・・・・・・・・・・・・213 高木良一
1.1 まえがき
1.2 薄膜焦電材料
1.2.1 焦電材料のその薄膜化
1.2.2 焦電薄膜の作製
1.3 薄膜焦電型赤外線センサとその応用
1.3.1 マイクロポイント形センサ
1.3.2 アレイ形センサ
1.4 まとめ
2.光学応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226 安達正利
2.1 はじめに
2.2 光学用単結晶の育成法
2.2.1 LN,LTおよびKLN
2.2.2 ストイキオメトリー(化学量論比)組成LN,LT単結晶の連続チャージ二重るつぼ法による育成
2.2.3 K3Li2Nb5O15(KLN)単結晶の育成
2.3 光学特性
2.3.1 LN,LTおよびKLNの電気光学効果
2.3.2 非線形光学結晶
2.3.3 疑似位相整合(QPM)
2.3.4 フォトリフラクティブ効果
第4章 記憶・記録・表示デバイス 塩嵜 忠
1.強誘電体とメモリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242
2.強誘電体薄膜メモリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243
3.FRAM研究の最新の進歩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244
4.強誘電体ゲートFETメモリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248
5.強誘電体薄膜と液晶を組み合わせたメモリー性液晶表示デバイス ・・・・252
6.強誘電体メモリーの今後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254
Ⅲ 新しい現象および評価法 岡村総一郎
第1章 新しい材料,製法および評価法
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259
2.強誘電体材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259
2.1 新規Bi層状構造強誘電体
2.2 Bi2SiO5添加強誘電体材料
3.パターン作製法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262
3.1 電子線誘起反応微細加工プロセス
3.2 光感光性ゾル・ゲル溶液
3.3 インクジェットプリンティング(Inkjet Printing ; IJP)
4.評 価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・269
4.1 ヒステリシス測定回路
4.2 ヒステリシス測定におけるリーク電流等の影響
4.3 微細強誘電体キャパシタの電気的特性評価
4.4 強誘電体薄膜の微小領域評価
4.5 強誘電体薄膜の圧電ひずみ測定
4.6 強誘電体薄膜の分極ドメイン分布観測
4.7 その他の微小領域評価手法
4.8 熱刺激電流測定
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・283
内容説明
本書では強誘電体の単結晶、セラミックス、高分子フィルム、薄膜、液晶、コンポジットの製造法ならびにその特性と評価法について述べ、誘電性、焦電性、さらに光学的特性を応用したデバイスについて述べている。
目次
1 材料の製法、特性および評価(酸化物単結晶の育成と評価;強誘電体セラミックス;高分子材料 ほか)
2 応用とデバイス(誘電応用;圧電応用;焦電・光学応用 ほか)
3 新しい現象および評価法(新しい材料、製法および評価法)
著者等紹介
塩嵜忠[シオサキタダシ]
奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。