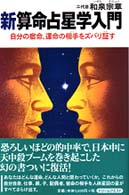出版社内容情報
☆ 酵素研究の第一人者60名による執筆!!
☆ 酵素工学の基礎から応用までの最新技術を網羅!!
はじめに
本書の前身である「新・酵素利用技術の展開」(監修:相澤益男,シーエムシー)が出版されたのは,1988年である。当時注目された新しい有用酵素の開発,新しい用途開発を中心に,各産業分野における酵素利用技術の現状と展望を第一線の研究者にご執筆いただいた。1980年代のバイオテクノロジーにおける酵素利用技術の進展がまとめられている。
21世紀を迎え,バイオテクノロジーは大変貌を遂げている。遺伝子工学がバイオテクノロジーの基盤技術として定着し,ゲノム解析が急展開するとともに,バイオインフォマティクスなど生命情報ベースのバイオテクノロジーの台頭がめざましい。いよいよバイオテク世紀といった感である。
本書は,進展のめざましいバイオテクノロジーの重要分野である酵素利用技術の最近の展開についてのオーバービューである。
現代のバイオテクノロジーを支える遺伝子工学と酵素利用技術には,二面性の密接な関連性がある。遺伝子工学では,ポリメラーゼなどの酵素が巧妙に利用されている。酵素を利用する重要な分野である。一方,遺伝子工学によって酵素の生産技術が一新された。たとえば,ホタルルシフェラーゼは,ホタルから抽出するのではなく,大腸菌等での遺伝子発現によって生産されるようになった。また,酵素を遺伝子工学で構造改変することによって耐熱性,ph特性などの酵素機能を改質できる道が拓けた。これらの分野は,酵素をエンジニアリングする酵素工学である。
1990年代の酵素利用技術をオーバービューするにあたって,「新規酵素の利用」,あるいは「酵素を利用する新規技術」に限定せず,「酵素工学技術の進展」にも目を向けた。第?T編酵素工学技術基礎,第?U編酵素利用技術,とした根拠である。膨大な領域を網羅することは本書の意図ではない。最近注目されている酵素工学技術と酵素利用技術に焦点を合わせ,それぞれのフロンティアでご活躍されている方々にご執筆いただいた。
本書が,酵素にかかわるバイオテクノロジーに関心をもつ医薬品,化学品,トイレタリー,コスメティックス,食品,臨床検査,などに関連する企業の企画,研究,開発担当者はもとより,酵素工学,酵素利用技術に関心をもつすべての方々にとって,新たなシーズの創出とニーズの拡大のきっかけになれば幸甚である。
2001年10月 東京工業大学 副学長,大学院生命理工学研究科 教授 相澤 益男
執筆者一覧(執筆順)
相澤益男 東京工業大学 副学長;生命理工学研究科 教授
中村 聡 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 生物プロセス専攻 助教授
扇谷 悟 独立行政法人産業技術総合研究所 生物遺伝子資源研究部門 分子環境適応研究グループ長
星野 保 独立行政法人産業技術総合研究所 生物遺伝子資源研究部門 遺伝子資源解析研究グループ
冨田耕右 関東学院大学 工学部 工業化学科 教授
津本浩平 東北大学大学院 工学研究科生物工学専攻 講師
郷田秀一郎 新エネルギー・産業技術総合開発機構 博士研究員
熊谷 泉 東北大学大学院 工学研究科生物工学専攻 教授
小畠英理 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 助教授
宇田泰三 広島県立大学 生物資源学部 教授
一二三恵美 広島県立大学 生物資源学部 助手
川端猛夫 京都大学化学研究所 有機合成基礎研究部門 助教授
近藤 匡 筑波大学人間総合科学研究科 消化器外科
平野 隆 独立行政法人産業技術総合研究所 分子細胞工学 部門
海老原隆 東京工業大学 生命理工学 研究科
川合修次 花王(株)生物科学研究所 第1研究室 室長
小林 徹 花王(株)生物科学研究所 第1研究室 主任研究員
中山泰一 (株)資生堂 研究開発本部 基盤研究センター 薬剤開 発研究所 主事
飯田年以 (株)資生堂 研究開発本部 基盤研究センター 創薬研究所 研究員
横山峰幸 (株)資生堂 研究開発本部 基盤研究センター 創薬研究所 副主幹研究員
杉浦 純 王子製紙(株)研究開発本部 新技術研究所 上級研究員
福永信幸 王子製紙(株)研究開発本部 製紙技術研究所 米子研究 室 上級研究員
坂井拓夫 近畿大学 農学部 教授;大阪府立大学 名誉教授
清水英俊 ノボザイムズジャパン(株)応用技術部 研究員
中嶋康之 ノボザイムズジャパン(株)応用技術部 研究員
何森 健 香川大学 農学部 教授
福田秀樹 神戸大学大学院 自然科学研究科 教授
白石眞人 (株)ニチレイ 技術開発センター シニアリサーチャー
大澤久夫 (株)ニチレイ 技術開発センター シニアリサーチャー
太田博道 慶應義塾大学 理工学部化学科 教授
広原日出男 滋賀県立大学 工学部 教授
大塚耕太郎 長瀬産業(株)研究開発センター 主任研究員
野本史樹 長瀬産業(株)研究開発センター 研究員
太田泰弘 マルキン忠勇(株)京都研究所 所長
大西 淳 マルキン忠勇(株)京都研究所 主任研究員
丸 勇史 マルキン忠勇(株)京都研究所 主幹研究員
塚田陽二 マルキン忠勇(株)専務取締役 生産技術本部長
跡見晴幸 京都大学大学院 工学研究科合成・生物化学専攻 助教授
田中渥夫 京都大学大学院 工学研究科合成・生物化学専攻 教授
宇山 浩 京都大学大学院 工学研究科材料化学専攻 助教授
小林四郎 京都大学大学院 工学研究科材料化学専攻 教授
酒井正春 北海道大学大学院 医学研究科 生体機能専攻 分子生 化学講座 助教授
増井昭彦 大阪府立産業技術総合研究所 材料技術部酵素応用グループ 主任研究員
藤原信明 大阪府立産業技術総合研究所 材料技術部酵素応用グループ 主任研究員
松本邦男 神奈川工科大学 工学部 応用化学科 教授
前田昌子 昭和大学 薬学部 教授
辰巳宏樹 キッコーマン(株)研究本部 課長職
黒坂啓介 ユニチカ(株)メディカル事業部 メディカル開発部 マネージャー
川瀬至道 ユニチカ(株)メディカル事業部 メディカル開発部
内田和之 ユニチカ(株)メディカル事業部 生化学営業部
近藤仁司 ユニチカ(株)メディカル事業部 メディカル開発部 部長 現:医用材料営業部 部長
吉岡俊彦 松下電器産業(株)健康医療開発推進室 リーダー
梅澤一夫 慶應義塾大学 理工学部 教授
今中忠行 京都大学大学院 工学研究科合成・生物化学専攻 教授
古本昭子 大阪府立産業技術総合研究所 材料技術部酵素応用グループ 客員研究員
蒲池利章 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 講師
大倉一郎 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 教授
割石博之 九州大学大学院 農学研究院 森林資源科学部門 助教授
構成および内容
序 章 相澤益男
?T 酵素工学基礎編
第1章 極限環境微生物と極限酵素 中村 聡
1 微生物の多様性と極限環境微生物 ………………………… 3
2 極限酵素の応用 …………………………………………… 4
2.1 好熱菌酵素の応用例
2.2 好アルカリ性菌酵素の応用例
3 極限酵素の機能向上 ……………………………………… 6
3.1 耐熱性の向上
3.2 反応至適pHの人工変換
4 将来の展望 ………………………………………………… 10
第2章 低温活性酵素の応用展開 扇谷 悟、星野 保
1 はじめに …………………………………………………… 13
2 低温活性酵素の名称、定義とその由来
3 低温活性酵素が低温で高い活性を示すメカニズム
4 低温活性酵素の人工創製
5 低温活性酵素の産業への応用 …………………………… 17
5.1 洗剤
5.2 食品加工
5.3 化学合成・廃棄物処理
5.4 バイオテクノロジー研究
5.5 バイオセンサー
6 おわりに
第3章 耐熱性酵素の新展開 冨田耕右
1 はじめに …………………………………………………… 22
2 耐熱性酵素と好熱菌
3 耐熱性酵素の利用展開 ………………………………… 22
3.1 臨床検査試薬
3.2 有機物質の合成
3.3 環境関係
4 おわりに
第4章 タンパク質工学による酵素の分子改質 津本浩平、郷田秀一郎、熊谷 泉
1 タンパク質工学と酵素 ………………………………… 37
2 部位特異的変異導入
2.1 熱安定性の向上
2.2 耐熱化性の向上
2.3 基質特異性の転換
3 無作為変異導入 ……………………………………… 39
3.1 進化分子工学概説
3.2 ライブラリーの構築
3.3 ファミリーシャッフリング
3.4 エキソンシャッフリング
4 ゲノム解析・構造ゲノム科学に基づいた分子改質 …… 42
4.1 ホモロジー検索による構造・機能予測
4.2 構造ゲノム科学と酵素の分子改質
5 あとがき
第5章 酵素ハイブリッドの創出 小畠英理、相澤益男
1 はじめに ……………………………………………… 47
2 化学結合による酵素ハイブリッド ……………………… 48
2.1 抗原性の低減と血中半減期の延長
2.2 有機溶媒中で働く酵素
2.3 磁性を有する酵素
3 遺伝子組換えによる酵素ハイブリッド ………………… 51
3.1 シーケンシャル反応を触媒する酵素ハイブリッド
3.2 触媒機能と結合機能のハイブリッド
4 おわりに
第6章 「スーパー抗体酵素」のチャレンジ 宇田泰三、一二三恵美
1 はじめに ……………………………………………… 57
2 抗体酵素の考え方の原点と今後 …………………… 58
3 いろんな天然型抗体酵素 …………………………… 59
3.1 核酸分解抗体酵素
3.2 血液凝固に関連した天然型抗体酵素
3.3 サイログロブリンに対する天然型抗体酵素
3.4 Thomasらによる酵素の活性化サイトに対する抗イディオタイプ抗体
3.5 その他の天然型抗体酵素
4 「スーパー抗体酵素」の特徴的性質-トリプシンとの比較- …… 63
5 「スーパー抗体酵素」のチャレンジ …………………… 66
6 おわりに
第7章 エナンチオマーを分別する人工酵素 川端猛夫
1 はじめに ……………………………………………… 71
2 アルコール類のエナンチオ区別アシル化-酵素から人工の分子触媒へ- … 71
3 エナンチオマーの分別反応-ラセミ体アルコールの速度論的分割- ……… 73
4 加速性による選択性の発現 ………………………… 75
5 エナンチオ区別アシル化のメカニズム ……………… 76
6 エナンチオ区別アシル化触媒(人工酵素)の合成 …… 78
7 おわりに
第8章 活性酸素関連酵素の応用展開 近藤 匡、平野 隆
1 はじめに ……………………………………………… 82
2 SODによる臓器障害の防止 ………………………… 83
3 DIVEMA-SOD …………………………………… 84
4 DIVEMA-SODによる肝虚血再灌流障害の予防 … 86
5 おわりに
第9章 生体外タンパク質合成の新展開 海老原隆、相澤益男
1 はじめに ……………………………………………… 90
2 生体外タンパク質合成とは …………………………… 90
3 生体外タンパク質合成研究の流れ …………………… 91
4 生体外タンパク質合成研究の現状 …………………… 91
4.1 タンパク質合成の世界標準技術を目指して-ロシュvs三菱化学-TOYOBOなど-
4.2 ラピッドトランスレーションシステム(ロシュ)
4.3 PROTEIOS(三菱化学-TOYOBOなど)
4.4 生体外タンパク質合成の覇者は?
5 生体外タンパク質合成の応用展開 …………………… 94
5.1 機能/構造解析への展開
5.2 進化分子工学システムへの展開
5.3 イムノアッセイへの展開
5.4 生命システムの再構築を目指して
6 おわりに
?U 酵素利用技術編
第1章 トイレタリー・コスメティクス
1 トイレタリーと酵素 ………………………………… 101 川合修次、小林 徹
1.1 はじめに
1.2 洗剤用酵素
1.3 その他のトイレタリー用酵素
1.4 おわりに
2 化粧品に使用される酵素 …………………………… 110 中山泰一
2.1 はじめに
2.2 化粧品に利用されている酵素は限られている
2.3 化粧品に配合される酵素
2.4 おわりに
3 酵素を用いた植物由来の新しい化粧品原料の開発 … 117 飯田年以、横山峰幸
3.1 はじめに
3.2 新しい植物原料(CRS)の開発
3.3 本原料の特徴
3.4 まとめ
4 酵素によるクラフトパルプ漂白技術 ………………… 125 杉浦 純、福永信幸
4.1 はじめに
4.2 クラフトパルプについて
4.3 キシラナーゼによるクラフトパルプの漂白
4.4 米子工場における酵素の自製と操業
4.5 実用化の動向
4.6 将来展望
4.7 おわりに
5 バイオ精錬 ………………………………………… 135 坂井拓夫
5.1 はじめに
5.2 綿繊維の構造と精練
5.3 バイオ精練に使用する酵素
5.4 PPaseによる綿布の精練
5.5 バイオ精練の特徴
5.6 バイオ精練に使用する酵素の安全性
5.7 おわりに
第2章 食品・飼料
1 ペクチンメチルエステラーゼ-より有利な果実加工の手段として- …… 147 清水英俊
1.1 はじめに
1.2 酵素開発の背景
1.3 酵素反応のメカニズム
1.4 酵素の評価
1.5 おわりに
2 飼料と酵素 ………………………………………… 154 中嶋康之
2.1 はじめに
2.2フィターゼの利用
2.3 多糖類分解酵素の利用
2.4 おわりに
3 希少糖、D-プシコースの酵素合成 ……………… 160 何森 健
3.1 はじめに
3.2 D-プシコースの生産に用いる酵素、D-タガトース3-エピメラーゼについて
3.3 D-タガトース3-エピメラーゼを用いたD-プシコースへの転換反応
3.4 反応液、D-フラクトースとD-プシコースからのD-プシコースの分離
3.5 おわり
4 廃食用油からのディーゼル燃料の生産 …………… 167 福田秀樹
4.1 はじめに
4.2 バイオディーゼル燃料生産の反応-スキームおよび製造法の比較-
4.3 酵素によるメタノリシス反応
4.4 wholw cell biocatalyst による反応
4.5 おわりに
5 冷凍状態での機能性食品素材の酵素生産 ………… 176 白石眞人、大澤久夫
5.1はじめに
5.2 凍結と酵素反応
5.3 凍結で促進される化学反応
5.4 凍結状態でのデキストラナーゼの反応
5.5 チロシナーゼ関連酵素の利用
5.6 おわりに
第3章 ファインケミカル合成
1 精密酵素合成の新展開 …………………………… 188 太田博道
1.1 酵素および酵素反応の特徴――何を有機合成に生かすか
1.2 ES錯体形成と結合エネルギー
1.3 酵素の官能基選択性――ニトリルの加水分解
1.4 疎水性反応場としての酵素
1.5 酵素反応の選択性のチューニング
1.6 酵素反応の溶媒
1.7 おわりに
2 加水分解酵素によるキラルテクノロジー …………… 201 広原日出男
2.1 背景
2.2 実用化条件
2.3 L-アミノ酸の合成-大きなインパクトを与えた初期の成果-
2.4 2級アルコールの単一鏡像体合成-立体反転と組合せ-
2.5 キラルなα-置換カルボン酸の合成
2.6 5-置換ヒダントインからのD-アミノ酸の合成-環境負 荷低減工業生産プロセス-
2.7 必須条件のまとめ
3 生体触媒を利用した光学活性アルコールの工業生産 … 213 大塚耕太郎、野本史樹
3.1 はじめに
3.2 光学活性3-キヌクリジノール
3.3 光学活性グリシドール
3.4 光学活性2-メチルブタン酸と2-メチルブタノール
3.5 光学活性体の開発事業
4 シアル酸の酵素合成 ……………………… 223 太田泰弘、大西 淳、丸 勇史、塚田陽二
4.1 はじめに
4.2 従来技術
4.3 シアル酸の完全酵素合成法の開発
4.4 おわりに
第4章 機能材料
1 固定化生体触媒 …………………………………… 230 跡見晴幸、田中渥夫
1.1 はじめに
1.2 多種多様な固定化の方法
1.3 細胞を担体とした固定化法:細胞表層工学
2 酵素触媒重合による高分子機能材料 …………… 239 宇山 浩、小林四郎
2.1 はじめに
2.2 フェノール類の酵素触媒重合
2.3 機能性ポリフェノールの酵素合成
2.4 酵素モデル錯体を用いるフェノール類の酸化重合
2.5 機能性ポリエステルの酵素合成
2.6 おわりに
第5章 遺伝子工学・タンパク質・細胞工学
1 酵素マーカーによる遺伝子発現の解析 ……………… 253 酒井正春
1.1はじめに
1.2 遺伝子発現解析に用いられるマーカー酵素遺伝子
1.3 遺伝子発現解析における酵素遺伝子の活用
1.4 おわりに
2 タンパク質工学と酵素利用技術-写真フィルムリサイクルに適した酵素へのアルカリプロテアーゼの改変- … 263
増井昭彦、藤原信明
2.1 はじめに
2.2 酵素の耐熱化
2.3 Bacillus sp. B21-2株の生産するAprN
2.4 酵素耐熱化のための分子設計基準
2.5 AprNの耐熱化
2.6 変異酵素によるX線フィルムの分解
2.7変異酵素の繰り返し利用
2.8 おわりに
第6章 診断・分析・医薬
1 臨床検査用酵素の新展開 ………………………………… 271 松本邦男
1.1 はじめに
1.2 液状試薬用酵素
1.3 酵素サイクリング用酵素
1.4 ヒト型酵素
1.5 その他
1.6 おわりに
2 生物発光反応を検出に用いた生体成分の酵素免疫化学的測定法 …… 284 前田昌子
2.1 はじめに
2.2 生物発光反応を用いる酵素活性の測定とそのイムノアッセイ検出系への応用
2.3 おわりに
3 ホタルルシフェラーゼによる微生物迅速判別法 ……………………… 298 辰巳宏樹
3.1 はじめに
3.2 ルシフェラーゼの改変
3.3 大腸菌群の測定
3.4 黄色ブドウ球菌の測定
3.5 今後の展望
4 ソルトビトール測定用酵素-ソルビトール測定とその臨床的意義- …… 308
黒坂啓介、川瀬至道、内田和之、近藤仁司
4.1 はじめに
4.2 ソルビトール測定の臨床的意義
4.3 ソルビトール測定法
4.4 ソルビトール測定用酵素
4.5 おわりに
5 バイオセンサ …………………………………………………… 316 吉岡俊彦
5.1 はじめに
5.2 電気化学酵素センサ
5.3 ディスポーザブル電気化学酵素センサ
5.4 乳酸センサ
5.5 血糖センサへの応用
5.6 血糖自己測定用グルコースセンサ
5.7 おわりに
6 酵素阻害剤の開発 ……………………………………………… 325 梅澤一夫
6.1 はじめに
6.2 酵素阻害剤と医薬
6.3 チロシンホスファターゼの役割と種類
6.4 チロシンホスファターゼ阻害剤のスクリーニング
6.5 2型糖尿病とチロシンホスファターゼ
6.6 チロシンホスファターゼ阻害剤によるインスリン関連シグナル伝達の増強
6.7 ニトロソアミンのない誘導体の分子デザイン
6.8 おわりに
第7章 環境
1 環境工学と酵素利用技術 ……………………………………… 334 今中忠行
1.1 はじめに
1.2 PCR(Polymerase Chain Reaction)法
1.3 耐熱性DNAポリメラーゼ
1.4 KOD DNAポリメラーゼの立体構造
1.5 おわりに
2 酵素を用いた切削加工油の腐敗制御技術 ……………………… 341 藤原信明、増井昭彦、古本昭子
2.1 はじめに
2.2 溶菌酵素
2.3 切削加工油
2.4 溶菌酵素生産菌の分離
2.5 溶菌酵素による殺菌効果
2.6 溶菌酵素生産菌の性質
2.7 溶菌酵素の性質
2.8 今後の展開
3 メタンモノオキシゲナーゼ ………………………………………… 350 蒲池利章、大倉一郎
3.1 はじめに
3.2 菌体を用いたメタノール生産
3.3 メタノール生産のための培養条件
3.4 半回分式メタノール合成法
3.5 メタン資化細菌を用いたポリヒドロキシブタン酸の生産
3.6 ハロゲン化炭化水素の分解
3.7 膜結合型MMOの性質
3.8 おわりに
4 リグニンペルオキシダーゼの作用機構と環境浄化への応用 ……… 361 割石博之
4.1 リグニン分離能の環境浄化への適用
4.2 リグニンペルオキシダーゼの諸性質
4.3 リグニンペルオキシダーゼの反応機構
4.4 芳香族性環境汚染物質分解への適用
-

- 和書
- 両手を開いて