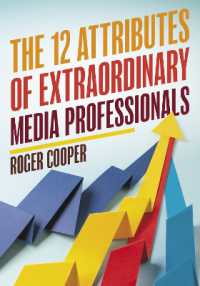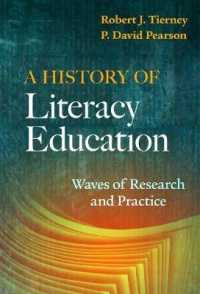出版社内容情報
★地球温暖化対策の決めて,CO2固定化・隔離の最新研究を網羅
★産学官の総勢33名の第一線研究者による本格的成書
執筆者一覧(執筆順)
乾 智行 京都大学名誉教授
湯川英明 地球環境産業技術研究機構・微生物分子機能研究室
道木英之 東洋エンジニアリング(株)・技術研究所・環境技術G
宮本和久 大阪大学大学院薬学研究科・教授
藏野憲秀 (財)海洋バイオテクノロジー研究所・釜石研究所
北島佐紀人(財)地球環境産業技術研究機構・植物分子生理研究室
富澤健一 (財)地球環境産業技術研究機構・植物分子生理研究室
松永 是 奈良先端科学技術大学院大学・教授
横田明穂 東京農工大学・工学部・教授
真野 弘 (財)地球環境産業技術研究機構・化学的CO2固定化研究室
松本公治 関西電力(株)・総合技術研究所・環境技術研究センター
三村富雄 関西電力(株)・総合技術研究所・環境技術研究センター
飯島正樹 三菱重工業(株)・化学プラント技術センター
光岡薫明 三菱重工業(株)・広島研究所
大隅多加志(財)電力中央研究所・我孫子研究所・上席研究員
増田重雄 地球環境産業技術研究機構・ CO2海洋隔離プロジェクト室
小出 仁 工業技術院・地質調査所・環境地質部
鈴木 款 静岡大学・理学部・教授
田中晃二 岡崎国立共同研究機構・分子科学研究所・教授
柳田祥三 大阪大学大学院・工学研究科・教授
和田雄二 大阪大学大学院・工学研究科・助教授
北村隆之 大阪大学大学院・工学研究科・助手
榧木哲人 東京工業大学大学院・理工学研究科
碇屋隆雄 東京工業大学大学院・理工学研究科・教授
佐々木義之 資源環境技術総合研究所・温暖化物質循環制御部
杉本 裕 東京理科大学・工学部・工業化学科・助手
井上祥平 東京理科大学・工学部・工業化学科・教授
瀧田祐作 大分大学・工学部・応用化学科・教授
加藤三郎 (株)島津製作所・航空機器事業部・技術部
斉藤昌弘 資源環境技術総合研究所・温暖化物質循環制御部
荒川裕則 工業技術院・物質工学工業技術研究所・基礎部
丹羽宣治 (財)地球環境産業技術研究機構・化学的CO2固定化研究室
鈴木栄二 (財)地球環境産業技術研究機構・環境触媒研究室
構成および内容
第1章 総 論 乾 智行
〈CO2固定化・隔離の生物化学的方法 編〉
第2章 バイオマス利用
1 微生物機能によるCO2 on-site処理技術 湯川英明
1.1 はじめに
1.2 微生物とCO2
1.3 on-site処理技術をめざして
1.4 おわりに
2 バイオマス資源とCO2問題 道木英之
2.1 はじめに
2.2 自然界の炭素の循環
2.3 バイオマスの特徴
2.4 バイオマス資源と生産
2.4.1 バイオマス資源量
2.4.2 利用可能なバイオマスと量とその特質
2.4.3 光合成による植物の生産
2.4.4 植物による光エネルギー利用効率
2.5 バイオマス変換技術
2.6 バイオマス利用の研究開発動向
2.7 おわりに
第3章 細菌・藻類の利用 宮本和久,藏野憲秀
1 はじめに
2 海洋生物によるCO2固定
3 微細藻類の大量培養によるCO2固定技術
3.1 微細藻類によるCO2固定
3.2 高効率株の探索
3.3 高効率株の育種
4 微細藻類バイオマスの変換・有効利用
4.1 有効利用の可能性
4.2 バイオマスエネルギーシステム
4.3 オイルへの変換
4.4 微細藻類バイオマスを原料とする水素生産
5 おわりに
第4章 植物の利用 北島佐紀人,富澤健一,横田明穂
1 はじめに
2 砂漠環境下における植物と光合成
3 活性酸素除去系の改善
4 RuBisCOの改良の試み
5 光呼吸系の向上の試み
6 CO2濃縮構成の導入の試み
7 気孔を介した蒸散とCO2取り込みの制御の改良
8 耐塩性の向上の試み
9 組み換え遺伝子の葉緑体ゲノムへの組み込み
10 今後の技術課題
第5章 海洋生物の利用 松永 是
1 はじめに
2 海洋生物のスクリーニング
3 海洋生物を利用したCO2固定
4 炭酸固定微生物による有用物質生産
5 おわりに
〈CO2固定化・隔離の物理化学的方法 編〉
第6章 二酸化炭素の分離
1 膜分離 真野 弘
1.1 はじめに
1.2 高分子膜の開発
1.3 促進輸送膜の開発
1.4 膜分離プロセスの検討
1.5 他の分離膜の開発状況
1.6 おわりに
2 吸着分離 真野 弘
2.1 はじめに
2.2 CO2吸着分離プロセス
2.3 火力発電プラントでの試験例
2.4 おわりに
3 化学吸収法による炭酸ガス分離技術 松本公治,三村富雄,飯島正樹,光岡薫明
3.1 はじめに
3.2 化学吸収法の原理とパイロットプラントの構成
3.3 省エネ吸収剤の開発
3.4 石炭焚き条件試験結果
3.5 火力発電所と炭酸ガス分離プロセスの連結システム
3.6 おわりに
第7章 CO2の海洋隔離 大隅多加志,増田重雄
1 はじめに
2 技術のねらい
3 技術の有効範囲はどこまでか
4 技術開発目標の設定
5 溶解型海洋隔離の科学的基礎
6 「二酸化酸素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」の到達点
6.1 日本近海での海洋隔離に係わる環境影響評価のための調査研究
6.2 CO2中層放流に伴う環境影響予測技術の開発
7 研究の将来展望
8 まとめ
第8章 CO2の地中隔離 小出 仁
1 CO2地中隔離の意義
2 枯渇油・ガス田および閉塞帯へのCO2地中隔離
3 非閉塞帯水槽へのCO2地中隔離
4 CO2の地中隔離能力と経済性
5 温室効果ガス排出削減目標と地中隔離の役割
6 CO2の海洋低下隔離
7 CO2圧力による天然ガス回収(CO2-EGR)
8 地中メタン生成細菌によるメタン再生
第9章 CO2鉱物隔離 鈴木 款
1 はじめに
2 炭酸塩生成による固定化
2.1 炭酸カルシウムの溶解度と沈殿:海水を用いる可能性
2.2 ケイ酸塩鉱物との反応による炭酸塩の生成
3 CO2・CO32-を含む鉱物生成による隔離
3.1 クラスラシル化合物による固定化
3.2 ハイドロタルサイト型化合物によるCO2固定化
4 まとめ
〈CO2固定化・隔離の化学的方法 編〉
第10章 光化学的二酸化炭素還元反応 田中晃二
1 はじめに
2 光化学的反応
3 CO錯体触媒によるCO2還元反応
4 レニュウム錯体によるCO2還元反応
5 ルテニュウム錯体によるCO2還元反応
6 錯体媒体による光化学的CO2還元の問題点
7 おわりに
第11章 電気化学・光電気化学的二酸化炭素固定 柳田祥三,和田雄二,北村隆之
1 はじめに
2 電気化学的
2.1 基本的手法と評価
2.2 金属を陰極とする還元
2.3 電極触媒による低電位還元
2.4 電気化学的カルボニル化
3 光電気化学的還元
3.1 化合物半導体によるCO2還元
3.2 光増感触媒によるCO2還元
3.3 有機分子へのCO2の可視光固定
4 展望第
12章 超臨界二酸化炭素を用いる固定化技術 榧木哲人,碇屋隆雄
1 はじめに
2 無触媒カルボキシル化反応
3 超臨界二酸化炭素の水素化反応
4 アルキンと二酸化炭素との還化反応によるピロン合成
5 炭酸エステル合成
5.1 炭酸ジメチル合成反応
5.2 感情炭酸エステル合成
5.3 二酸化炭素とエポキシドの開環共重合
6 おわりに
第13章 CO2を利用する有機合成 佐々木義之
1 はじめに
2 CO2の反応過程
3 CO2への求核反応
4 CO2の転移を伴う反応
5 脱水縮合反応
6 CO2の付加反応
7 CO2生成反応
8 おわりに
第14章 高分子合成 杉本 裕,井上祥平
1 はじめに
2 二酸化炭素とエポキシドの共重合
2.1 有機亜鉛系触媒
2.2 無機亜鉛系触媒
2.3 構造明確な亜鉛錯体触媒
2.4 アルミニウム系触媒
2.5 希土類系触媒
3 二酸化炭素とエポキシド以外の環状モノマーの共重合
3.1 二酸化炭素とオキセタンの共重合
3.2 二酸化炭素とエピスルフィドの共重合
3.3 二酸化炭素とアジリジンの共重合
4 二酸化炭素と非極性炭化水素モノマーの共重合
4.1 二酸化炭素とジエンの共重合
4.2 二酸化炭素とジインの共重合
5 二酸化炭素と極性ビニルモノマー共重合
5.1 二酸化炭素とビニルエーテルの共重合
5.2 二酸化炭素,環状ホスホナイト,アクリルモノマーの三元共重合
6 二酸化炭素とジアミンの縮合重合
7 二酸化炭素とジオールのアルコキシドから生じるアルキルカルボナート塩と,
ジハライドの出力の縮合重合
第15章 直接分解
1 CO2の直接分解 瀧田祐作
1.1 はじめに
1.2 プラズマによるCO2のCOへの分解
1.3 マグネタイトによる分解
1.4 触媒法によるメタンをもちいた分解
2 CO2のCH4による接触還元反応NASA技術とそのCO2固定化への応用 加藤三郎
2.1 はじめに
2.2 NASAにおける閉鎖環境制御生命維持コンセプト
2.3 化学的固定基本反応
2.4 CO2のCH4による接触還元反応例
2.5 バイオマスエネルギーを利用したCO2固定化技術について
2.6 おわりに
第16章 触媒水素化
1 CO2の接触水素化によるメタノール合成
―NIRE/RITE共同研究を中心にして― 斉藤昌弘
1.1 はじめに
1.2 メタノール合成の特徴や意義
1.3 メタノール合成反応の概念
1.4 NiRE/RITE共同研究開発の概要と主な成果
1.5 おわりに
2 エタノール,炭化水素合成 荒川裕則
2.1 エタノール合成
2.1.1 はじめに
2.1.2 鉄―カリウム系固形触媒によるエタノールの高収率合成
2.1.3 ロジウム系固形触媒によるエタノールの高選択的合成
2.1.4 ルテニウム系錯体触媒によるエタノール効率的な合成
2.2 炭化水素合成
2.2.1 はじめに
2.2.2 低級パラフィンの選択的合成
2.2.3 低級オレフィンの選択的合成
2.2.4 ガソリン留分の合成
2.3 おわりに
〈変換システム〉
第17章 CO2変換システムと経済評価 丹羽宣治
1 システムの概念
1.1 はじめに
1.2 システムの構成
2 概念結果
2.1 基本設備と施設計区分
2.2 システム設計のための前提条件
2.3 コスト算出基準
3 設計結果
3.1 必要ユーリティおよび建設素材
3.2 海上輸送システム
3.3 全体配置計画図
4 自然エネルギーによる発電システムの概念設計
4.1 水力発電
4.2 太陽熱発電
4.3 太陽光発電
5 本システムの建設費と経済性
5.1 設備建設コスト
5.2 コスト
6 本システムの評価
第18章 CO2複合変換システム構想 鈴木栄二
1 はじめに
2 ソーラハイブリット燃料システムの提案
3 太陽熱発電による水素生産
4 太陽熱化学によるメタン改質反応とソーラーメタノール
4.1 太陽エネルギー効率
4.2 太陽熱化学のCO2排出抑制効果
5 太陽熱化学による石炭の改質:ソーラーメタノールとソーラ水素生産
6 太陽エネルギー化学工場の工学的考察
7 まとめ
内容説明
本書は、二酸化炭素の化学的変換と大量隔離の最新技術について、斯界の第一線で活躍中の多数の研究者によって、執筆されたものである。
目次
CO2固定化・隔離の生物化学的方法編(バイオマス利用;微細藻類によるCO2固定 ほか)
CO2固定化・隔離の物理化学的方法編(二酸化炭素の分離;CO2の海洋隔離 ほか)
CO2固定化・隔離の化学的方法編(光化学的二酸化炭素還元反応;電気化学・光電気化学的二酸化炭素固定 ほか)
CO2変換システム編(CO2変換システムと経済評価;CO2の複合変換システム構想)
-
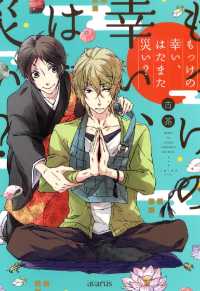
- 電子書籍
- もっけの幸い、はたまた災い? 月刊コミ…