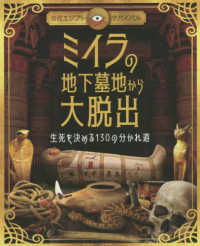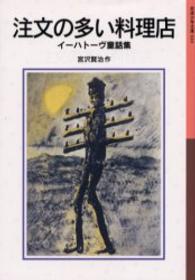出版社内容情報
執筆者一覧
(所属は1992年時点。カッコ内は2000年6月現在)
片山善章 国立循環器病センター 臨床検査部
星野 忠 日本大学 医学部
河野均也 日本大学 医学部
緇荘和子 東京医科大学 臨床病理学教室 (現・東京医科大学 臨床病理学教室、東洋公衆衛生学院)
藤巻道男 東京医科大学 臨床病理学教室 (現・東京医科大学名誉教授、東洋講習衛生学院 学院長)
小栗豊子 順天堂大学附属病院 中央臨床検査室 (現・順天堂大学付属病院 臨床検査部)
猪狩 淳 順天堂大学 医学部
渡辺文夫 神奈川県立衛生短期大学 技術科 (現・特定非営利活動法人 南陽台地域福祉センター理事)
磯部和正 筑波大学 臨床医学系
中井利昭 筑波大学 臨床医学系
高橋豊三 横浜市立大学 医学部
中島憲一郎 長崎大学 薬学部 (現・長崎大学大学院 薬学研究科)
長谷川明 東燃(株) 基礎研究所 (現・プロメガ(株))
舟橋真一 東燃(株) 基礎研究所 (現・(株)中外分子医学研究所)
菊地俊郎 東洋紡績(株) 生化学事業部
日方幹雄 日本合成ゴム(株) 筑波研究所 (現・JSR(株) 筑波研究所)
今井利夫 東邦大学 理学部
笠原 靖 富士レビオ(株) 中央研究所 (現・昭和大学 医学部)
刈田保樹 NOK EG&Gオプトエレクトロニクス(株) (現・ネオプト(株) ディバイス技術部)
軽部征夫 東京大学 先端科学技術センター
竹内正樹 (株)東芝 検体技術部
岡田 淳 関東逓信病院 臨床検査科 (現・NTT東日本関東病院 臨床検査科)
山本重夫 (株)ビーアールディー
構成および内容
第1章 総論
1 臨床検査薬の技術
1.1 最近の生化学的検査法の現状 片山善章
1.1.1 はじめに
1.1.2 酵素的測定法の特徴
1.1.3 日常検査に利用されている酵素的測定法
(1) 電解質および金属の酵素的測定法
(2) 酵素的測定法の問題点
1.1.4 電解質および金属の酵素的測定法
1.1.5 酵素的測定法の問題点
1.1.6 血清酵素の酵素的測定法
1.1.7 血清酵素のアイソザイムの測定
1.1.8 おわりに
1.2 免疫学的検査 星野 忠、河野均也
1.2.1 はじめに
1.2.2 非放射性イムノアッセイの分類
(1) 酵素イムノアッセイ(EIA)法
(2) 蛍光イムノアッセイ(FIA)法
(3) 発酵イムノアッセイ(LIA)法
1.2.3 おわりに
1.3 血液学的検査 緇荘和子、藤巻道男
1.3.1 はじめに
1.3.2 プロテインC測定の自動化
1.3.3 第ⅩⅢ因子、Dダイマーの自動化
1.3.4 TAT・PICの自動化
1.3.5 今後の動向
1.4 微生物学的検査 小栗豊子、猪狩 淳
1.4.1 はじめに
1.4.2 臨床微生物検査における迅速化の現状
1.4.3 病原微生物の迅速検査に用いられる技術
(1) 共同凝集反応(Co-agglutin-ation test)
(2) ラテックス凝集反応〔Latex agglutination test(LA)〕
(3) 蛍光抗体法〔Immunofluorescent antibody technique(IFA),Fluorescent antibody test(FA)〕
(4) 酵素抗体法〔Enzyme immunoassay(EIA),Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)〕
(5) 逆受身赤血球凝集反応〔Reversed passive hemagglutination test(RPHA)〕または
逆受身ラテックス凝集反応〔Reversed passive latexagglutination test(RPLA)〕
(6) 放射免疫測定法〔Radioimmunoassay(RIA)〕
(7) 免疫電子顕微鏡法〔Immune electron microscopy(IEM)〕
(8) DNAプローブ法
1.4.4 おわりに
2 臨床検査機器の技術 渡辺文夫
2.1 はじめに
2.2 生化学的検査用機器
2.2.1 種類と機構
2.2.2 フロー方式の技術
2.2.3 ディスクリート方式の技術
2.2.4 フィルム方式
2.2.5 共通要素技術
2.3 免疫学的検査用機器
2.3.1 種類
2.3.2 比濁法(TIA)、比朧法(NIA)
2.3.3 ラテックス免疫凝集法(LIA)
2.3.4 酵素標識免疫分析法(EIA)
2.4 血液学的検査用機器
2.4.1 自動血球計数器
2.4.2 自動白血球分類装置
2.4.3 セルソータ
2.5 細菌学的検査用機器
第2章 検査薬と検査機器
1 バイオ検査薬用の素材
1.1 モノクローナル抗体 磯部和正、中井利昭
1.1.1 はじめに
1.1.2 モノクローナル抗体作成法
(1) 一般的なモノクローナル抗体作成
(2) 遺伝子工学によるモノクローナル抗体作成
1.1.3 モノクローナル抗体の応用
1.1.4 おわりに
1.2 オリゴヌクレオチドの利用 高橋豊三
1.2.1 はじめに
1.2.2 合成オリゴヌクレオチド
1.2.3 オリゴヌクレオチド類似体
1.2.4 オリゴヌクレオチドの末端修飾
1.2.5 リボザイム ribozyme
1.2.6 三重らせん構造の形成
1.2.7 オリゴヌクレオチドの細胞内吸収とその行方
1.2.8 抗ウイルス効果
(1) HIVの抑制
1.2.9 おわりに
1.3 生物発光体/化学発光体の種類 中島憲一郎
1.3.1 はじめに
1.3.2 生物発光体
(1) ホタルの発光
(2) バクテリアの発光
(3) 発光タンパク質
(4) その他
1.3.3 化学発光体
(1) ルミノール系
(2) アクリジン系
(3) アダマンチルジオキセタン系
(4) シュウ酸エステル系
(5) その他
1.3.4 おわりに
1.4 発蛍光体 中島憲一郎
1.4.1 はじめに
1.4.2 発蛍光団
1.4.3 官能基に特異的な蛍光試薬
(1) チオール化合物
(2) アミノ化合物
(3) カルボニル化合物
(4) カルボン酸
(5) アルコール性化合物
1.4.4 酵素基質蛍光試薬
1.4.5 おわりに
1.5 組換え抗原 長谷川明、舟橋真一
1.5.1 はじめに
1.5.2 C型肝炎診断薬
1.5.3 第一世代のHCV診断薬
1.5.4 第二世代のHCV診断薬
1.5.5 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)診断薬
1.5.6 ヒト成人白血病診断薬
1.5.7 おわりに
1.6 新しい酵素とその利用 菊地俊郎
1.6.1 はじめに
1.6.2 臨床検査薬用酵素の設計
1.6.3 酵素特性を改良した酵素(Bucillus属耐熱性ウリカーゼ)
(1) 染色体DNAの調製
(2) 形質導入
(3) ウサギのウリカーゼ抗体の調製
(4) プラークハイブリダイゼーションによるウリカーゼ遺伝子の単離
(5) ウリカーゼ遺伝子の解析
(6) 発現プラスミッドの構築
(7) 大腸菌でのウリカーゼの生産
1.6.4 新しい尿素の測定系(酵母ウレアアミドリアーゼ)
1.6.5 酵素法による電解質の測定(グリセロールキナーゼ)
1.6.6 高感度発光検出系酵素(発光細菌ルシフェラーゼ、フラビン還元酵素)
1.6.7 遺伝子診断用酵素(耐熱性DNAポリメラーゼ)
1.6.8 おわりに
1.7 ラテックス
1.7.1 はじめに 日方幹雄
1.7.2 概論
1.7.3 ラテックスの種類と感作方法
(1) 物理吸着用ラテックス
(2) 化学結合用ラテックス
(3) 着色ラテックス
(4) 血球凝集反応用ラテックス
(5) 磁性ラテックス
1.7.4 用途
(1) スライドテスト法
(2) 光学測定法
(3) マイクロタイター法
(4) 微粒子EIA
(5) フィルター分離法
(6) 免疫クロマト法
(7) DNA診断
(8) その他
1.7.5 検査薬の作製
(1) 感作
(2) 粒径と感度
(3) 性能評価
(4) 分散液
1.7.6 おわりに
2 測定系の最近の進歩
2.1 EIA法 今井利夫
2.1.1 はじめに
2.1.2 測定法の分類
2.1.3 測定法
(1) 抗原の測定
(2) 抗体の測定
2.2 CLIA 中井利昭、磯部和正
2.2.1 はじめに
2.2.2 化学発光とは
2.2.3 化学発光イムノアッセイの概要
(1) CLIA
(2) CLEIA
(3) 化学発光イムノアッセイの臨床への応用例
2.2.4 おわりに
2.3 DNAプローブ法 笠原 靖
2.3.1 はじめに
2.3.2 測定原理
2.3.3 ハイブリダイゼーションの反応機構
2.3.4 プローブの調製
2.3.5 spotハイブリダイゼーションの測定法法
2.3.6 サザンブロッド(Southern blot)ハイブリダイゼーション
2.3.7 in situハイブリダイゼーション
2.3.8 ダーゲットDNAの増幅法
(1) PCR(polymerase chain reaction)
(2) LCR(ligase chain reaction)
(3) 3SR(self-sustained sequence replication)
(4) PCR/OLA ELISA測定法
2.3.9 おわりに
3 検出系と機器
3.1 レーザを利用する検出機器 刈田保樹、軽部征夫
3.1.1 はじめに
3.1.2 光音響分析法
3.1.3 SPRセンサ(Surface Prasmon Sensor)
3.1.4 レーザネフェロメトリー(Laser Nephelometry)
3.1.5 光CT(Optical Computed Tomography)
3.2 DNA関連機器-in situハイブリダイゼーション法および免疫組織化学染色法のための自動装置 高橋豊三
序文
3.2.1 はじめに
3.2.2 材料と方法
(1) 化学試薬
(2) 細胞と組織
(3) パラフィン切片
(4) 自動装置とその操作
3.2.3 非放射性標識DNAプローブ
3.2.4 in situハイブリダイゼーションと免疫組織化学染色
3.2.5 結果
(1) 自動装置
(2) この自動装置を用いた応用例
3.2.6 おわりに
3.3 生化学自動分析装置 竹内正樹
3.3.1 生化学自動分析装置の歴史
3.3.2 生化学自動分析装置の方式
(1) Continuous Flow方式(連続流れ方式)
(2) Discrete方式(分離独立分析方式)
(3) 遠心方式
(4) 試薬パック方式
(5) ドライケミストリー方式
3.3.3 自動分析装置に使用されている分析技術
(1) 試薬アプリケーションの条件
(2) 測定の演算処理
3.3.4 おわりに
第3章 資料編
主要病原性微生物と検査薬 岡田 淳
内容説明
本書は1992年4月に臨床検査薬に利用できる技術を解説するとともに当時のニーズも抽出しようとする目的で発行されたもの。普及版では技術の製品解説を中心にすることとし、現在では意味を失っている臨床検査アンケート調査および体外診断用医薬品の認可手順の記事を削除した。
目次
第1章 総論(臨床検査薬の技術;臨床検査機器の技術)
第2章 検査薬と検査機器(バイオ検査薬用の素材;測定系の最近の進歩;検出系と機器)
第3章 資料編
著者等紹介
山本重夫[ヤマモトシゲオ]
株式会社ビーアールディー
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。