出版社内容情報
刊行のねらい
我が国の電池産業はこれまで絶えず世界をリードしてきた。ニカド電池の高性能化、乾電池やアルカリ乾電池の非水銀化、鉛蓄電池の高性能化などでも我が国電池産業界の功績は大きい。また、最近脚光を浴びているニッケル/金属水素化物電池、リチウムイオン電池などのハイテク二次電池の開発でも我が国が一歩抜きんでているのが現状である。
最近のハイテク二次電池の研究・開発の経過を見ると、材料開発の占める比重が極めて大きくなっている。本書はハイテク電池とその材料の研究開発に第一線で直接携わる方々に執筆を依頼した。
執筆者一覧(執筆順)
(所属は『新規二次電池材料の最新技術』発行時(1997年3月)のものです。)
小久見善八 京都大学 大学院 工学研究科 物質エネルギー化学専攻 教授
菅野 了次 神戸大学 理学部 助教授
脇原 將孝 東京工業大学 工学部 化学工学科 教授
逢坂 哲彌 早稲田大学 理工学部 応用化学科 教授
伊東 秀俊 早稲田大学 大学院 理工学研究科
稲葉 稔 京都大学 大学院 工学研究科 物質エネルギー化学専攻
金村 聖志 京都大学 大学院 工学研究科 物質エネルギー化学専攻
豊口 吉徳 松下電器産業(株)中央研究所 チームリーダー
丹治 博司 旭化成工業(株)守山機能膜工場 工場長
森田 昌行 山口大学 工学部 応用化学工学科 教授
石川 正司 山口大学 工学部 応用化学工学科
井土 秀一 (株)ユアサコーポレーション 中央研究所 主幹
近藤 繁雄 松下電池工業(株)技術研究所 主幹技師
橋本 嗣夫 橋本化成(株)調査室 室長
境 哲男 大阪工業技術研究所 主任研究員
西尾 晃治 三洋電機(株)研究開発本部
ニューマテリアル研究所 電子化学研究部 部長
野上 光造 三洋電機(株)研究開発本部 ニューマテリアル研究所 電子化学研究部 主管研究員
坪田 正温 日本電池(株)電池開発本部 本部長
西野 敦 松下電器産業(株)研究本部 顧問
山木 準一 NTT入出力システム研究所 エネルギー研究部 研究グループリーダー
内容および構成
二次電池技術の現状と将来 小久見善八
1.はじめに
2.電池の構成と特性
3.高性能二次電池とは
4.電池の構成要素
4.1 電極材料
4.2 イオン伝導体
4.3 セパレーター
【第Ⅰ編 リチウム二次電池】
第1章 正極材料 菅野了次
1.コバルト系、ニッケル
1.1 はじめに
1.2 コバルト、ニッケル系正極材料の歴史
1.3 酸化物正極材料の種類と構造
1.4 酸化物系正極材料、LiCoO2、LiNiO2
1.5 合成と組成・構造
1.6 充放電機構
1.7 充放電特性劣化機構
1.8 熱安定性
1.9 固溶系
1.10 将来への展望
2.マンガン系スピネルおよびバナジウム酸化物正極 脇原將孝
2.1 はじめに
2.2 リチウムマンガンスピネルの構造
2.3 LiMn2O4の合成
2.4 Li Mn2O4の充放電特性
2.5 LiMyMn2-yO4(M=Cr,Co,Ni)の充放電特性
2.6 LiMyMn2-yO4中でのLi+の拡散係数の算出
2.7 LiMyMn2-yO4のヤーン・テーラー歪み
2.8 酸化バナジウムV2O5
2.9 アモルファスV2O5、V2MoO8
2.10 おわりに
3.有機正極 逢坂哲彌、伊東秀俊
3.1 はじめに
3.2 電解重合導電性高分子
3.3 導電性高分子正極の特性向上
3.4 無機正極活物質の複合化
3.5 ジスルフィド化合物
第2章 負極材料
1.炭素材料 小久見善八、稲葉 稔
1.1 はじめに
1.2 炭素材料の構造
1.3 炭素の負極特性
1.4 溶媒の影響ならびに表面皮膜
1.5 表面処理による特性向上
1.6 炭素材料中のリチウムの拡散
1.7 おわりに
2.リチウム電池用リチウム金属負極 金村聖志
2.1 はじめに
2.2 リチウム金属上の表面皮膜
2.3 デンドライト生成抑制
2.4 まとめ
3.その他の負極材料 豊口吉徳
3.1 はじめに
3.2 合金負極
3.3 化合物負極
第3章 セパレーター材料 丹治博司
1.はじめに
2.セパレーター材料の種類
3. セパレーターの基本機能と要求特性
4. 小型二次電池用セパレーター
4.1 ニカド電池用セパレーター
4.2 ニッケル水素電池用セパレーター
5. リチウムイオン電池用セパレーター
5.5.1 リチウムイオン二次電池の特徴とセパレーターの要求特性
5.2 リチウムイオン電池用セパレーターの製造技術
5.3 セパレーターと電池性能
6.今後の課題
第4章 電解質
1.電解液 森田昌行、石川正司
1.1 はじめに
1.2 有機溶媒
1.3 電解液の伝導度
1.4 電池特性におよぼす影響
1.5 課題と展望‐最近の報告から‐
2.ポリマー電解質 井土秀一
2.1 はじめに
2.2 イオン伝導のメカニズム
2.3 イオン伝導度の改良
2.4 熱的安定性
2.5 化学的・電気化学的安定性
2.6 ポリマー電池の特徴
2.7 おわりに
3.固体電解質と全固体リチウム二次電池 近藤繁雄
3.1 はじめに
3.2 リチウムイオン伝導性固体電解質
3.3 Li2S・SiS2系ガラスの電池への応用
4.リチウムイオン電池の支持電解質 橋本嗣夫
4.1 はじめに
4.2 支持電解質
4.3 支持電解質の製造方法
4.4 支持電解質の物性
【第Ⅱ編 ニッケル/金属水素化物電池】
第1章 ニッケル・水素化物電池 境 哲男
1.はじめに
2.アルカリ二次電池の発展プロセス
2.1 電気自動車とアルカリ二次電池
2.2 軍事技術と電池の高出力化
2.3 電池の密閉化と民生分野の拡大
2.4 携帯用機器の普及と電池の高容量化
2.5 資源・環境問題とニッケル・水素電池
2.6 地球環境危機とEVの実用化
3.ニッケル・水素電池の概要
3.1 電池の反応機構
3.2 電池密閉化の機構
3.3 過放電保護機能
3.4 電極の製造方法
3.5 水素電池の高容量化
3.6大型電池の開発
4.電池用水素吸蔵合金の研究開発
4.1 水素吸蔵合金の概要
4.2 水素吸蔵合金の電気化学的反応
4.3 希土類系AB5型合金
4.4 チタン・ジルコニウム系AB2型合金
4.5 チタン・ジルコニウム系AB型合金
4.6 バナジウム系固溶体型合金
4.7 マグネシウム系錯体型合金
5.二次電池と資源問題
6.最後に
第2章 正極と電解液 西尾晃治、野上光造
1.はじめに
2.電極反応
3.ニッケル極の種類と歴史
4.焼結式ニッケル極
5.非焼結式ニッケル極
6.電解液の影響
7.最近の開発動向
【第Ⅲ編 鉛蓄電池】 坪田正温
1.はじめに
2.密閉化技術
3.正極板の改良
4.負極板の改良
5.電池構成技術
6.電池管理材料
7.あとがき
【第Ⅳ編 電気二重層キャパシタ】 西野 敦
1.はじめに
2.EDLCの基本構成と動作原理
3.電気二重層キャパシタの構成と製法
3.1 電気二重層キャパシタの構成
3.2 分極性電極体
3.3 電気二重層キャパシタ(EDLC)の製造法
3.4 ACFCの製法条件と容量との関係
4.中型低抵抗EDLCの構成とその特徴
4.1 中型EDLCの構成
4.2 中型EDLCの主な特徴
5.電気二重層キャパシタの特性と応用
5.1 小型EDLCの特徴とその応用
5.2 中型EDLCの特徴とその応用
6.まとめ
【第Ⅴ編 二次電池の安全性】 山木準一
1.はじめに
2.電池の安全性の基礎
2.1 電池の自己発熱原因
2.2 事故のトリガー
3.リチウムメタル二次電池の安全性(安全性の改良研究)
3.1 負極リチウムの切断
3.2 負極板の端子の剥離
3.3 内部ショート
3.4 安全性試験
4.リチウムイオン二次電池の安全性(実際に使用するにあたって)
4.1 電池安全性評価の基本的考え方
4.2内部発熱
4.3 安全性試験
4.4 その他の注意点
5.まとめ
内容説明
ハイテク電池は幅の広い材料と生産技術を総合して製造される製品である。本書は、1997年に刊行された『新規二次電池材料の最新技術』の普及版である。
目次
二次電池技術の現状と将来
第1編 リチウム二次電池
第2編 ニッケル/金属水素化物電池
第3編 鉛蓄電池
第4編 電気二重層キャパシタ
第5編 二次電池の安全性
-

- 電子書籍
- その結婚、私がします【タテヨミ】第80…
-
![裏アカ女子だけど隣にいて良いですか?~脱ぎますからイイね下さい~[ばら売り] 31歳、銀座OL 山本 さゆ編 第9・10話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1109943.jpg)
- 電子書籍
- 裏アカ女子だけど隣にいて良いですか?~…
-
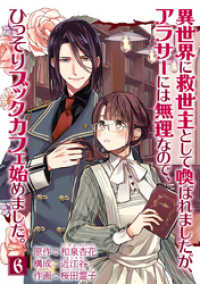
- 電子書籍
- 異世界に救世主として喚ばれましたが、ア…
-
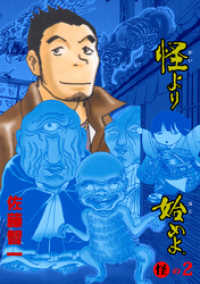
- 電子書籍
- 怪より始めよ。 2 マンガの金字塔
-

- 電子書籍
- 海の天辺 3 マーガレットコミックスD…



