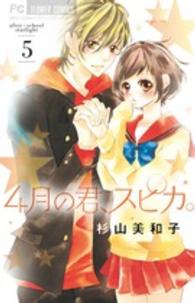内容説明
文学に描かれた“食”の記号が読者に受容されるメカニズム、ビール・コーヒー・ショコラ・などハイカラ食品の受容、料理屋と料理学校の文化的位置など、近代日本の“食”の言説と文化を写真資料とともに辿りつつ、“食”のトータルな文化記号的な意味を考察する。
目次
第1章 味と表現の類比(グルメの論理と小説の論理―岡本かの子「食魔」・矢田津世子「茶粥の記」;『食通放談』とグルメの言説―矢田津世子「茶粥の記」の出典について ほか)
第2章 グルメの時代相(明治の食道楽―村井弦斎「食道楽」・幸田露伴「珍饌会」;大正の美食―谷崎潤一郎「美食倶楽部」 ほか)
第3章 飲み物の象徴性(ビールの魅力―森鴎外の西洋;ショコラ・コーヒー・紅茶―永井荷風が好んだ飲物)
第4章 固有名と一般読者への通路(料理屋の名という固有名詞;料理学校の歴史とその周囲)
附録
著者等紹介
真銅正宏[シンドウマサヒロ]
1962年、大阪府生まれ。神戸大学大学院文化学研究科博士課程単位取得退学。同志社大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
1
第4章 固有名詞と一般読者への通路 ▲「料理屋の名という固有名詞」相撲のように番付表などがあった。ランドマークとして料理屋の名前が用いられる▲「料理学校の歴史とその周囲」。かつて料理はもてなしの一環だったが、明治以降に家庭での料理が体系化されてゆく。2016/04/24
つれづれ
1
恩師の著書を、遅ればせながら読了。不思議なもので、今やわたしは「ごちそうの古本屋」をやっている。恩師から学んだのは、食への執念?…多分そうだ。文学作品における味覚表現、文学作品に描かれる食の時代相、飲み物の象徴性、料理学校の歴史など、興味深いテーマで論じられる。しかしわたしにはやはり「文学研究」なるものが何なのかわからず、興味深く面白い「情報」としか読むことが出来なかった。2009/03/24