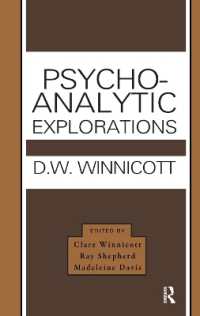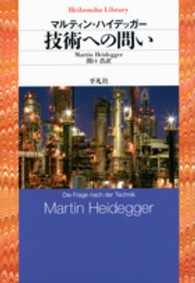内容説明
「プラトンの共同食事」から「子ども食堂」まで。子どもたちの生きる力。「給食・食育」はその根底をなす営みである―。視察旅行記とともに、現代における世界の学校給食の実態とその歴史を紹介する。
目次
第1章 福祉から「教育としての給食」への歩み―法制の歴史を軸に
第2章 子どもにみる「食と性格・人格形成」の相関関係―食・給食は、学びと人間形成の土台
第3章 人類史のなかの食と食思想
第4章 イギリスにおける給食運動と法制の展開
第5章 欧米諸国と日本の学校給食の歩み
第6章 フランスとイギリスへの学校給食視察の旅
著者等紹介
新村洋史[シンムラヒロシ]
1943年静岡県清水市生まれ。1980年東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(教育行政学)。2015年3月まで、至学館大学(旧、中京女子大学)、名古屋芸術大学に教員として勤務した。名古屋芸術大学名誉教授。大学教育学会理事・常任理事(2000~2009年)、東海高等教育研究所所長(1990~2009年)、教育科学研究会常任委員(1976~2020年)、東京民研・学校給食部会共同研究者(1992~2021年)など歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
4
協同と供食の生活→共感しあう能力進化 エリザベス救貧法→300年→学校給食法令 福祉→教育としての給食: 1951年・国際公教育会議 1954年・学校給食法 食育基本法・学校給食法 子どもの食と性格・人格形成の相関関係: 朝食の内容・質と心身の健康度 供食文化の衰退≒個食の影響 人類史のなかの食と食思想: 先人の食思想 英国・給食運動と法制の展開: 1906年ー教育・給食法 欧米諸国と日本の学校給食の歩み: フランスと英国への学校給食視察の旅: 2000年代の英国の給食・食教育の混迷 給食・食育の原点2024/12/08
asajee
2
食育の重要性と、日本の学校給食の素晴らしさを再確認2025/02/01
Go Extreme
1
起源:人類の「共食」は協同 共感 人格形成の基盤 イギリス:個人主義で公的導入遅延 産業革命下の貧困で慈善活動開始 1906年法制定(福祉→教育)も財源不足等課題多 現代は新自由主義影響 フランス:栄養重視 行政システム整備 応能原則 教育の一環 食育専門職 他欧米諸国:独(朝食) ノルウェー(市直営) スウェーデン(校内調理)等 米国は遅れて開始 日本:慈善事業(山形県鶴岡市)から始まり 戦時下の国策利用を経て 戦後全児童へ拡大 現代的意義:地域に根差す給食 食育の重要性 国際条約による子どもの権利保障2025/04/18
Masa199802
1
ヨーロッパでは給食は元々地域のボランティアで賄われていたが、国民を屈強にし、徴兵時の合格率を上げる(イギリスでは応募してきた5人に2人しか健康診査を合格しないほど栄養失調者が多かった)為に国が介入。 その後戦後は生徒の登校促進や貧困撲滅といった福祉の面から行われていたが最近では福祉→教育の面が大きくなっており、食育や人間形成の場といった認知が進んでいる。 2025/01/11
やす
0
案外面白かった。2025/12/20