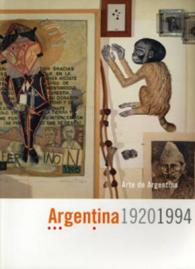内容説明
アーツカウンシルの最大の特徴は「アームズ・レングスの原則」によって運営されることである。本書では、実際の組織を対象とした実証的な分析を通じ“アーム”が外部要因(政治的な状況等)によって可変的なものであることを明らかにしつつ、この「原則」をどのように実現するべきか、また日本のアーツカウンシルが、どのように成立、発展しうるかを考察する。
目次
第1章 アーツカウンシルとは何か
第2章 英国:アーツカウンシル・イングランド
第3章 英国:クリエイティブ・スコットランド
第4章 日本:アーツカウンシル的組織「自治体文化財団」
第5章 日本:びわ湖ホール
第6章 アームズ・レングスの原則
第7章 日本版アーツカウンシルの確立へ向けて
著者等紹介
太下義之[オオシタヨシユキ]
三菱UFJリサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長。独立行政法人国立美術館理事。1962年東京生まれ。専門は文化政策。博士(芸術学)。公益社団法人日展理事、公益社団法人企業メセナ協議会監事、公益財団法人静岡県舞台芸術センター評議員。文化経済学会“日本”監事、文化政策学会理事、政策分析ネットワーク共同副代表。観光庁「世界に誇れる広域観光周遊ルート検討委員会」委員など役職多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
msykst
13
アームズレングスなる原則があると。本書の文脈においてこれは、助成団体たるアーツカウンシルが政府と一定の距離を保つ事を指すと。でもまぁ普通に「え、アーツカウンシルって公的機関っぽいけどそんなんできるん?」ってなるけど、まぁ案の定絵に描いた餅で、今まで一度も実現された事はなかったいうのを海外の事例の分析を通じて示す。むしろ文化政策の予算増額や総合政策化等々、一見すると望ましい動きがある度にアームズレングスの理念は阻害されていく(政策進化のジレンマ)。この辺は昨年末に訳出された『文化資本』にも詳述されている。 2018/09/17
yyhhyy
3
口は出さないが金は出す行政の文化事業の歴史や日本の箱物文化行政の背景など記録がまとめられている。2018/07/08
ノーマン・ノーバディ
1
特に面白いのは「アームズ・レングス」はケインズが言ったことではないと喝破する2章とびわ湖ホールの事例を分析した5章、スコットランドに興味があれば3章もか。アーツカウンシルのアームズレングスを大学自治や報道機関の独立と比較する6章は飛躍がある気がしたが2010年代の社会情勢がそうさせたのだろう。2020年東京五輪が日本の文化プログラム充実のチャンスと締めくくられていたが、結果的にはどうだったのだろう。2025/09/02
のの
1
オリンピック文化プログラムに向けてもあり、2010年代からアーツカウンシルが日本で注目されて来ているような気がするけれど、実はその根本的なところってちゃんとされているの?ということで、整理している本。文化財団についての研究が手薄ではないかという指摘、本家英国のアームズレングスの話は当然ながら、大学の自治や科学政策との関連まで書いているのは考える補助線になる。やっぱり蟻川先生のは読まないと…2018/07/23
hushigi1242
0
アームズレングスの法則はその言葉が誕生してから今日までいまだ実践されたことはない理想論だった、だと!2022/05/07
-
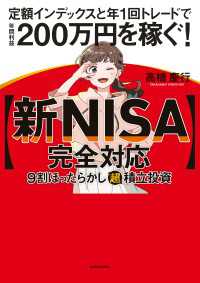
- 電子書籍
- 【新NISA完全対応】 9割ほったらか…
-
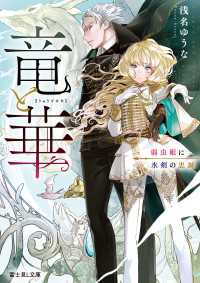
- 電子書籍
- 竜と華 弱虫姫に氷剣の忠誠 富士見L文庫