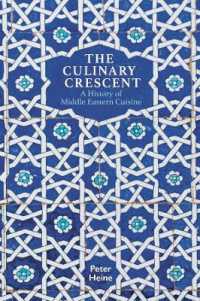出版社内容情報
障害者芸術のイメージを変え鑑賞できる場をつくる試みと、作品の正当な評価をめざして国内外で活動する先駆的なグループの活動を紹介し、全ての人が暮らしやすい新しい社会システムの構築への展望を描く
【本書で紹介する主な団体、事業と取り組み】
「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA」滋賀県社会福祉事業団による障害者と健常者、福祉とアート、アートと地域社会など、様々なボーダー(境界)を越えてゆく事をコンセプトにヨーロッパの美術館との連携も積極的に展開する試み。
「たんぽぽの家」奈良発、障害者の自己主張の場づくり。詩や舞台などのコンサート活動や絵画や書などの芸術表現と、「エイブルアート・カンパニー」による積極的な企業コラボレーションでの障害者観の転換を図る。
「アトリエ インカーブ」知的障害者のためのアートスタジオ。芸術作品の正当な評価を求めニューヨークへなどのアート市場へ積極的に進出。アーティスト(障害者)の働き方の多様性と生活基盤、プライドの構築をミッションに掲げ事業展開を続ける。
「アートを活かした障がい者の就労支援事業」大阪府の取り組み。障害の有無に関係なく希望者が自由に作品を出品でき、来場者が自由に鑑賞、購入ができるなどの機会の平等を保障し持続可能なシステムの構築に向けて官民の協働を推進する。
【著者紹介】
大阪市立大学都市研究プラザ特任講師。博士(創造都市)。NPO法人都市文化創造機構の事務局次長も務め、“創造都市”をめざす自治体やNPO関係者らのプラットホーム構築のための活動を行う。大阪創造都市市民会議世話人、社会福祉法人大阪ボランティア協会 ボランティア・NPO推進センター運営委員。
目次
第1章 芸術と福祉well‐beingを架橋する
第2章 芸術表現と福祉
第3章 アール・ブリュットとしての評価と作品収蔵―滋賀県社会福祉事業団の実践から
第4章 共感による人間関係の再構築―たんぽぽの家の実践から
第5章 経済的自立の可能性―アトリエインカーブの実践から
第6章 持続的に支えるシステムの必要性―大阪府「アートを活かした障がい者の就労支援事業」から
第7章 選択肢拡大とQOL向上を保障する社会へ
著者等紹介
川井田祥子[カワイダサチコ]
大阪市立大学都市研究プラザ特任講師。大阪市立大学大学院創造都市研究科博士(後期)課程修了、博士(創造都市)。NPO法人都市文化創造機構の事務局次長も務め、“創造都市”をめざす自治体やNPO関係者らのプラットフォーム構築のための活動を行う。大阪創造都市市民会議世話人、社会福祉法人大阪ボランティア協会ボランティア・NPO推進センター運営委員、文化経済学会“日本”理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
sabato
十日家sakana