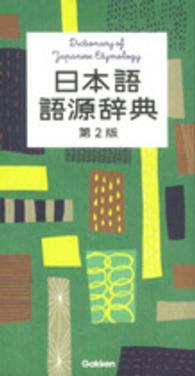内容説明
「再帰性」の概念を基軸に、いまの時代の本質を究明。われわれが身を置いているのは、モダニティの終わりではなく、モダニティのさらなる徹底化の過程である。
目次
1 政治の再創造―再帰的近代化理論に向けて
2 ポスト伝統社会に生きること
3 再帰性とその分身―構造、美的原理、共同体
4 応答と批判
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
43
90年代に書かれた3人の社会学者の論文と応答の4章建てで、翻訳にしては文章が平易だとはいえ、背景を知らず、いきなり本書を読むのはややハードルが高いと感じられました。とはいえ、それぞれどういう仕事をされているのか調べて勉強になりました。共通しているのは、マルクス主義が退潮したことで社会に対する批判理論が無くなって、硬直化した後期近代を構想していることです。①ベックは、リスク社会化という面が前景化してきた社会において、新たな原理として再帰的という考え方を導入することで、従来の二項対立や真理の独占からの解放が政2021/12/31
白義
20
前期近代の進歩信仰が崩れ、不確実性が世界を覆ったように見える後期近代では、人々は再帰的に、つまり自分自身の生き方を考え解釈しながら選ばないといけない。そうした時代認識で書かれた論文が並んでいる。さて、近代を脱伝統化と捉える見方はよくあるが、そもそも「伝統」というものの多くが近代になってから創造されたものだということは有名だし、みんなが自分の生を個人で意味付けられる現在でも、原理主義や保守的な運動というのは盛んだ。この逆説に明確な説明を与えているギデンズの論文はさすがに読みごたえがある2015/01/06
たばかるB
19
一昔前に流行った再帰性概念である。今回はS・ラッシュを中心に読んだ。彼の論調は秩序問題を起点とした社会と個人の存続について論ずるあたりベックより先鋭的である。再帰性を3類型に認知的/美的/解釈学的に分類し、他二人に批判的態度をとりながら論を進めるのだがいかんせん分かりにくい。中盤あたり美的再帰性ー脱構築の連鎖は永遠と分類を続けるだけであって、共同体の意味論を再度位置付けられないなど、政策科学的な面がほろりとある。2021/10/08
たばかるB
13
スコットラッシュに再挑戦。再帰性の文脈より、ポストモダンの流れで捉えた方がわかりやすい。ポストモダンの持つ差異化→脱構築による批判の連続は伝統その他全ての価値を転覆させる。伝統なき社会集団への再帰性を考える上で、ギデンズは利益集団が専門知システムを参照する形。ラッシュはそこを否定し、伝統的な共同体の持つ「意味」「文化」の維持に注目し、共同体内部で培われてきた解釈が共有され続け、反復され続けることを再帰的な共同体の条件として考える上で示す。/こうしてみるとラッシュの議論は他2人と比べ視野が広い。2022/04/27
きいち
9
問題意識を共有する三人の社会学者が寄せた論文と、それに対する批評で構成されている。仲良しと思われるのにお互い結構強く批判していて、こうして考えが磨き上げられていくのか、と楽しくなる。現実の課題と強く切り結んでいるベックも、再帰性の概念を一番深く練り上げているギデンズもいいけど、じゃあどうすればいいのか、となるとラッシュの観点が最も有効そうに見える(でも、ラッシュの文が一番わけわからん)。単純な近代と再帰的な近代が混在している中で対話を成立させるには、感情への配慮が必要、というふうに理解したのだけれど。2012/06/12
-
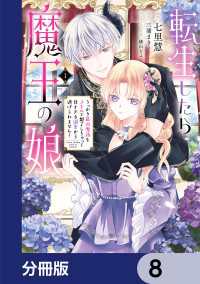
- 電子書籍
- 転生したら魔王の娘 うっかり最凶魔族を…
-
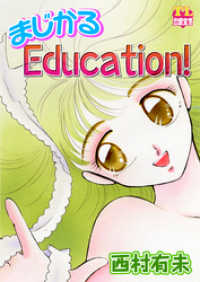
- 電子書籍
- まじかるEducation!