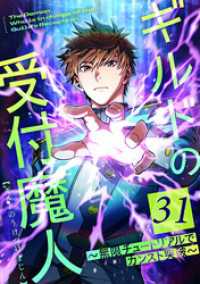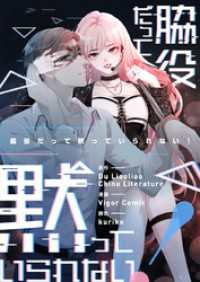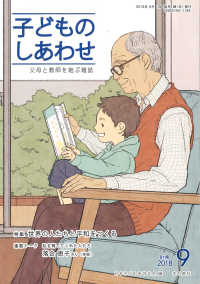内容説明
熊野山村の盛衰―。死者と生者が寄り添って生きる山の日常―。古道を踏むといつしか出会う異形の世界。巡礼路にある善根宿を営むおえん。那智の近くの山中の集落を廻る山の郵便脚夫岩次郎。栗の壺杓子屋晃太郎。修験者の最後の宿坊を守る五郎。力作中篇の4作。民俗伝奇小説集第4弾!
著者等紹介
宇江敏勝[ウエトシカツ]
1937年三重県尾鷲市の炭焼きの家に生まれる。1957年、和歌山県立熊野高校を卒業。紀伊半島の山中で林業労働にたずさわるかたわら、文学を学ぶ。現在、作家・林業・熊野古道語り部。文芸同人誌『VIKING』同人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件