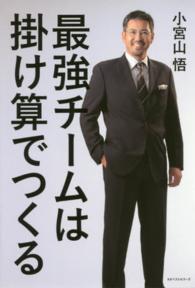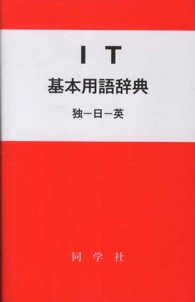目次
またひとつ舟が出ていく―二〇〇一年六月二十三日~十二月二十六日
貝のための子守唄―二〇〇二年一月二十六日~十二月二十五日
血まみれの童話―二〇〇三年一月一日~十二月二十五日
痕跡―二〇〇四年一月二日~十二月二十六日
谷に響く笛―二〇〇五年一月一日~十二月二十四日
骸骨の瞳、骸骨の口―二〇〇六年一月五日~十月八日
軽くて小さいが麗しいもの―二〇〇七年一月三日~五月七日
あきらめないでください―二〇〇九年五月~二〇一二年六月
著者等紹介
山崎佳代子[ヤマサキカヨコ]
1956年静岡生れ。ベオグラード在住。詩人。日本近現代詩を翻訳紹介(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
43
ヨーロッパの辺境ベオグラードへ、日本語をトランクに入れて移り住んだ詩人の山崎佳代子が2001年6月から10年間にわたって記した日々の記録。断章に継ぐ断章。これを読む前に、『そこから青い闇がささやき』を手にすることをお勧めする。2014/10/18
かもめ通信
28
『そこから青い闇がささやき』に続き、詩人であり翻訳家でもある山崎佳代子さんの本を手にした。本書は2001年から2012年までの歳月を日記形式で綴った随筆で、第66回読売文学賞(随筆・紀行賞)作品でもあるという。1990年代のユーゴスラビア紛争で、ボスニア・ヘルツェゴビナやコソボから逃れてきたセルビア人たちの支援活動にたずさわった経験から、難民の話題も多い。詩人が育む言葉は、たとえそれが“詩からはみ出た言葉”であってもやはり、選び抜かれた言葉であり、読む者の心に余韻を残す言葉でもあった。2017/02/13
踊る猫
14
気取った言い方をすれば英語などではない「マイナー」な言葉を扱い続ける著者の、それ故に小さな呟きに満ちた本である。その声はしかし、こちらを「聞き逃してはならない」と衿を正させる凛とした響き/強度を保っている。同時多発テロ、イラク戦争、フクシマ……マスメディアや権力者の大声に頼らず、やはりこれも「マイナー」な文学者の声を届けるその筆致は見事。ただ、後半駆け足になってしまうところが惜しいかな。フクシマに対する著者の言葉をもっと聞きたかったのに……死別が次々と書かれるのが印象に残る。一期一会の重要性を痛切に感じる2017/05/10
qoop
8
ユーゴスラヴィアからセルビアへ… 国家の激変をまたいで書き綴られた本書だが、そうした大きな変化は背景として触れられるのみで、著者の視線は日々の生活に据えられており、その地で暮らす人々の喜びと悲しみを写し出す。もちろん彼らの被った受難の深さ大きさがうかがい知れるのだが、それは民族/国家/民衆という大きな主語に基づくものではなくあくまでも個々人の受難として書かれている。あるいはそれだからか、大きな悲劇を前にして徒らに抒情に傾くきらいを感じる箇所もありそこは気になった(松島を訪れた際の「汚染」という一言など)。2019/12/03
relaxopenenjoy
6
雑誌への2001-2007年連載エッセイが元になってて、2009-2012年の記録を加筆。セルビアのベオグラードを拠点に、日本(実家の静岡や東京、震災後の仙台や松島など)、旧ユーゴ各国(コソボ、ボスニア、モンテネグロなど)など各所も舞台。セルビアでの生活、仕事(作詩、翻訳、大学教師等)、ご家族や恩師や親しい友人との別れ、 難民との交流や支援、お孫さんが産まれたり。本作内記述で気になって調べて初めて知ったが、著者のご主人(H)は山崎洋氏で、洋氏の父さんはユーゴ人(ゾルゲ諜報団の一人)。2025/06/07