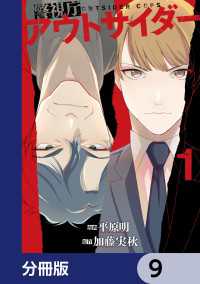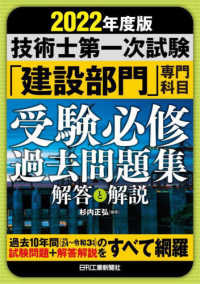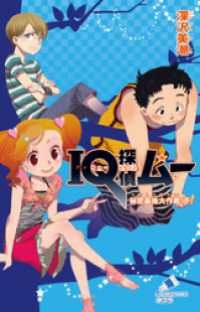内容説明
世界を瞠目させた“ブーム”の作家による力作から新世代の作家の野心作に至る、膨大な作品群を紹介。創造するラテンアメリカに併走しながら、さまざまな貌を見せるその姿を、広く長い射程で捉える。広大な文学世界を探索するための道しるべ。
目次
第1部 ラテンアメリカ文学の過去・現在・未来(メキシコ現代文学;アルゼンチン現代文学;マッコンドとクラック―新しいラテンアメリカ文学をめざして)
第2部 現代ラテンアメリカ文学併走(影の傑作;書かない理由―エルネスト・サバト『文字と血の間で』;理性が眠らなければ魔物が生まれる―フエンテス『コンスタンシア』 ほか)
第3部 ラテンアメリカ文学のさまざまな貌(既視のボマルツォ;ゲイの受容―メキシコとルイス・サパータ;スペイン語圏の文学賞)
著者等紹介
安藤哲行[アンドウテツユキ]
1948年岐阜県生まれ。神戸市外国語大学外国語学研究科修士課程修了。現在、摂南大学外国語学部教授。専攻はラテンアメリカ文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
9
スペイン語圏を勉強しようシリーズ。1999年から2003年までユリイカに連載したラテンアメリカ文学の時評エッセイを中に挟んで、20世紀以降の歴史や同性愛を取り巻く社会風潮などちょっと長めのエッセイでサンドイッチにしてあります。おっかなびっくりながら読んで見たい、面白そう、な本がたくさん紹介されていて、読みたい本がたくさん増えてしまいました。 2025/03/27
梟をめぐる読書
8
400頁まるごとラテンアメリカ。残念ながらわが国の翻訳状況は芳しくなく、従って紹介された膨大な作家や作品のほとんどを実際に読むことはできない(数ヶ国分の公用語をマスターでもしない限り)わけだが、しかしこれはこれ、軽妙洒脱な文学エッセイとしても十二分に楽しめる。ともあれ安藤哲行、木村榮一、鼓直といった訳者の名は日本の読者にとってマルケス、リョサ、ボルヘスといった固有名詞と同じくらい重要になっていると思うので、これからも是非、現地での「併走」を続けて行って欲しい。2011/12/18
oyatsudoki
0
じっくり読みました。いくつか気になる作品を見つけたのでいずれ手にとってみたいと思います。日本の出版社さんには若手作家や女性作家の作品の邦訳をもっと出して頂きたいですね~。特に女性作家の小説はどこの書店や図書館でも大体アジェンデくらいしか見ませんし。2013/06/29
まっきaka谷林
0
90年から03年にかけての作品紹介コラム73篇が中心だが、恐ろしいのはそのほとんどが未訳。今年訳されたものもちらほら。濃厚です。濃厚すぎて一年がかりで読んだ。スペイン語学びたくなる。2012/12/11
pio
0
気になるとこだけ読んだけど面白かった。いろんな本について触れられてて圧倒された。2021/11/13