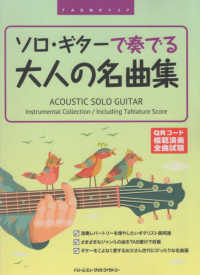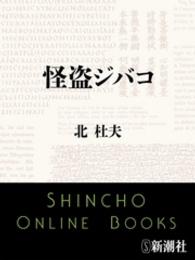内容説明
わたしたちは、「ごはん」を食べなければ、生きていくことができません。また、「ごはん」は、体の発育のためにも、欠かすことのできない大切なものです。そんな「ごはん」=「食べ物」にまつわる世界の状況や、食料生産をささえる農業の問題について、いっしょに考えていきましょう。
目次
第1章 食べ物とわたしたちの社会
第2章 食べ物をささえる産業
第3章 食料自給率から見えてくること
第4章 食べ物から世界と日本を見てみよう
第5章 農業の新しい動きに注目しよう
第6章 農業にふれる楽しさ
著者等紹介
生源寺眞一[ショウゲンジシンイチ]
1951年愛知県生まれ。東京大学農学部農業経済学科卒業。農林水産省農事試験場研究員、北海道農業試験場研究員を経て、1987年東京大学農学部助教授、1996年同教授。2011年名古屋大学農学部教授ののち、2017年から福島大学教授。現在は食農学類長。これまでに東京大学農学部長、日本農業経済学会会長、日本学術会議会員、食料・農業・農村政策審議会会長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
42
忘れた頃に話題になる食料自給率。漠然と考えていたことを再考する機会になった。廃棄される量の膨大なことを、どう考えるかということ。廃棄の全体量は、メディアに乗ることもあるが、思考がそこで止まっていた。廃棄の中身を知ることで、ものの見方も変わる。単に、需給バランスだけでではないということ。自分自身、家庭菜園でそれなりの量の野菜を作っていることもあり、作ることに眼が向く。2025/03/26
もとむ
24
日本における食品ロス、食料自給率、飽食…それらを知りたくて読んでみたけど、当たり前に日本だけの問題ではないですね。今の日本はかなりの食料を海外からの輸入に頼っているので、世界規模での食糧事情、農業事情を意識しないと。そのために自分に何が出来るのかを考えたい。少なくとも「食べ残しをしない」「スーパー等の買い物は古い方からとる」そのくらいはしないとなあ。本書は児童書だけど、専門的な解説も多く、大人でも難しい箇所も多々ある。でもその分入門編としてはすごく良いのでオススメです。2025/04/06
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
16
日本の食料自給率が下がっているのは、生産力が落ちているのではなく、食べすぎてるだけ、という目から鱗の現実が!その中には廃棄されてるものも多いのだろうなあ。作り置きって一見合理的なように見えて、実は無駄も多いんじゃないかな。ラップとかジプロックとか多用してるし。2025/02/02
綿帽子
3
児童書。良くも悪くも教科書を読んでいるような気持ちになる本でした。食料自給率にはカロリー自給率と生産額自給率とがある。生産額自給率は国産の方が値段が高いその価値を素直に反映しているもの。ということが知れて勉強になった。お米ラブなのでこれからもおいしいお米を食べていきたいです。2020/09/14
Opus13
2
じつに緻密な食糧問題の見取り図。2025/04/30