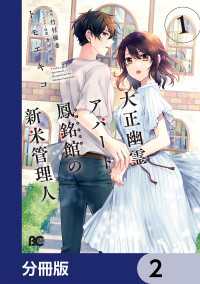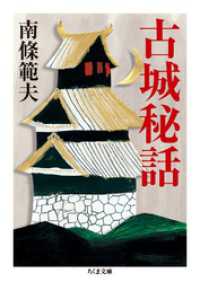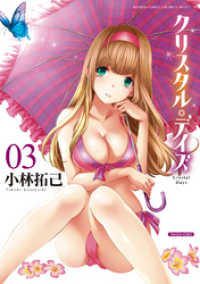- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
将棋はいつ、どのように日本にやって来たのでしょうか。なぞの多い将棋の歴史をたどると、将棋が日本で独自に進化したことがわかります。今より駒が多い将棋、名人誕生のひみつ、コンピュータとの対決など、将棋の楽しさがいっぱい!
目次
第1章 将棋の歴史を知ろう(将棋の起源はインドの「チャトランガ」;世界にある、将棋のなかま ほか)
第2章 頂点を目指せ!将棋界のしくみ(名人以外もある将棋のタイトル;棋士になるには―せまき「四段」への道 ほか)
第3章 将棋を楽しもう(駒の動きは?―ルールをおぼえよう;駒のならべ方にも順番がある ほか)
第4章 コンピュータと人間、どっちが強いのか?(対決!名人とコンピュータ;なぜ「将棋」を研究したのか ほか)
著者等紹介
高野秀行[タカノヒデユキ]
1972年横浜市生まれ。日本将棋連盟六段。1984年に中原誠十六世名人に入門し、1998年にプロ棋士となる。棋風は居飛車本格派。現在、明治大学、國學院大学で講座を持つほか、将棋教室で子どもたちに指導をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
77
著者の高野秀行さんは、現役の棋士。将棋の普及も棋士の役割。将棋に関する多くの著作があります。藤井2冠で人気の将棋、その成り立ちや歴史をわかりやすく解説している。将棋の起源は、インドのチャトランガ。7世紀にペルシャに伝わりシャトランジというゲームになり、チェスの原型になったらしいです。日本の将棋は、大陸伝来説と東南アジア説があり、結論は出てません。ただ将棋だけが、取った駒を使えるため、引き分けが極端に少ないそうです。日本最古の駒は奈良時代で、名人は徳川家康が俸禄を与えてからなど将棋好きに興味が湧く話題が多数2020/09/08
☆よいこ
49
将棋の歴史や楽しみ方がわかる。字が大きくふりがなあり、小学校中学年から読める。[第1章:将棋の歴史を知ろう]起源はインドのチャトランガ[第2章:頂点を目指せ!将棋界おしくみ]羽生さんと藤井さんどっちが強いの?疑問形にしといて”楽しみですね”とは卑怯だ[第3章:将棋を楽しもう]ルール、反則、礼儀作法[第4章:コンピュータと人間、どっちが強いのか?]大学の教授にインタビュー。だから、疑問形に答えなし。▽ルールについてはよくわかる。戦術についても少しだけある。2020/01/17
小紫
8
藤井棋聖の活躍もあって、最近にわかに興味が湧いてきた将棋について、まずは子供むけのに一冊挑戦してみました。「棋聖」だけでなくタイトルはいくつもある、ということや、世界に似たようなゲームは数あれど、相手方の駒を自分のものとして使えるルールがあるのは将棋だけ、ということ、その日本の将棋の歴史についても大きな文字で、しかもルビつきで知ることができて面白かったです。とっかかりとして良い一冊かと思われます。またもう少し詳しいのを読んでみたくなりました。《図書館》2020/08/20
izw
6
将棋がゲームとしてルールが整うまでの歴史、江戸時代の世襲制の名人を中心とした将棋の普及、明治時代の新聞将棋棋戦、現代の棋戦の仕組みなど、プロの将棋を楽しむための背景が丁寧に解説されている。駒の動かし方や、指し方についても多少の記載はあるが、これだけで楽しめるようにはならないだろうが、将棋への興味・関心を抱かせるきっかけにはいい本だと思う。2020/07/26
BEAN STARK
4
中将棋、大将棋めんどくさそう。羽生九段、加藤九段、藤井七段は三人とも中学生でプロ棋士になっている。2020/07/11