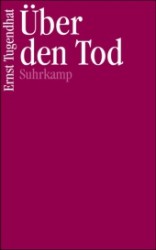内容説明
江戸時代の日本に、現在わたしたちが学んでいる算数や数学とはちょっと違う算術があったことを知っていますか?「和算」といいます。江戸時代の日本は、算術が大変なブームで、大人も子どもも楽しみながらそれを学んでいました。そんな「和算」の世界をのぞいてみましょう。
目次
第1章 算数・数学の歴史(古代エジプト・メソポタミアの数学;古代ギリシャ数学;古代インド数学;アラビア数学;古代中国数学;日本の数学)
第2章 和算のたんじょうと発展(和算のたんじょう;和算の発展;和算の特徴)
第3章 和算にチャレンジしてみよう(井於算額の問題;裁ち合わせ;盗人算(過不足算)
杉形算
油分け算
倍増し問題
橋普請算
円規の術)
第4章 算学の心得
著者等紹介
小寺裕[コテラヒロシ]
1948年、大阪府大阪市天王寺区生まれ。信州大学理学部数学科卒業。2006年に、二代目福田理軒を襲名。現在、日本数学史学会運営委員長。東大寺学園中学校・高等学校教諭を長く務め、授業で算題を扱うなど、数学教育における和算の可能性に注目している。全国の算額調査も鋭意継続中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
83
「算法少女」を読むための予習にと手に取りましたが、掲載されている問題が難しく、私にはたいへん手強いものでした。児童書ですので、問題は "大人の方と一緒に考えて"となっていますが、解法の説明が難しかったのです。数学現役の中学生、高校生なら簡単に理解できるのかもしれません。 ただ、江戸時代に西洋数学ではなく日本独自の和算が、武士や町人といった身分に関わらず趣味や芸の一つとして広く親しまれていたことが垣間見え、江戸時代の日本は世界にも類を見ない算数先進国だったことがうかがい知れました。2019/02/13
あーさん☆来年も!断捨離!約8000冊をメルカリでちびちび売り出し中!(`・ω・´)ゞ
57
ほとんど同じ事が書かれているが、こちらはどちらかと言うと小学6年生と大人用。著者が違いで学年違いが多い事がわかる。2019/03/26
むつこ
17
和算、どんなにやさしく説明してもらっても難しい。。。好きな人には楽しい算数(算法)だろうな。気持ちは伝わってきました。2016/07/01
あねさ~act3
2
算術の歴史的な話が面白かった。 子供の頃読んだ「算法少女」と言う本を思い出しました。 もう一度読みたいなぁ。 図書館にあるかな? 2018/08/08
-
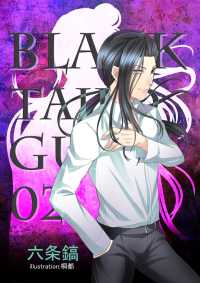
- 電子書籍
- BLACK-TAILED GULL 0…