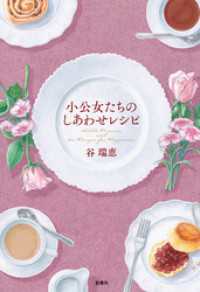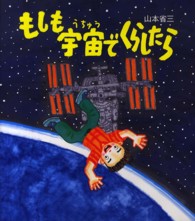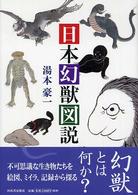目次
食べたのは、何?
恐竜みたい
ホネの探検
食べたことある?
ひらきのホネ
タイのタイ
塩焼きのホネ
あごのホネ
肉食・草食
目玉のホネ〔ほか〕
著者等紹介
盛口満[モリグチミツル]
1962年、千葉県生まれ。通称ゲッチョ。千葉大学理学部生物学科卒業後、1985年より自由の森学園中・高等学校理科教員として生物を担当。2000年、同校を退職し沖縄へ移住。NPO法人珊瑚舎スコーレの講師をへて、2007年より沖縄大学人文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
88
掲載されているホネの絵が、みんな恐竜の骨格に見えてきます。こんなところで進化論の勉強になるとは、タイトルに付いている "食べて始まる"からは想像もつきませんでした。日本の食卓にあがる骨付きの料理は数多くありません。干物の魚、サンマような小ぶりな魚、フライドチキン、くらいでしょうか。それらを食べてみても、綺麗に骨だけにすることは、ほとんどありません。こうして絵本にしてくれると、ホネの形が明瞭にわかります。そして、動物の骨格の巧みさに驚かされます。いただいた魚や鳥が命ある動物であることにあらためて気づきます。2019/02/04
keroppi
74
図書館で目に止まった絵本。食卓で出会う魚やフライドチキンの骨を、こんな風にじっくり見たことなかったなぁ。まるで恐竜の骨格見本のよう。こうやって見ていくと、私たちは、生き物をいただいて生きているということを実感する。最近、骨のある魚は食べられない人もいるらしいが、こうやって身近にあるものから、科学する力を得るのは、とてもいいことだと思う。2020/02/08
へくとぱすかる
70
絵本は幼児だけのものではない。類書の少ないジャンルをカバーする出版形態としての役割は、相当に大きいと思う。恐竜のホネの話から始まるが、メインは食卓で出会うホネ。魚が中心だがフライドチキンもトン足もある。アジの開き、サンマの塩焼きはもちろん、韓国など外国の市場で買った魚のひものなどから、生物の生態や進化をさぐれるとは驚きだ。たとえばチリモンなど、生物学習を身近な素材から始めるのは、案外奥深く、何より命をいただいているという大きな意味を知ることができるだろう。著者自身のペンによる精密な絵・図版に圧倒される。2020/12/22
kinkin
52
普段何気なく食べている魚や肉。そんな食べ物のホネを手書きイラストで紹介した本。食べ終わったらポイの魚のホネ、普段は見ることのない動物のホネ多数。ホネ好きの方にオススメ。2015/03/03
seacalf
50
普段何気なくむしゃこら食べている焼き魚やフライドチキンなど、身近な食卓から骨に親しんでみようというコンセプトが素敵。絵本をきっかけに調べて、ケンタのチキンの部位は五種類もあるのを初めて知った。恥ずかし。サンマの骨が緑がかってるのも気付かなかったなあ。ジュゴンは骨が重いなど豆知識もちらほら。カイギュウ類は波浪が激しい沿岸域で体を安定させるために骨が重い方が有利な一方で、クジラなどは体を軽くし速く泳ぐためにスポンジ状で軽い骨を持つほうが有利なんだそうだ。好奇心をくすぐること。たまには骨を観察するのも一興かと。2020/04/04