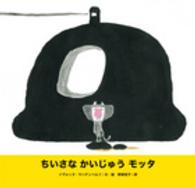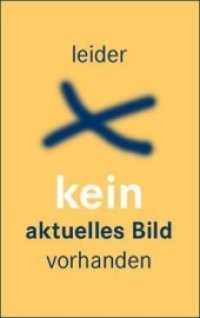目次
第1部 労働祭日(マサチューセッツ;ミズーリ)
第2部 感謝祭
第3部 新年
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
90
30年くらい前の本。アメリカにおける死刑制度の内側を探求した作品、前半は死刑執行に使用する器具や道具の成り立ちから、さまざまな失敗を重ねながら死刑に使う器具を改良する男の話。電気椅子やガス室は始めた頃はすぐに死ななかったことが多かったという。人の命を合法的に奪うというよりも、料理に使う食材の焼け具合をどうすればいいのかと考える死刑産業に携わる人の心怖かった。後半は死刑執行に関わる人、死刑囚やその他のインタビューがまとめられている。死刑制度の是非を語る本ではないので注意。図書館本2025/07/08
EnJoeToh
1
Alan Jeffrey Bannister, October, 1997.2013/10/15
苔
1
死刑によってもたらされる「人の死」は、見せしめの道具や社会的利便性に基づくものであってはならない。貧富の差が命の価値の差であってはならない。それがいかに「タテマエ」なのか分かってしまった。私は決して強烈な死刑廃止論者ではない。しかし、政治の道具として人の生命が簡単に天秤にかけられるというのは、許し難い事実だった。死刑という「システム」が生む矛盾を突きつけられた。2013/05/22
釈聴音
1
表紙にもなっている「電気椅子」―木材の一部は絞首台に使用されていたものを「リサイクル」(!)したもの―がいかに「人道的」であるかを力説する製造メーカー社長(ガス室工事、薬物注射機器も請け負っているらしい)が「ホロコースト否定論者」に利用されるなど、現実がブラックジョークの域に達した観がある。それに比べ、目前に「死」を見据えざるを得ない死刑囚たちの言葉はひとつひとつが重い。死刑の現実を見る上での必読書と言ってよい。2012/10/08