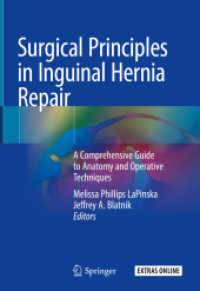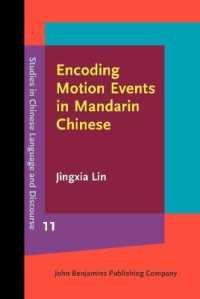出版社内容情報
21世紀は知性の時代、報道の時代、そして情報・諜報の時代、つまりインテリジェンスを掌握した個人、企業あるいは国家がこの世紀をリードすることになろう。
しかし20世紀を振りかえらないで、今世紀を展望することはできない。20世紀にはじめてインテリジェンス現象が顕在化し、時代を大きく動かしたからである。
20世紀メディア研究所が総力を結集して創刊する『Intelligence』は、内外の研究者、リサーチャーが寄稿した実証的、多角的なインテリジェンスの総合誌である。
【目次】
発刊の挨拶……………………………山本武利
特集:戦時期・占領期の一次資料による研究調査の現在
【特集1 プランゲ文庫】
占領期雑誌目次データベースの作成――プランゲ文庫の活用を目ざして……………山本武利
プランゲ文庫漫遊――長谷川如是閑の告白と再生にふれて……………………………堀真清
プランゲ文庫データベースと近代文学研究
――武者小路実篤、志賀直哉の新出資料を中心に………………………………宗像和重
占領期検閲雑誌の整理・保存事業について………………………………………………山田邦夫
【特集2 アメリカ国立公文書館】
アメリカ国立公文書館のOSS資料ガイド
――リサーチャーのための概説………………ローレンス・マクドナルド 山本武利訳
アーキビストから見た公文書館資料とリサーチャー
――ジョン・テイラー氏に聞く…………………………………聞き手・訳編 土屋礼子
ワシントン・リサーチガイド――DCで初めてリサーチをする方に……………………井川充雄
■■■■■■■■■■■■
大恐慌回復期の『日刊民衆』
――カナダ日本人労働者「キャンプミル労組」の日白提携・運動……………田村紀雄
幻の日本語新聞『ベルリン週報』を求めて
――サイバー・メヂィアによるクラシック・メディア探索記…………………加藤哲郎
『プレスアルト』(1937~43年)にみる戦時宣伝論………………………………………津金澤聡廣
1930年代「報道写真」のメディア構造とその表現――伊奈信男の報道写真論………原田健一
戦後日本の国民的メロドラマ……………………………………………ミツヨワダ・マルシアーノ
【資料紹介】オーストラリア陸軍の日本陸軍諜報機関分析
――オーストラリア陸軍参謀本部………………………………………………山本武利訳
■■■■■■■■■■■■
執筆者紹介
投稿規定、執筆要領
編集後記
英文目次
■■■■■■■■■■■■
『20世紀メディア研究所』について ( http://www8.ocn.ne.jp/‾m20th/ )
「研究所の設立について」―― 山本武利
私は1964年に大学院修士課程に入った。それが研究生活の最初とすれば、2002年の現在まで38年間も研究に携わってきた。大学院時代から40歳台前半までは、明治初期から昭和戦前期までの新聞史研究が中心であった。新聞史研究との関連で広告史とその関連メデイア、広告主、広告代理店の資料を同持並行的に収集していた。さらに40歳台後半になると、広告やそれを生み出す消費杜会研究に関心を高め、日本、中国、韓国の近代化と消費者意識の比較研究を行いたいとの意欲も高まった。内外の研究者との共同研究が多かったので、文部科学省科学研究費や各財団の研究助成金を獲得せねばならなかった。
50歳台になり、昭和戦後期にも研究対象に広げ、GHQ/SCAPのマイクロフイツシュ資料にとりつかれた。メリーランド大学のプランゲ文庫や国会図書館へよく行った。さらに50歳台後半からは第2次大戦期の日米の宣伝、謀略研究に足を突っ込み、主としてアメリカ国立公文書館のOSS,OWIの資料の収集、分析に力を入れた。私はプロパガンダ、諜報という政治コミュニケーション研究への強い関心を研究者になる以前からもっていたにもかかわらず、それに時間を費やしてこなかったから、これらの機密解除資料との出合いは嬉しかった。1996年から二年間滞在したアメリカ国立公文書館では、10万枚のコピーをとった。しかし資料の山に埋もれ、整理、解読できたのは、一部に過ぎない。
さらに2000(平成12)年度から私が代表者になった占領期雑誌記事情報データベース化プロジェクトが、文部科学省科学研究費(研究成呆公開促進費)を受けるようになった。この巨大な長期プロジェクトを完成し、広く研究者やリサーチャーに活用してもらうようにするためには、多くの方の協力が不可欠である。とくに各種雑誌の分類やデータベースヘのキーワード人力のためには、資料そのものの深い分析が必要であることを、この2年間の体験で痛感させられた。
いままで、私はその時々の白分内部から湧き上がる関心、興味にしたがって、研究テーマを設定し、資料を探し、その収集資料の範囲でなんらかの成果を発表してきた。結果として、19世紀から20世紀におけるメディアと情報、文化、政治、社会とを広く関連づける研究を行ってきた。だが個人の力ではとても及びつかないことに挑戦してきたドンキホーテであったかもしれない。そろそろ戦線を縮小し、終止符を打つべき時機との天の声が聞こえそうな歳になった。しかしこの約40年間の各研究の課題を今後も追究し、できれば集大成したいとの意欲もまだ残っている。最近では、コミュニケーションや杜会学、杜会心理学ばかりでなく、政治学、経済学、思想史、歴史学など隣接の領域でメディアやメディア史に関心をもつ人が増加している。それらの方々から新鮮な見方や方法を学べば、研究ももっと幅広くなろうとの期待もある。
そこで私は多くの方々と恒常的に共同研究を行う場を設定しようと思い立ち、既設の20世紀メディア研究所の中に「20世紀メディア研究会」を昨年7月に数人の仲間と設立した。そして私が行ってきたようなテーマに関心をもつ内外の研究者に研究会への参加を呼びかけた。幸い、友人、知人ばかりでなく一面識もなかった方々が多数賛同して、研究を発表し、また活発な議論を交わし、貴重な情報交換を行う場としてこの研究会を認めていただいている。
研究会では発表内容や討論結果を周知させるメディアとしてインターネットのアドレスをもっている。また今春、ホームページを立ち上げるよう鋭意準備を進めている。しかし研究発表や促進の場としての活字メディアの威力は依然として健在である。いや研究発表のメディアとしての権威は雑誌が最高である。したがって研究誌は研究会に参加する人にも、参加できない人にも研究会の内容を知り、確かめるメディアとなる。またそれは私やメンバー全員に研究会へのインセンティブをあたえることになろう。そこで私は20世紀メディア研究所を基盤とした研究誌の発刊を決意した。
雑誌のタイトルは『Intelligence』と決めた。誌名に違和感を抱く読者もいよう。英語のintelligenceに諜報や諜報機関の意味合いがあるからである。しかし諜報研究はコミュニケーション研究で欠落した領域である。私もそれに最近研究の重心を移している。諜報や謀略は研究分野として市民権を得なければならない。多くの英和辞典はもともとintelligenceという言葉に知性、情報、知識、報道、通信という意味を付し、それらの用例に諜報よりも多くのスペースを割いている。これらの語彙は私の旧来のテーマそのものである。
ともかく多角的、多彩なメディア分析をめざしている本誌に格好なネームが『Intelligence』である。
つまり20世紀のメデイアやその杜会的、政治的な多様な機能、役割を一語に包含する便利な言葉として、Intelligenceという言葉に着目し、それを本誌のタイトルとした。本誌は定期刊行物である。定期的に開催される20世紀メディア研究会と連動している。最低一年に一回刊行するが、研究会の成果があがれば、複数回出すこととなろう。『Intelligence』は研究会の発表者の論文を中心に、研究ノート、資料紹介などを掲載する。しかし広く一般の方にも投稿を呼びかけることにする。それに対応し、事務局内に編集委員会を設け、投稿の査読を行い、掲載の可否を決定する。また毎号原則として特集形式をとるが、その際、編集委員会が内外の研究者に執筆を依頼することもある。したがって本誌は研究会発表原稿、投稿原稿、依頼原稿で構成される。研究会は会員を固定することなく、誰でも参加可能で、会費なしで当面運営している。研究会の案内も無料である。しかし本誌はだれにも有料である。紀伊国屋書店を通じて発行、販売される。本誌が広く世に迎えられ、それとともにメディア研究ならびにメディア史の研究に少なりとも寄与することを祈らずにはいられない。