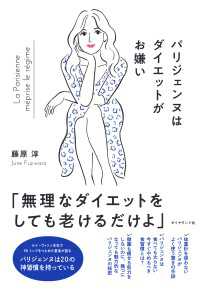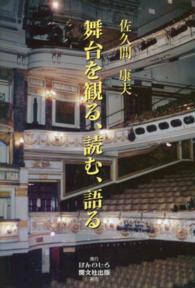出版社内容情報
原書『Punishment and Modern Society』(1990)
刑罰プロセスが社会・歴史的な文脈によってどのようにして現在の形をとるようになったのか、処罰が持つ社会的意味は何か。デュルケム、ルッシェとキルヒハイマー、パシュカーニスなど、処罰の歴史的基礎、社会で果たす役割、文化的意義を説明しようと試みてきた社会理論家や歴史家の研究を順に検討。著者は、刑罰が、犯罪統制の技術であるにとどまらず、権力、社会―経済構造、文化の感受性と相互作用し、その結果、複雑な社会制度になっているとの持論を展開。社会と歴史の理論への洞察が、現代社会の処罰、さらにはもっと広く一般の現代社会の特徴に影響を及ぼすこと、そして、それを統合することが、この複雑な社会制度を理解することにつながり、刑罰政策分野でもより現実的で適切なものへと発展し、政策決定者に寄与すると力説する。
第1章 処罰の社会学と今日の処罰
第2章 処罰と社会的連帯??エミール・デュルケムの著作
第3章 処罰と権威の構築??デュルケム的主題の再検討
第4章 処罰の政治経済??ルッシェとキルヒハイマー、およびマルクス主義的伝統
第5章 イデオロギーと階級統制としての処罰??マルクス主義的テーマの変種
第6章 処罰と権力技術??ミシェル・フーコーの著作
第7章 権力パースペクティヴを越えて??処罰に関するフーコーの批判
第8章 処罰の合理化??ウェーバーの命題と近代刑罰
第9章 処罰と文化??文化形態と刑罰実務
第10章 処罰と感受性??「文明化された」制裁の系譜学
第11章 文化的主体としての処罰??文化形成における刑罰の役割
第12章 社会制度としての処罰
デービッド・ガーランド[デービッド ガーランド]
デービッド・ガーランド(David Garland)
1955年生まれ。スコットランドダンディーの出身。エディンバラ大学法学部、シェフィールド大学犯罪学修士課程を修了後、エディンバラ大学社会-法研究で1984年博士号を取得。1979年エディンバラ大学のロースクール講師を皮切りにプリンストン大学、カリフォルニア大学バークレー校等で教鞭をとり、現在、ニューヨーク大学ロースクール及び社会学教授。
法社会学分野の第一人者で、雑誌「処罰と社会(Punishment and Society)」の創立編集者。アメリカ犯罪学会から、セリン・グリュック賞、サザランド賞を受けるなど受賞歴多数。現在、イギリス学士院、エディンバラ王立学院、アメリカ犯罪学会のフェロー。
本書に加え、『処罰と福祉』(1985)、『統制の文化:現代社会における犯罪と社会秩序』(2001)はガーランドの三部作と言われている。
向井 智哉[ムカイ トモヤ]
向井 智哉(むかい・ともや)
早稲田大学文学部、同大学院文学研究科修士課程修了。現在、同研究科博士課程在学中。
藤野 京子[フジノ キョウコ]
藤野京子(ふじの・きょうこ)
早稲田大学第一文学部、同大学院文学研究科修士課程修了。テキサス州立サム・ヒューストン大学刑事司法学部修士課程修了。東京少年鑑別所、矯正協会附属中央研究所、矯正局、法務総合研究所等を経て、現在、早稲田大学文学学術院教授。
主著に、『薬物はやめられる!?』(財団法人矯正協会、2007)、『困っている子を支援する6つのステップ』(明石書店、2010)等があり、訳書に、『犯罪理論』(F. P. ウイリアムズ?、M. D. マックシェン著、財団法人矯正協会、1997)、『エビデンスに基づく犯罪予防』(ローレンス・W・シャーマン、ディビッド・P・ファリントン、ブランドン・C・ウェルシュ、ドリス・レイトン・マッケンジー著、財団法人社会安全研究財団、2008)等がある。『近代犯罪心理学文献選』の編纂(クレス出版、2016)も手掛けている。