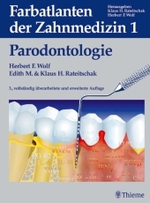内容説明
刑務所の中にビール工場!?罪を犯した人が社会貢献を通じて更生し自立する驚きのイタリア・モデルを紹介。
目次
序章 福祉施設化する日本の刑務所
第1章 イタリアの刑事司法
第2章 イタリアの精神保健サービス
第3章 イタリアの依存症対策
第4章 イタリアの社会協同組合
第5章 その他の民間の財団
終章 イタリアから見える日本の問題
著者等紹介
浜井浩一[ハマイコウイチ]
1960年生まれ。龍谷大学教授。専門は犯罪学。早稲田大学教育学部卒業後、1984年に法務省に採用され、少年鑑別所、少年院、刑務所、保護観察所のほか、矯正局、法務総合研究所、在イタリア国連犯罪司法研究所を歴任。臨床心理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akihiro Nishio
24
少し刑務所で働いている人間としては非常に興味深く読めた。イタリアの刑務所が障害者の累犯に対して処罰よりも福祉に重きを置くように変化していった経緯と、現在のシステムを見聞したもの。正直、現場の誰もが、収入を得る方法がなく万引きで何度も入所してくる障害者を持った人を処罰することに意味を感じていないので、非常に示唆に富む内容であった。現在のイタリアの仕組みを日本が真似るのはさすがに無理だと思うが、保護観察の仕組みの中で福祉と連携するのは不可能ではない。本書の中で道しるべも記されている。少しずつでも進んで欲しい。2017/06/06
春風
6
精神病院を解体したイタリアのバザーリア法は有名だけど、司法や依存症対策まで徹底して同じ思想に貫かれていたとは驚き。刑罰の目的は応報ではなく更正とと明確に規定した憲法をもとに、収容ではなく社会復帰を最初から意識した刑罰や精神医療が進められている。被害者感情に刑が左右されがちな日本とは思想そのものが違うので、なかなか道は険しいけれど参考になる。2013/06/06
向う岸
3
1978年に公布されたバザーリア法を元に、イタリアでは精神障碍者や受刑者を隔離するのではなく地域社会の保健サービスや官民の連携で自立支援を助ける。全てが順調ではないし、カソリックという背景があるとはいえ、犯罪を個人の問題とせず社会全体で困難を解決することが救済だとするのは成熟した市民感覚だ。受刑者がビールを製造したりヘロインやコカインの個人使用なら罪は問わず治療を優先させるというのはすごいな。更生とは謝罪や反省をすることではなく、自分が社会の役に立っていると認識させて普通に生活できる市民に戻ること。2013/05/28
ひろか
2
システムの問題であろうが、だからといってイタリアのように法律を変えたからといってこのような日本でこのような展開になるのだろうか。2013/05/26
gami
1
「誰も排除しない社会」は人類が達成すべき目標のひとつに思えるが、その中には当然、人や秩序を損ねた人も入る。罪を犯した人を隔離することは、私たちの身を守るためであり、人生をかけての反省を促すことでもあるので、直ちに無くすことはできない。しかしそれは、排除と表裏でもある。そもそも小さな子どもがルールを犯したときだって、私たちは一時的にその子を別の場所に「排除」する。人間として「排除」をまったくしない社会を目指すということは、「汝の敵を愛せよ」同等に困難なはずである。 本書は、私たちと排除という視点で取った。2021/10/14
-

- 電子書籍
- アンパンメンー明治起業家譚- 4巻 C…
-

- 電子書籍
- 最後の晩ごはん 旧友と焼きおにぎり 角…