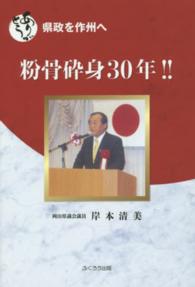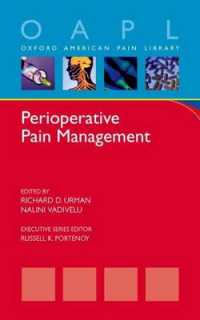出版社内容情報
「日の丸・君が代」の強制に象徴される管理強化により、学校現場はどのような状況になっているのか。自由な空気が奪われるなかで生徒たちを教育していくことはできるのか。
第一章 教育基本法「見直し」先取りする現場
第二章 つくられる「指導力不足」教員
第三章 エスカレートする「日の丸・君が代」の強制
第四章 監視される都立高校の教師たち
第五章 生徒にも強制を始めた東京都教委
第六章 「つくる会」教科書採択をめぐる圧力
第七章 分断され孤立化する現場
はじめに
教育基本法の改正をめぐって、国会で議論が繰り広げられています。最大の焦点となっているのは、「愛国心」と「教育への不当な支配」についての条文です。
現行の教育基本法には、「愛国心」についての記述はありません。「我が国と郷土を愛する態度を養う」といった文言を新しく盛り込むことの是非が、改正論議の大きなポイントになっています。
そしてもう一つ、とても重要なのが「教育行政」に関する条文です。現行の教育基本法は第十条で、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」と述べて、教育行政の役割を明確に限定しています。これに対して政府の改正案は、国と地方公共団体の教育への関与を強化する内容となっています。
しかし、実際に教育現場を取材すると、現場はすでに教育基本法改正を「先取り」したような状況になっているのを実感します。
「国旗・国歌法」(国旗及び国歌に関する法律、一九九九年)の成立を境に、学校には「日の丸・君が代」が一〇〇%導入されましたが、「日の丸・君が代」は戦前の「御真影」のような神聖不可侵な存在になろうとしています。全員が国旗に向かって起立し、国歌斉唱することを強制する。全員を一律に同じ方向に向けさせて、異なる意見や考えは許さず、上から言われたことに黙って従う。そんな学校や社会をつくろうというのでしょうか。不安を感じずにはいられません。
一方で、教育委員会や管理職に楯突く教員は、「指導力不足教員」や「不適格教員」として、徹底排除する動きもあります。校長の恣意的・意図的な判断で、教員が現場から排除されるとすれば、自由で自主的な教育活動などできなくなってしまうでしょう。
全国的にも突出しているのが、東京都教育委員会です。「日の丸・君が代」の扱いを細かく指示し、国歌斉唱の際に起立しない教員やピアノ伴奏を拒む教員を大量に懲戒処分している都教委は、職務命令違反を重ねると、戒告・減給・停職一カ月・停職三カ月と、処分をどんどん重くしていくのです(累積加重処分)。そこまでしている自治体は、ほかに聞いたことがありません。
国歌斉唱の際に生徒や保護者に「思想・良心の自由」についてアナウンスすることも、都教委は一切禁止しました。ホームルームで教員が説明するのもご法度です。都立高校では、生徒に憲法を教えてはいけないという不思議な論理がまかり通っています。
「教育公務員は全体の奉仕者だ。上司の命令に従うのが当然だ」という議論がありますが、違法・不正な命令であれば、拒むべき場合もあるのではないでしょうか。そもそもすべての公務員には、日本国憲法を尊重し擁護する義務があるはずですが、東京都では、憲法や教育基本法の理念や精神は完全に踏みにじられているようです。
教科書採択では、教育現場の意見が排除され、教育委員の権限が大きくクローズアップされました。行政から独立して教育のあり方をチェックするのが教育委員会ですが、「形骸化している」と批判され、一方でその政治的中立性が問題にもなっています。
教育現場は疲れきっています。職員会議で活発な議論が交わされることがなくなった、という話は前から耳にしていましたが、職員室での先生同士の会話も少なくなっているといいます。
子どもたちの問題について、先生が職員室でざっくばらんに話し合い、校長や教頭も一緒に考えるのが学校のあるべき姿だと思うのですが、現実の学校はそうではない。先生たちは多忙で、がちがちに管理され、分断され孤立化している。仲間であるはずの校長や教頭ら管理職は、文字どおり先生を「管理する側」になってしまって、教育行政の顔色ばかりうかがっているのです。
取材から、そんな教育現場の息がつまるような実態が浮かび上がってきました。