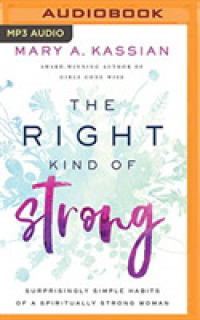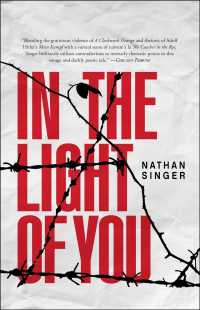出版社内容情報
第1部=メディアスクラムなど報道の問題を00~06年にかけて1つずつテーマを選び論じる。第2部=アジアプレス・野中章弘氏と対談。マスコミ不信を克服する方策を探る
まえがき
第1部 マスコミの過熱報道と特ダネ意識
◆日本初の脳死移植をめぐる報道の過熱ぶり
はじめに
報道の経過
◎ドナー発生、侵されるプライバシー
◎再度の脳死判定へ
◎法的脳死と判定
◎臓器摘出・搬送・移植手術
マスコミへの批判事例と検証
◎事例1 侵されたプライバシー
◎事例2 マスコミのマナーの悪さ
◎事例3 低質な表現
◎事例4 その他の現象
インターネット上のマスコミ批判
二例目以降も繰り返されたプライバシーの侵害
求められる報道姿勢とは
◆米大統領選、歴史的大誤報 ―― 出口調査の落とし穴
はじめに
出口調査機関一社に頼り切ったマスコミ各社
迷走する米メディア
誤報の新聞はオークションに
脚光浴びる出口調査
出口調査の弱点
権力に隙を突かれない慎重さを
◆「お受験殺人」にみる、思い込み報道の危険性
はじめに
事件のあらまし
パターン化した発想が「お受験」に
「お受験殺人」のイメージを決定的にした続報
落とし穴にはまった毎日新聞の勇み足
軌道修正を余儀なくされたメディア
マスコミへの批判相次ぐ
過去の教訓を今再び
◆集団的過熱取材とメディア規制の動き
「正義の味方」から傲慢な存在へ
メディア規制化への報道被害と自民党の対応
メディア規制に火を点けた自民党「五五年体制」の崩壊
「人権擁護法案」の問題点
「個人情報保護法案」(民間対象)の問題点
「青少年有害社会環境対策基本法案」の問題点
「集団的過熱取材」の主な事件例と過熱報道が起こる根拠
集団的過熱取材の自粛とメディアの対応
政治に左右されない自浄能力を
◆北朝鮮拉致被害者の報道合戦
はじめに
過熱した拉致被害者の帰国報道
「北朝鮮の情報操作に乗った」
二大紙とも似たような大見出し
メディアの宿命
「週刊金曜日」による単独会見
「週刊朝日」の無断掲載
慣れと思い込みからの脱却を
◆イラク戦争報道にみる遺体映像の扱い
はじめに
世界を駆けめぐった衝撃の遺体写真
◎アメリカ ―― 「ソマリアの悪夢」
◎ロシア ―― チェチェン紛争
◎日本 ―― 「三島事件」
ホワイトハウスの世論操作
米民間人虐殺映像
情動に訴えたイスラム武装勢力による人質映像
イラク人捕虜の虐待写真
戦争写真の歴史と遺体写真の扱い
思考停止からの脱却を
◆誤報がもたらした騒動二例
はじめに
「コーラン冒涜事件」の 誤報 はなぜ起きたのか
◎根底にあるものはマスコミの「思い込み」
◎されなかった「裏付け」取材
◎余波
「アンコールワットはタイのもの」発言にカンボジア人は怒った
◎根底に内在する感情
◎女優発言はどうして歪曲されたのか
デマ報道の怖さ ―― 確たる裏付け取材を
◆スタッフカメラマンに求められるジャーナリズム精神
宇宙船アポロ13号と米兵の死
アジアの身近なベトナム戦争 ――「日本人の目で戦争写真を」
単純思考の危うさ ―― 東京で作られるニュース写真のイメージ
アメリカの担保が求められるアジアの大ニュース
「カラ手形」の紙面獲得
スタッフカメラマンは何を考えたのか
求められるジャーナリスト精神
第2部 対談*「分断」は克服できるか
ーー過熱するマスコミへの警鐘として
[松本逸也×野中章弘(アジアプレス代表)]
過熱化した時代背景
平均化したニュース感覚
「質」か「部数」か
読者任せ
ニュースの価値づけが求められている
深化するマスメディアの官僚化
天皇報道の過熱ぶり
不可解な責任体制
立場を明確に
思考停止から脱却できるか
メディアリテラシーが必要
過熱報道は多様性を切り捨てる
国民の縮図がマスコミだけれど
まえがき
私が朝日新聞社に入社した一九六九(昭和四四)年という時代は、東京・有楽町界隈にはまだ戦後の焼け跡闇市的な怪しい雰囲気が残っていた。JR(当時は国鉄)山手線・有楽町駅のガード下には、小さな飲み屋や焼鳥屋、焼きトンを食わせる安酒の店が軒を連ね、赤提灯がその風情を一層、醸し出していた。新聞社はその一画にあった。数寄屋橋の角にまるで軍艦のように凛として立っていた本社ビルは、一九二七(昭和二)年建立の鉄筋の七階建て。二・二六事件(一九三六〔昭和一一〕年)では反乱軍に襲撃されるなど大戦争、敗戦、焦土の中の混乱、そして民主化と経済復興という幾多の歴史をも見つめてきた、まさに昭和の生き証人だった。
そのころ、新聞は多くの読者から尊敬にも似た信頼感によって支えられていた。「新聞は嘘をつかない」。その信頼感がグラグラと音を立てて崩れ始めたのは、今思えばバブル経済の時期と密接に関わっていたように思う。新聞社は、東京の他に、名古屋、大阪、西部(福岡)に本社を、そして、北海道に支社を構え、それぞれが新聞を印刷、発行している。入社した当時は、本支社が今よりもっと強い独自性をもった新聞を制作していた。それぞれの地域で、地域に密着したニュースを毎日、読者に届けていた。ところが、一九八〇(昭和五五)年、その半世紀の歴史を刻んだ東京本社が銀座から築地に移転した。この本社移転が大きな意味で紙面に後々、陰を落とすことになったと私は感じている。
八一年、私は東京本社から名古屋本社に異動した。この頃から、東京発のニュースの比重が他本社でも大きくなっていた。名古屋にいても、東京のニュースばかりが目につくようになった。それは全国に散らばる大型スーパーや洋服屋のチェーン店とよく似ていた。東京は、年々人口が増え高層ビルが林立し、朝夕のラッシュは日を追ってひどくなっていった。道路には車が数珠つなぎだし、仕事を終えての一杯飲み屋でもサラリーマン同士が袖すりあわせ、身を縮ませなければならなくなった。カラオケはサラリーマンの最高の発散法になり、アッという間に世の中に浸透した。東京は忙しくなり、毎年のように、いや毎月のように記者が採用され、地方のベテラン記者もどんどん東京に吸い上げられていった。地方は若い新人記者だけとなり、それだけ地方の力が弱まるのは当然のことだった。こうして情報や人流の異常なまでの東京一極集中化が、本来あるべき新聞社の姿を大きく変えていった。
そんなある年のこと、同僚が自作自演のニュースのねつ造というショッキングな事件を起こした。「サンゴ損傷事件」として知られた事件だが、この事件は、さまざまな意味で考えさせられることが多かった。なぜ彼はあんなことをしてしまったのか。多くの仲間の中で自分だけが特別の存在でありたいという功名心からくるものだったのか。もし、そうなら、その功名心、競争意識を煽ったのは一体だれなのか。この事件の底流には社会病理的な、構造的な問題が潜んでいるのではないか。折しも、日本経済はバブルが崩壊し今までの元気印が嘘のように意気消沈。しかし、バブル時代に植え付けられたマスコミ内部における功名心(特ダネ意識)は、このときすでに社会常識を逸脱するほどまでに膨張していたのである。
さて、本書は、私が新聞社を早期退職し目白大学でメディア関係の教鞭をとりはじめた二〇〇〇年春から同大の紀要に書き綴ったものに少々手を加えたものである。新聞社に勤務していたときには気づかなかったことも、新聞社から少し離れたところから見ると、同じ事柄でも随分と違って見えるものだ。それに新聞社を辞する頃から、マスコミと世間との間に意識の乖離が潮目のように生まれてきていることに薄々気づいていた。
メディアを講義するからには、当然、自身が歩んできたことも含め、これから進むべきマスコミのあり方に目を光らせるという役割が求められているように私は思った。それも単に批判するのではなく、世の中におけるマスコミの必要性を説きながら、しかし、おかしいものはおかしいという姿勢がもっとあってしかるべきといつも考えている。そんな理由から、毎年、その年に問題になったテーマをひとつ選んで紀要に「過熱するマスコミ報道」として連載してきた。二〇〇一年に関してだけ、学内誌『国語国文学』に米大統領選の誤報問題を掲載させて頂いたので、六年間、七テーマ、それに本書のために「スタッフカメラマンに求められるジャーナリズム精神」の章を追加し、第一部として構成した。
今回、書き下ろした「スタッフカメラマン……」は、長く新聞カメラマンとしていろいろな経験をし、さまざまな局面に出合いながら感じていたことを綴ったものである。内容をかいつまんで言えば、情報量によって人間は変わってしまうものなのか。現場と東京とのニュースに対する意識・感覚の大いなる差はどうして生まれるのか。戦争と宇宙開発の関係から知った生命の重みの差とは何なのか。アジアの大ニュースに情報大国アメリカの担保がなぜ必要なのか。さらには、ベトナム戦争から湾岸戦争まで、戦争という究極の事件取材において当時、思ったことを書き記した。これらは、現役時代とは違って客観的にマスコミの世界が見られるようになった今、自然に思い浮かんだ問題と疑問の数々である。言うなれば、新聞社を辞して六年という時間の「装置」を経た、私にとって忘れられない諸々なのである。
新聞社の花形は記者(ライター)である。私の場合、入社当時から「撮って書くカメラマン」として養成され、ライターと同じように地方の支局を経験し、察回り(警察を拠点に取材活動をすること)から遊軍まで記者活動の貴重な経験をした。国内から海外まで、私一人で、単独で取材に出かけるケースが多かった。記者とカメラマンはペアで行動するというのがそれまでのパターンであったが、今ではほとんどが単独行動だ。つまり記者兼カメラマンは時代の要請であったのだ。だからこそ、私はここで新たに章をたてることで、カメラマンにジャーナリズム精神の必要性を求めるのである。私は、デスク、部長時代、後輩にいつも「カメラマンこそ記事を書け。ライターこそ写真を撮れ」と言ってきた。それは、お互いを知ることで、記者は写真本来の力を、カメラマンは記事を書くときにどんなデータが、そして、ねらいはどうなのかという必要性が求められ、自ずと勉強になるからだ。私の経験から言うと、単独で取材活動をしていると、あるニュースに接したとき、これは写真で大きく伝えたほうが良いなと思うケースと、いやこれこそ記事で事細かに報道したほうがベターだといったケースを自分の中で使い分けられるようになる。それが証拠に、「優れた記者はやはり優れたカメラマン」であったという先輩に、私は何人も出会ってきた。
第二部で野中章弘氏との対論を掲載したのは、野中氏がマスコミに対して前向きでありながら、鋭い批判の持ち主であることを私は知っていたからであり、対論で私とは違った観点から一極集中報道に対して意見をずばり言ってくれるであろうと確信したからである。野中氏は、アジアプレスというフリージャーナリストの集団を主宰し、数年前には朝日新聞の紙面審議会委員というお目付役ともいえる大きな仕事も経験している。
また、本書を完成させるうえで、現代人文社編集部の木村暢恵さんには本当にお世話になりました。野中さん、木村さんのお力添えなくしては本書は生まれませんでした。あらためて感謝致します。
二〇〇六年六月吉日