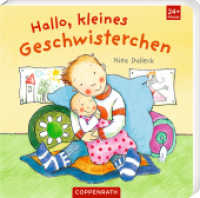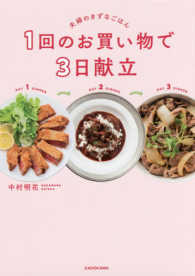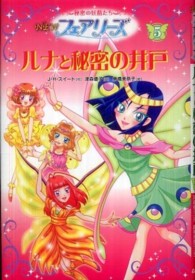出版社内容情報
今、刑事司法は「激動の時代」にある。そうした時代には、これをリードする明確な原理・原則が必要とされる。その観点から、司法改革に伴う諸立法を分析する。
第1部 防御――「包括的防御権」を考える
第1章 弁護人と押収拒否権
一 問題の所在――弁護人に対する捜索
二 押収拒否権の由来
三 押収拒否権の目的
四 本件捜索の問題点と「防御の守秘性」保護
五 まとめ――立法論について
第2章 弁護士の押収拒否権と「捜索遮断効」
一 問題の所在――札幌地決平10・4・29について
二 押収拒否権と業務上の秘密
三 捜索の可否と押収拒否の効果
四 準抗告と押収拒否権の意味
五 まとめ――押収拒否権と防御の利益
第3章 接見交通権の展望
一 接見と自白の任意性・信用性
二 準抗告と接見
三 罪証隠滅のおそれと3・24判決
四 捜査の顕著な支障説の当否
五 起訴後の余罪取調べと接見指定権
六 接見交通権の優位性
第4章 初回接見と憲法34条
一 最三小判平12・6・13の紹介
二 本判決の意義
三 初回接見と弁護人依頼権
四 判例と捜査の顕著な支障基準
五 判決の問題点
第5章 接見等禁止と被告人の防御権
一 問題の所在――接見等禁止処分と被告人・弁護人の書類の授受
二 接見等禁止一部解除について――一部解除先行説と自由な授受優先説
三 弁護人の自主規制について――弁護の自粛説と弁護の拡充説
四 防御に関する情報保護について――防御権と「情報プロセス」・「情報ストック」の保護
第6章 勾留の執行停止について
一 問題の所在――大阪高決平11・2・10の紹介
二 判例と「緊急の生活利益」基準説の定着
三 勾留執行停止の再構成――「防御の利益」基準説の可能性
四 結語――勾留執行停止の柔軟な運用
第2部 公訴――当事者処分権主義を考える
第7章 公訴権の濫用
一 最決昭55・12・17刑集34巻7号672頁の紹介
二 公訴権濫用論について
三 本決定の意義
四 まとめ
第8章 訴因の特定
一 問題の所在――覚せい剤自己使用罪と訴因の概括記載の背景
二 概括記載と実体法説
三 最終行為説、最低一行為説
四 手続法説と防御権
第9章 「訴因」の機能 ――共謀共同正犯
一 ある訴因逸脱認定――「共謀共同正犯」から「幇助」へ
二 起訴状の記載と審判の対象――事実記載説と新法律構成説
三 訴因と検察官の釈明――争点説と訴因説
四 「共謀」と「幇助」――縮小認定説と逸脱認定説
五 まとめ――「裁量糺問主義」の克服と「弾劾主義」の徹底
第10章 訴因の機能 ――恐喝罪
一 問題の所在――恐喝の原因と訴因逸脱認定
二 恐喝罪の訴因と事実記載説の意味
三 恐喝の理由と訴因の逸脱認定
四 防御の利益と訴因変更の要否
五 まとめ――「糺問化」の克服と弾劾主義の徹底
第3部 裁判――当事者追行主義を考える
第11章 裁判官の役割
一 職権尋問の実情
二 職権尋問の正当性
三 「裁量糺問主義」
四 「裁量糺問主義」から「真の当事者主義」へ
第12章 被告人質問と黙秘権
一 黙秘と被告人質問
二 質問権の優位性と証拠調べの「客体」説――職権主義の重視
三 客体説批判――黙秘権の優位性と当事者主義
四 「被告人質問」から「被告人陳述」へ――証拠調べの「権利」説
第13章 聴覚障害者と訴訟能力
一 問題の所在――刑事裁判の理解力
二 刑事裁判の認識理解力について
三 黙秘権と弁護人依頼権――意思疎通力について
四 「手続打切り」への道
第14章 不一致供述、自己矛盾供述
一 321条1項1号と供述の「不一致」
二 検面調書と供述の相反性の意味
三 328条と証明力を争う証拠
四 まとめ――刑訴法改正と不一致供述
第15章 自白の補強証拠
一 最一小判昭42・12・21の紹介
二 自白の補強法則の意義
三 補強法則の各論
第16章 犯行再現写真の証拠能力
一 問題の所在――最決平17・9・27と犯行再現写真の証拠能力
二 実況見分の意義
三 実況見分調書の証拠能力
四 被害者・被疑者の犯行再現、犯行関連供述の証拠能力
五 今後の展望――捜査手続「可視化」原理
第4部 上訴――検察官上訴を考える
第17章 控訴審と当事者主義
一 事実誤認・破棄と控訴審の役割――甲山事件のひとこまから
二 控訴審の運用上の問題点
三 事実誤認を理由とする控訴審の運用改革
四 控訴審と当事者主義の徹底
第18章 甲山事件と「控訴権消滅」論
一 甲山事件と2度目の検察官控訴
二 検察官控訴の合憲性について
三 2度の検察官控訴の問題点
四 「控訴権消滅」論
第19章 甲山事件と破棄判決の拘束力
一 問題の所在――裁判の経過
二 拘束力の対象――要証事実対象説と個別事実対象説
三 拘束力の幅――積極判断拘束説と消極判断拘束説
四 拘束力の消滅――証拠基準説と手続基準説
五 審理不尽・事実誤認の破棄判決と「拘束力の吸収」
第5部 司法改革――21世紀刑事司法を考える
第20章 被疑者取調べと司法改革の視点
一 「取調べ状況観察記録書」と問題の所在
二 司法「公共性の空間」論と取調べ適正化
三 司法改革と憲法原理の接点――包括的防御権と録音・録画
四 被疑者取調べのあり方――真実解明と適正手続
五 結語――「裁判員」制度と取調べ適正化の展望
第21章 被疑者取調べのビデオ録画
一 「密室取調べ」――司法改革の取りこぼし
二 「反省=自白」一体観から「弾劾型取調べ」観へ
三 取調べ可視化立法――取調べ規制と証拠能力規制
四 「可視化」原理と「包括的防御権」に基づくビデオ録画
第22章 証拠開示を伴う整理手続
一 新しい証拠開示手続の概要
二 ケース研究の視点から
三 弾劾目的の証拠開示と実質的な全面証拠開示
四 まとめ――整理手続から裁判員裁判へ
第23章 開示証拠の『目的外使用』
一 目的外使用禁止――議論の出発点
二 立法化への道――平成16年、第149回国会
三 「正当化条項」(法281条の4第2項)
四 目的外使用の構造
五 開示証拠の複製等の適正管理と「他人」――目的外使用禁止各論(1)
六 開示証拠複写物の4類型――目的外使用禁止各論(2)
七 他の事件への流用と「正当化条項」の機能――目的外使用禁止各論(3)
八 「正当化条項」と社会的相当性――目的外使用禁止各論(4)
九 民事事件への複写物の転用――目的外使用禁止各論(5)
十 まとめ――包括的防御権の視座から
第24章 司法改革の展望
一 「弁護が司法を動かす時代」
二 時代の原理――包括的防御権と当事者処分権主義
三 整理手続と被告人
はしがき――21世紀刑事司法の展望
1 刑事司法が動いている。20世紀末から21世紀初頭へと時代の流れにあわせて様相を変えている。20世紀末は、現行刑訴法が施行されて50年目を迎える時期にあたっていた。運用は一定の安定を見るようになった。それは「精密司法」と表現されて高く評価される面をもった。ただ、実は、捜査機関が密室の取調べで作成する「供述調書」を基盤とする「物語司法」であることも明白であった。そこには、「えん罪」が生まれやすい構造が潜むことになってしまった。
今、動きつつある「司法改革」は、これを担った者達の主観的意図とは別に、大局的、法史的にみれば司法の構造的弱点の改革を目指すものとなる。当然、旧来の運用とあるべき運用とがぶつかる。「激動の時代」が始まる。そうした時代には、これをリードする明確な原理・原則が要る。司法改革に伴う諸立法をながめ返しながら、これを探ってみよう。
2 第1に、捜査段階では、勾留段階から弁護人が公費で被疑者を弁護する時代がすぐに来る。捜査を常に監視できるプロが存在することになる。弁護人のプレゼンスは、大局的には捜査のありかたを変える。勾留期間を潤沢に使って被疑者取調べにより情報を得る捜査手法は限界に来る。裁判員裁判が見込まれる事件については、後の公判廷における自白の証拠能力を巡る争いを可能な限り防ぎ、迅速かつ的確な立証を検察官が余儀なくされる――被疑者取調べのビデオ録画は避けて通れなくなる。
第2に、検察官の公訴権行使は、検察審査会の審査の対象となる。しかも、今時の法改正で再度の起訴相当決議による起訴強制も導入された。国家が独占してきた公訴権を市民が監視し修正するものとなる。また、訴因変更手続のありかたも変わる。今までは公判では法律のプロ達のみで五月雨型の立証を行なってきた。しかし、市民である裁判員が関わる事件では、連続的開廷、集中審理方式を要する。その場合、訴因変更を介在させることは審理と心証形成に大きな混乱を生じる。公判前整理手続段階で早々に訴因を修正し、あるいは当初から予備的訴因でも訴追する運用が見込まれる。こうして、市民による裁判にふさわしい公訴提起が求められる。その意味で、公訴提起も「可視化」される。
第3に、2005年11月、証拠開示を伴う公判前整理手続が施行された。すでに各地で多様な事件について実施されているようだ。全体状況はまだ総括されていない。公判前整理手続は、請求予定証拠、類型証拠、主張関連証拠を段階的らせん的に開示して、被告人・弁護人側が争点を十分に煮詰めることができる条件作りを求めるものだ。しかし、検察側は、各ステージの要件を可能な限り厳格に狭く解釈運用する姿勢をみせている面もある。頑なな運用が定着すれば、円滑な裁判員裁判の運用は危ぶまれる。それだけに証拠開示の安定的な運用が整うか否か慎重な見極めを要する。
第4に、証拠調べの実施についても、裁判員が法廷でただちに心証を形成できる証拠資料の的確かつ理解可能な提示――プレゼンテーションを要することとなる。その実験も各地で始まった。このことが、あらためて公判中心主義、直接主義の理念に息吹を吹き込むこととなる。
第5に、控訴理由の構成、控訴審のありかたも変わらざるを得ない。今、控訴審は原則として、あらたな事実については、その取調べを控える制限的な運用で固まっている。事後審の徹底と言ってもいい。今後も、市民が関与した裁判について、事実認定を理由に破棄することは例外的なことにならざるをえまい。量刑不当についても、裁判員を交えた裁判体の判断をプロの3名の裁判官でくつがえすことは例外的にしかできまい。他方、市民が加わったために「感情司法」ともいうべき現象が起きるおそれもある。その不正義を正す役割を控訴審が担うこととなることも予想される。
第6に、刑事手続全般にわたり、刑事弁護の質の向上が一層求められる。捜査段階から公判前整理手続を経て裁判員裁判が実施されることを見込んだ準備を要する。今、捜査段階では、身体拘束された被疑者が取調べを受けているのに対応して、接見を中心とする弁護を行っているが、今後は、独自調査を柱にする新たな弁護活動が必要になる。
3 以上の流れの中から読み取るべき、21世紀刑事司法をリードする原理は2つある。
まず、「可視化」原理である。手続の世界では、手続のかたちが正義を決める。法律家のプロが担った司法から、市民が監視し、参加し、決定する司法へと変容を遂げつつある。「可視化」の徹底こそ、市民が納得する正義を刑事裁判の場で実現するものである。
今ひとつの原理は、被疑者・被告人の「包括的防御権」の思想である。国家が刑罰権発動を求める相手側となる市民は、被疑者・被告人たる地位に強制的に置かれる。「防御」は多様かつ多面的でなければならない。自由権、請求権、社会権など人権の多様な性質を複合した包括的な防御と弁護の権利を要する。刑事手続固有の人権のあり方でもある。これを包括的防御権と名付ける。
本書は、かかる視点設定を示すことをねらいとして、ここ8年ほどの間にまとめた論文を収録したものである。
4 収録した小品を振り返り、時代の流れと重ねるとき、そこから今後の課題もみえてくる。
まず、今の時代の特徴は、「解釈から立法へ」というべきものである。大枠を定める条文と法律の構造を手がかりにして精緻な解釈論によって刑事手続のかたちを作った時代から、「立法」により構造を変革した上で再度精緻な解釈論を組み立て、しかも運用でこれを試す時代に入っている。立法、解釈そして運用のそれぞれの過程を見通すダイナミックな研究が今後求められる。
次に、刑事司法の変化の「流れ」が急だ。無惨で残酷な犯罪が多発する中、「世論」の求める現実的でむき出しの「感情司法」に押し流されやすくなる危険もみられる。この点からも、21世紀司法の「正義」をかたち作る上で、「被害者」の法的地位を確立し、国家に対する正当な評価と救済を求めるシステムの構築が不可欠だ。
世界の司法と日本の司法の大局的な比較検討も、必要になっている。世界で活きる日本が、司法の分野で「独善司法」になっていないか見極めが要る。被疑者取調べを密室で行なう実務を守るべき法文化と錯誤する感覚は是正すべきだ。このことを含めて、世界の「司法における正義」をリードできる「かたち」を提言しなければなるまい。
最後に、21世紀のあらたな犯罪現象の特徴――組織犯罪、インターネット犯罪、ストーカー犯罪――に対処できる厳正な刑法とその運用を支える適正な刑事手続のあり方もこれから問われる。
以上は、今後の研究の課題としたい。
5 最後に、私事にふれる。筆者は、今、甲南大学法科大学院で刑訴法を教えている。ただ、新司法試験と法科大学院は、「試験で選ばれるプロ」という特殊な法曹養成を求める制度だ。このため、地方にある小規模ロースクールは新司法試験の合格者数によっては、存立すら危ぶまれることとなる。それだけに、院生にはなによりも判例を軸にした基本的知識の習熟を指導している。本書のような学術論文集を読ませる余裕はない。
将来、ロースクールが安定期に入ったときには、本書をテキストとする刑事訴訟法演習で、未来のローヤー達とあるべき刑事司法論を教室で活発に議論したいと思う。その日が早く来ることを願ってやまない。
さて、学術論文集出版が困難な中、本書の出版をお引き受けいただいた現代人文社社長成澤壽信氏には心から感謝したい。また、本書は、甲南学園伊藤忠兵衛出版助成基金の助成を得た。記して学園に感謝したい。
2006年4月
大阪拘置所近くのレストランにて
[豈頁] 修