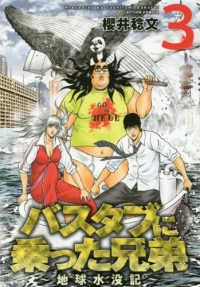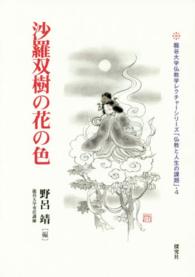出版社内容情報
1970年から今日まで、日本と世界の政治、経済、社会構造は激しい変化を遂げた。果たしてそれは人々を幸福にしたのだろうか。時代を読み解く評論を厳選した評論集。
【一九七〇年―一九七九年】
安保条約の実質的改定――一九六九年日米共同声明第五項の検討
司法政策の最近の特徴と司法権独立をめぐる理論状況
いわゆる任官差別問題について――司法制度の反動的再編成
論拠の薄弱な裁判長忌避――青法協攻撃の意図歴然
安保と政治反動――強化される治安体制
別件逮捕・自白強制・弁護人放置なぜ判断避けた――仁保事件上告審判決(最高裁一九七〇年七月三一日)
あまりに政治的な訴追委――司法権独立の尊厳を蹂躙
裁判官の政治的中立性
政治権力による再編成が問題の根源に――望まれる国民の裁判所
司法政策の今日的特質
第九回司法問題法学者懇話会(一九七二年四月八日 於・青山学院大学)
解けた・原判決の矛盾・――メーデー事件控訴審の判決理由を読んで
刑法「改正」は「憲法滅ぶ」の道
いわゆる「公害罪」について
世論への挑戦
問われる最高裁のあり方
鬼頭問題を生んだ司法の土壌
予断と偏見
背景をなす人権軽視の態度――「弁護人抜き裁判」特例法案
【一九八〇年―一九八九年】
青少年をめぐるイデオロギー攻勢と少年法改悪
相次ぐ再審開始とその背景
八〇年代の司法反動とその役割
少年法の岐路
金大中裁判への疑義
最近の改憲の動きと統治政策の分析
裁判官不祥事件の根底に潜むもの
軍国主義化の中の司法反動――人権保障機能の後退と行政追随
司法権と行政権の関係――大阪空港訴訟の最高裁判決にみる
拘禁二法案と民主主義の命運
再審の逆流を許してはならない
問い直される司法の姿勢
安保体制論と権利闘争
再審死刑囚の身柄問題
民主的良識の力量を示すもの――拘禁二法案再提出の断念
相次ぐ冤罪事件――問われる司法のあり方
「裁判」をめぐる現代的論点と民主主義法学の課題
ロッキード事件について
悪法としての「スパイ防止法」
ひとびとの連帯と歴史
思考の自立、職権の独立
見捨てられていく子供たち
警察依存社会か自律的市民社会か
検察に人なし
にんげんのにんげんのよのあるかぎり……
焦燥感にも似たもの
平和、人権、民主主義には運動が必要である
「スパイ防止・処罰」の発想を捨てよ
国家秘密法と国民の責任
今こそ体験を伝え道理を説くべきとき――国家秘密法は平和を保障しない
靖国神社と政教分離の原則
平和主義の旗印を高く掲げて――国家秘密法と平和的生存
盗聴不起訴の不当性
近代司法原理の現代的意義
日本の陪審制をさぐる
誤判防止策の確立を
松川事件が訴えるもの――松川事件無罪確定二五周年に当たって
警察国家再現の防止のために
人権侵害、誤判の温床 拘禁二法案
少年法の基本忘れた警察
【一九九〇年―一九九九年】
陪審論議に望む
何を守るための裁判所か
坂本弁護士のこと
なぜ空洞化したか 司法権の独立
「司法問題」を考える――「司法の危機」から二〇年
なぜ後を絶たぬ誤判
私たちは少数派ではない
小選挙区制は百年の禍根を残す
後を絶たぬ冤罪とその温床
小選挙区制を廃止する歴史的責任
人権の砦は死んだか――神坂任官拒否を批判する
政界再編の行きつくところ――国民の声反映しにくく
社会不安利用 「読売」の「緊急事態」対処――軍備増強勢力に利用の危険性 「朝日」提言
理性的社会と破防法――違憲の悪法の濫用を許してはならない
危険な盗聴捜査の立法化
日本社会と民主主義――刑事法学・裁判法学の角度から
寺西懲戒裁判で問われているもの――自由のない裁判官に市民の自由が守れるか
官僚臭にみちた最高裁・寺西懲戒決定と法曹一元
民主主義法学の気風
少年法を警察・検察による少年支配システムに変えてはならない
【二〇〇〇年―二〇〇五年】
巨大化した権限・組織にメスを――警察刷新会議の課題
司法官僚制度の形成と強化の歴史
弁護士のあり方――人権擁護の理念像
有事立法や司法改革との関連で――横浜事件再審請求の現代的意義を考える
私は忘れない――本間重紀さんの死を悼んで
手から手へ――『希望としての憲法』出版に籠める思い
憲法改悪の動きの中での言論弾圧事件の狙い
平和憲法の柱を否定
ビラ配り弾圧を許してはならない
「法と権力」研究私史――一九六〇―二〇〇五
エピローグ 最後の最終講義
まえがき
本書は、私が一九七〇年から二〇〇六年三月までの約三五年間に発表した時評的性格の濃い八八篇の小文を発表順に並べ、最後に回顧及び随想二篇をエピローグ風に加えて編んだものである(若干の字句修正は施した)。
小文の各テーマは、編集者の求めに応じたものや自分で決めたものなので、勢い私の専門(刑事訴訟法・裁判法)や好みを反映しており、そのため、その時代、その時期における「法と権力」と民衆との矛盾、葛藤、対立の重要なイッシューを網羅したものとはなっていない。それどころか逆に、極めて限定された分野のテーマを繰り返し扱う結果ともなっていて、こうして一書に収めてみると部分性が目立つ。
しかし、この部分性は、批判の関心や方法の継続性ないし一貫性と相俟って「法と権力」と民衆との矛盾、葛藤、対立のその時代、その時期のありようをかえって鮮かに写し出す結果となっているようにも思える。私としてはそこに本書を編むことの現代的意義を見出せるように考え、刊行することにしたのである。
もっとも、私の場合には、書いたものが論文的スタイルをとった場合でも、テーマの設定や分析、論証、論述のしかたなど全ての点において時評的性格を色濃く持っている場合が多い。その意味では、本書は、私にとっては、論文集の形をとった著作と重り合う同種同類のものとの意味合いを持つ。そうであるにつけ、本書の読者が既刊の論文集にも関心を向け参照して下さることを希望したい(巻末著者プロフィール参照)。
この春、私は専修大学を定年退職し、市井の研究者として暮らしていくことになる。思えば、私は物心ついた頃は戦時下にあり、国民学校で軍国少年としての教育を受けたが、敗戦を機として世界や日本を覆った平和、人権、反ファシズム(民主)、そして福祉(平等)の理念に深い共感、共鳴を覚え、民衆の立場を守る理論的イデオローグの役割を果たしたいと考え、懸命になって時代の課題に取り組んできた。その軌跡の一端は本書三一八頁以下で回顧している。
しかし、現在、日本や世界が直面している戦争、人権侵害、強権、そして弱肉強食の「現実」の深刻さ、もっと有り体にいえば人間破壊、社会解体のすさまじさを直視するとき、力が足りなかったとの思いを禁じ得ない。そうであればこそ、この厳しく困難な「現実」の中に潜み胎動し生育しつつある「もう一つの現実」を確かなものにする動きに、研究者として、あるいは一人の人間として余力を傾けたいと切に思う。その脈絡で、私は本書を過去三五年余の営みの回顧的意味合いにおいてではなく、その営みが「もう一つの現実」への「展望」と「希望」の種子を果たして用意し得たかという総括的意味合いにおいて位置づけたいと考えるのである。
そのような意味合いを籠めた本書を、私は、民主主義法学の建設と発展とに大きく貢献された渡辺洋三先生に捧げたいと思う。私は、六〇年安保闘争直後に法律家を志したあの時期に、先生の名著『法社会学と法解釈学』(岩波書店、一九五九年)や『法というものの考え方』(岩波新書、一九五九年)に接することがなければ、「法というもの」に理論的な関心を抱くことは勿論のこと、研究者を志すことも決してあり得なかったであろう。大学院時代に先生の「現代財産法の諸問題」を聴講させて戴き、その後研究者の道に入ってからも御著書や御論文のみならず学会(とくに民主主義科学者協会法律部会)や研究会等において、先生の鋭利且つ広い視野に立つ「現代市民法論」を直接・間接に御教示戴ける幸運に恵まれた。その民主主義精神の漲る理論は、今も私の学問的なよるべとも魂ともなっていることを強く感じる。病床にある先生にこの書物を捧げることにより、多年の御学恩に深く感謝の意を表したいと思う。
最後に、本書の刊行については、現代人文社の成澤壽信氏の積極的な御協力を得た。記して感謝申し上げる。
二〇〇六年三月一〇日
小田中聰樹