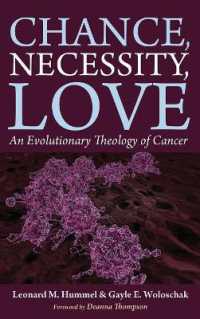出版社内容情報
ドイツの少年司法制度は、刑事法的色彩を強くもつ制度である。現在、「教育思想」による改革が進められている。DVJJの改革提言は、日本における少年法改革に参考になる。
ドイツ少年刑法改革のための諸提案
はじめに
1. 少年刑法の目的と任務
2. 人的な適用範囲
2.1 刑事責任年齢の下限
2.2 青年を少年刑法に含めること
2.2.1 現在の法律関係と改革の必要性
2.2.2 青年に関する特別規定
2.3 21~24歳の者(「若年成人」)を含めること
3. 物的な適用範囲
4. 少年刑事手続の諸原則
4.1 参加の原則
4.2 補充性の原則
4.3 裁判所外における紛争規整の優先
4.4 不利な地位に置かれない原則
4.5 補整の原則
4.6 迅速性の原則
4.7 専門性の原則
5. 刑法上の責任
6. 軽微犯の実体法上の非犯罪化
7. 紛争を規整する手続の促進
8. 手続関与者の資格と専門教育
8.1 少年係裁判官と少年係検察官
8.2 少年援助の担い手
8.3 警察
8.4 少年係保護観察官
8.5 執行に関係する者
8.6 ユーゲント・アカデミーで専門教育を適切に行う構造をつくること
9. 刑事手続における少年援助の地位と協力
9.1 刑事手続における少年援助の任務
9.1.1 少年援助の一部としての少年審判補助
9.1.2 専門性
9.1.3 助言機能と援護関係、証言私人起訴
13.4 付帯私訴手続
13.5 手続打ち切り決定の透明な仲介;援助の提供
14. 実体処分の改革の必要性
15. 二元主義の課題
16. 複数の実体処分の併合
17. 14~15歳の者に関する自由剥奪処分の禁止
18. 改革された制度における少年刑法上の制裁
18.1 さらなる制裁賦課のない有罪宣告
18.2 損害回復
18.3 社会内処分
18.3.1 社会内の援助的な処分
18.3.2 治療的・医療的な処分
18.3.3 社会内の懲罰的な処分
18.3.4 期間、指示の変更
18.3.5 社会内処分の強制可能性と代替拘禁
18.3.6 執行時効
18.4 運転免許の剥奪
18.5 少年拘禁
18.5.1 少年拘禁に対する根本的な批判について
18.5.2 少年拘禁の改革
18.6 少年刑
18.6.1 少年刑の賦課の展開
18.6.2 少年刑の要件
18.6.3 少年行刑法
18.6.4 閉鎖的収容
18.6.5 少年刑の期間
18.7 少年刑の賦課及び執行の延期
18.7.1 少年刑の前の保護観察(少年裁判所法第27条)
18.7.2 少年刑を言い渡す場合の保護観察のための刑の延期
18.7.3 少年刑を言い渡す場合の「事前の保護観察」
18.7.4 保護観察のための残余刑
序 言
少年たちは、巷で言われているよりも悪くない。他方で、教育程度の低い少年は、冷遇されていると感じている。こうした少年の中に、社会的弱者に対して攻撃を行う傾向を持つ、いわゆる「荒っぽい物質主義者たち」がいるDVJJの第二次少年刑法改正委員会の最終報告書と時を同じくして公表されたシェル研究による2002年の報告書の中心的な指摘は、このようなものである。そうでなくてもすでに、成人になるための成長過程は少年にとって重い負担になっている。そこにおいて残っているチャンスを潰さず、若年者に犯罪者としての烙印を押さず、彼らを疎外することなしに、少年犯罪にきめ細やかで、なおかつ柔軟に対応することが重要なのであれば、少年や青年の可罰的な行動の背景と発生条件において、こうした視点が考慮されなければならない。
「誰も犯罪者として生まれてくるわけではない。若者にフェアなチャンスを!」このようなモットーの下で、DVJJのヘンリー・マスケ基金は、少年を邪魔者と見る視点から、われわれの少年とのつき合い・協働における新しい文化へ、というパースペクティブの転換を訴えてきた。「問題を抱え込み、社会のくずとして、あたかも社会的に残るリスクであること、犯罪学、社会学、教育学の現代的な研究に知見を適合させること、実務に関連し、時代に適い、若年者のニーズに方向づけられた対応制度を作り出すことを、特に目的としている。その提案は、行為者と被害者、そして共同体の間にある紛争の規整に寄与する意図を持っている。それは、結果指向、合理性、そしてヒューマニティを義務づけられた、状況を見通す能力と思慮深さを備えた少年刑事政策の表現である。この基盤の上で、活発な議論がさらに行われることを、われわれは期待している。
代表して
ベルント=リューデガー・ゾネン
-

- 洋書
- The Coming