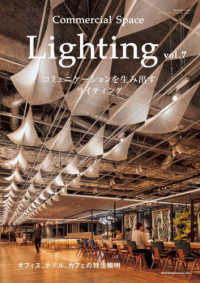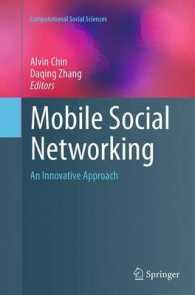出版社内容情報
過去10年間に高松家裁で処理された殺人・強姦・傷害致死・放火等の非行事案について処分内容や再非行の有無を検証し、社会調査や少年審判のあり方、被害者手当て等を提案。
はじめに――真の少年非行対策をめざして
少年保護事件処理概略図
第1部
事例で見る少年非行その後
written by 廣田邦義+畠 毅郎
データから見た重大事件の再非行
香川県内の重大事件数の推移
処分の内訳
再非行の割合
再非行の内容
中学生非行の再非行率
データから見た少年非行の特徴
1 少年の重大事件の大半は強盗である
2 強盗事件は増加しているか
3 少年の強盗事件の特徴
4 少年非行の最大の特徴は共犯率の高さ
事例から学ぶ少年非行
事例1
「元カレ」の家を放火した女子高校生
◆孤独感と攻撃性は比例する
◆集団内の序列と重大非行
◆重大事例の背景に潜む〈マージナル〉
事例2
自殺願望を持つ少年――殺人未遂の事例
◆殺人心理の背景に潜む自殺願望
事例3
祖母を殺害した事例
◆動機とは何か
◆原因論と処遇論
事例4
野球少年の再生;集団非行による強盗 ◆致傷
◆環境転位の効用
事例5
強制わいせつ少年の試験観察
◆性犯罪の背景に見られる家族システム
事例6
強姦のできないわいせつ>はじめに
調査官を取り巻く実情
1 最高裁判所当局の二枚舌(double-tongued)
2 調査官本来の活動をするには足りない人員
3 調査官広域異動政策がもたらしたもの
4 マニュアル化の浸透
5 パソコンの導入
劣化させられたなかで出現してきた4つの調査官タイプ
1 流れに棹さすタイプ
2 流れ川を棒で打つタイプ
3 流れにまかせていくタイプ
4 流れから出て、密着型をめざすタイプ
地域に密着しようとする(あるいは密着した)調査官のあり様について
―「流れ川を棒で打つ」あるいは「密着型」タイプ―
甦らせる手立ては
1 最高裁当局は、調査官の役割と専門性に見合った施策を行う
2 家裁の啓発宣伝に調査官を活用し、国民に開かれた家裁をめざす
3 「少年友の会」創設、充実強化を図り、付添人活動の活用を活性化させる
少年・保護者から見た警察と家裁
written by 廣田邦義
警察
1 逮捕に関する問題点
2 勾留に関する問題点
3 非行発覚から呼出しまでが遅い
4 保護者の立会い
5 面会
家庭裁判所
1 裁判官
2 調査官
第3部
少年非行対策への提年非行に関する適切な情報公開に向けた取組み
結びに代えて
少年非行の被害者と加害少年に対する援助
ー国家責任の明確化に向けて
written by 倉良一
検討の視点
被害者の救済と蘇生とは?
加害者の救済と蘇生とは?
国家の責任と役割
より良い解決をめざして
福祉から遠ざかる少年非行
ー結びに代えて
written by 岡田行雄
はじめに
触法少年事件に関する警察による「調査」
14歳未満の少年の少年院送致
保護観察中の少年への新たな措置
結びに代えて……非行少年に真の福祉的援助を
執筆者紹介
はじめに――真の少年非行対策をめざして
少年保護事件処理概略図
第1部
事例で見る少年非行その後
written by 廣田邦義+畠 毅郎
データから見た重大事件の再非行
香川県内の重大事件数の推移
処分の内訳
再非行の割合
再非行の内容
中学生非行の再非行率
データから見た少年非行の特徴
1 少年の重大事件の大半は強盗である
2 強盗事件は増加しているか
3 少年の強盗事件の特徴
4 少年非行の最大の特徴は共犯率の高さ
事r> ◆環境転位とレディネスの問題
◆点の調査と線の調査
事例8
虚像の「伝説」を用いてのし上がる少年
◆非行少年の序列社会
事例9
喧嘩の寸前で思いとどまった少年
事例10
芸能界を夢見る男子中学生
◆大波小波改善型
第2部
少年法の担い手
ー非行少年とどう向きあうか
少年事件裁判官論
written by 生田暉雄
はじめに
「最近の一ケースに関連して思うこと」
コメント
劣化させられた家庭裁判所調査官制度
ー甦らせる手立てはあるか
written by 杉山政志
はじめに
調査官を取り巻く実情
1 最高裁判所当局の二枚舌(double-tongued)
2 調査官本来の活動をするには足りない人員
3 調査官広域異動政策がもたらしたもの
4 マニュアル化の浸透
5 パソコンの導入
劣化させられたなかで出現してきた4つの調査官タイプ
1 流れに棹さすタイプ
2 流れ川を棒で打つタイプ
3 流れにまかせていくタイプ
4 流れから出て、密着型をめざすタイプ
地域に密着しようとする(あるいは密着した)調査官のあり様について
―「流れ川を」という言葉の独り歩き
逆送の類型
1 年齢超過型
2 メニュー切れ型
3 できあがり型
4 重大非行型
改正前の原則逆送事件の例
1 暴走族のリンチ事件(傷害致死)
2 祖母殺害事件(殺人)
原則逆送事件の基本的視点
1 原則逆送事件の過半数は傷害致死
2 従来の診断的社会調査に処遇プランを加える
処遇プランの提案
1 試験観察での処遇プラン
2 少年院での処遇プラン
少年事件に関する情報公開
written by 岡田行雄
はじめに
警察と弁護士による情報公開の意義と限界
家庭裁判所による情報公開の意義とジレンマ
少年非行に関する適切な情報公開に向けた取組み
結びに代えて
少年非行の被害者と加害少年に対する援助
ー国家責任の明確化に向けて
written by 倉良一
検討の視点
被害者の救済と蘇生とは?
加害者の救済と蘇生とは?
国家の責任と役割
より良い解決をめざして
福祉から遠ざかる少年非行
ー結びに代えて
written by 岡田行雄
はじめに
触法少年事件に関する警察による「調査」
14歳未満の少年の少年院送致
保護観察
はじめに
――真の少年非行対策をめざして
処罰範囲の拡大等を柱とする改正少年法が、その提案から数カ月であっさりと国会で可決されたのは2000年11月のことでした。その前から、少年審判への検察官関与等が、少年司法の担い手が量的・質的に不足している地方では、少年の成長・発達に大きなマイナスになるのではと思い、ひとりやるせない気持ちで一杯になっていました。
そんな折、当事住んでいた愛媛県の隣にある香川県高松市の家庭裁判所(以下、家裁)調査官たちが、少年法改正に関する独自の案を発表したとの新聞記事を読み、興味を覚えたのです。ちょうど、ある雑誌に、少年法改正のあり方について小論を執筆する仕事を引き受けていたこともあり、一度、その調査官たちに、その案の内容や発表に至った契機等についてお話をおうかがいしたいと思い、直接高松家裁に電話をかけました。ありがたいことに、近々高松の調査官たちが集まり研究会を開くので、そこでお話ししましょうとのこと。早速参加させてもらいました。
その集まりの場は、高松家裁の裁判官を務められた生田暉雄弁護士の事務所で、少人数でしたが、少年司法の現場で悪戦苦闘してきた方たちが揃っていましいては、再非行の追跡調査が可能であり、調査官としての長年の経験によれば、それほど重大な再非行は起こっていないのではという意見があり、早速調べてみようということになりました。
そこで、その次の回から、最近10年間に高松家裁で処理された重大な非行事案について、まず、その処分内容、再非行の有無等を調査官が手作業で確認し、その結果を踏まえて議論を重ねました。そうするうちに、ここでの議論を基にして、少年法が重大事件の再非行防止にどれだけ役立っているか市民に問おうではないかということになりました。
さらに、重大事件の再非行率だけでなく、重大事件をいくつかに類型化し、具体的な事件での処遇のあり方についても議論を重ねました。こうやればうまくいくという非行少年の処遇プランを具体的に提示することこそ重要だと感じたからです。こうした議論によって、真の非行対策とは何かが明確になり、少年法をパワーアップすることになります。少年の主体的な非行克服は、新たな被害者を増やさないという意味で市民の利益にもなるはずだからです。
もちろん、真の少年非行対策をめざすには、重大な事件を起こした少年の処分に注目するだけでは足りないとの意見も出たとしても、それで終わりになるのではなく、少年やその被害者にも希望の灯りがともる社会を造ることが、これから生まれ来る子どもたちに対する大人の責務なのです。
なお、本書について、皆さんに予めご理解いただきたいことが3点あります。まず、読みやすさを第一と考えて、原則として参考文献等の注記を省いています。次に、少年の問題行動を表す言葉として巷に流布している「少年犯罪」ではなく、「少年非行」という言葉を用いています。それは、少年犯罪は少年の個人責任を前提としている狭い概念でしかなく、少年法は、少年による犯罪の他にぐ犯(保護者の監督に従わないなど、将来罪を犯すおそれのあること)や触法行為をも対象にしており、何より少年非行が少年個人の問題ではなく、私たち社会の問題なのだと捉えるべきだと考えたからです。最後に、強盗、強姦、殺人、放火、傷害致死といった事件を総称して重大事件と呼んでいます。これは、官庁統計上「凶悪」と評される事件には、傷害致死が含まれていないことに加え、これらの事件は、被害者やそのご遺族はもちろん少年本人やその関係者にとっても重大であると考えたからです。
どうか、私たちのこうしたこだわりを頭の隅に置き
内容説明
過去10年間、高松家裁で処理された殺人・強姦・傷害致死・放火等の非行事案について処分内容や再非行の有無、少年審判のあり方、情報公開の意義と問題等を分析、提言。
目次
第1部 事例で見る少年非行とその後(データから見た重大事件の再非行;事例から学ぶ少年非行)
第2部 少年法の担い手―非行少年とどう向きあうか(少年事件裁判官論;劣化させられた家庭裁判所調査官制度―甦らせる手立てはあるか;少年・保護者から見た警察と家裁)
第3部 少年非行対策への提言(「原則逆送」事件における社会調査のあり方;少年事件に関する情報公開;少年非行の被害者と加害少年に対する援助―国家責任の明確化に向けて;福祉から遠ざかる少年非行―結びに代えて)
-
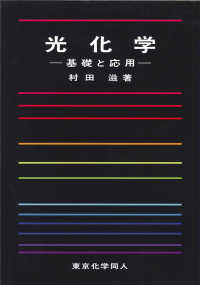
- 和書
- 光化学 - 基礎と応用
-
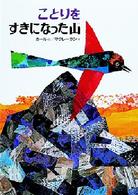
- 和書
- ことりをすきになった山