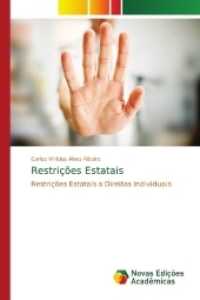出版社内容情報
病気になったときに頼れるのが公的医療・福祉制度。オーバーステイの外国人が使える制度もあるのです。相談事例と入手困難なお役立ち資料満載の1冊。
第1章
いまだに続く「いのちの差別」
各地の事例から
1. ペルー人の母と小児喘息の子どもを救うために〈東京〉
【未払い医療費】
2. 病院が、死亡したフィリピン人の未払い医療費を裁判で請求?!〈千葉〉
【健康保険】
3. 移住労働者に対する、健康保険制度の差別適用〈静岡〉
【入院助産制度】
4.入院助産について〈山梨〉
5.入院助産・国保交渉騒動記〈栃木〉
【養育医療】
6.タイ国籍の子どもに養育医療(未熟児医療)が認められる
【育成医療】
7.閉鎖的な行政の壁を破るために〈山梨〉
8.山梨育成医療初の適用例〈山梨〉
【更生医療】
9.HIV患者、更生医療「不適用」へのドラマ〈東京〉
【小児慢性特定疾患】
10.千葉市における小児慢性特定疾患適用事例〈千葉〉
【大気汚染医療費助成】
11.町田小児喘息事例のその後〈東京〉
第2章
「流れ」を変え、権利をかちとる
外国人医療と運動のネットワーキング
1. 移住労働者の医療・福祉│20世紀最後の10年を振り返る
2. 外国人医療・生活ネットワークの発足
第3章
地域で共に生きるために
自治体へのアプローチ
私たちのとなりには、ごくあたりまえのように移住労働者とその家族がいる。移住労働者問題というと、世間では「国際問題」だと思う向きも多いかと思われるが、これらは立派な国内問題でもある。そして、生活に密着し、誰もが避けて通れない問題、それが医療・福祉に関する分野である。
移住労働者の支援活動に携わる人々にとって、医療・福祉問題は難しい課題の一つであるといわれている。それは、制度の仕組みが複雑で多岐にわたっているからだけではない。ことは当事者の生命・生存に関わっている。異国の地でひとたび病気になるということは、身体的・経済的損失が大きいだけではない。それをきっかけに今まで築き上げてきた生活が崩壊していくこともある。継続して関わるのは非常に辛い課題である。個人の努力に依拠せざるを得ない、小さな支援団体であればなおさらである。
加えて、市区町村窓口での門前払いは日常茶飯事である。行政側の「根拠なき取り扱い」が、外国人医療問題の解決をより一層遠いものとしている。古くから出されている、法のコメンタールやマニュアルのどこを見ても、在留資格のない外国人をどう取り扱うべきかということは書いていない。福祉の研究者や専門家はィブな活動のひとつであるということもできるかもしれない。うまくいってもいかなくても、医療・福祉問題は、当事者のみならず、支援者とそのグループを確実に鍛え、育ててくれるのである。
このブックレットは、「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」の月刊機関誌である『M-ネット』に過去3回(2000年7月・2002年10月・11月)にわたって掲載された、医療・福祉問題の特集記事を集め、一部加筆訂正して構成したものである。この間のさまざまな事例や成果を多くの方に知っていただき、全国のNGO及び支援組織、あるいは病院や地域でソーシャルワーカーとして働く人たちに活用してほしい、という思いから作成した。
本編は主に支援事例と行政交渉から構成されている。また巻末には、膨大な法令の中から法的根拠を探し出す苦労を省くために、窓口での交渉に必要な法令や通知、政府見解をまとめた資料集を載せてある。中には簡単に手に入らないものもあるので、本編共々各地でのさまざまな討論や行政交渉などの運動のお役に立てていただければ幸いである。
-

- 和書
- 槍ケ岳開山 文春文庫