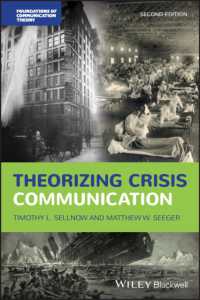内容説明
児童によっては、物語は得意だけど説明文は苦手、短い文章はいいけど長文は苦手など実態や意欲が異なります。自分の表現したいものは、どの文種がふさわしいのか、目的や相手に応じて自在に選ぶためには、幼い頃から様々な文種に出会わせることが大切です。多くの作品群の出会いの場をいかに設定するか。先生方の個性と児童の実態に合わせた文集と文種の組み合わせを愉しまれてください。
目次
実践1 Q&A「文集で学力をつけることができるのでしょうか」(第一学年―友達のよさを見付け、よさを感じることで表現技能が広がる文集づくり;第一学年―多様な内容に出会い、作文の楽しさを感じる文集づくり;豊かな表現が広がる、書くことが好きになる文集づくり;いろいろな文種を楽しむ児童が持つ文集づくり;内容に応じて文章の形式を選んで楽しんで書く文集づくり;資料を基に自分の思いや考えを表現した文集づくり)
実践2 Q&A「文集にはどのような種類がありますか」(第四学年―気軽に参加して表現技能や文種が広がる文集づくり;第四学年―読み手を意識して書く文集づくり;第四学年―児童の文種や表現が広がる教室環境としての文集づくり;第五学年―友達の作品のよさを味わわせながら、文種を広げる文集づくり;第六学年―書き手と読み手を行き来しながら表現が広がる文集づくり;第六学年―友達の表現方法を獲得し、文種の違いに気づく文集づくり)
実践3 Q&A「文集を作るとき鑑賞会は必要ですか」(第六学年―やりとり弾む「えんぴつ対談」鑑賞会;第五学年―説明の愉しさを味わう鑑賞会;第六学年―友達・自分再発見!あなたにお薦め鑑賞会;第六学年―「リレー掲示板」での鑑賞会;第六学年―学級通信の投書に重ねさせる「紙上鑑賞会」;第一・四・六学年―みんなでつくる愉しさに誘う『家族鑑賞会』)
実践4 文集活動の継続と発展Q&A(「文集を発行した後の指導としての評価・交流活動について具体的な指導のあり方を教えてください。」;「文集を活用しての書く、話す・聞く力を伸ばすための事後の指導法を教えてください。」;「中学校ではどのように発展させた文集指導をしていけばよいでしょうか。」;第一学年―よさを伝え合い書くことが好きになる文集づくり;第二学年―鑑賞会でひろがる文集づくり;第四学年―文章世界がひろがる文集づくり;第六学年―読みたい、書きたい、作りたい!オリジナル文集づくり)
著者等紹介
白石壽文[シライシヒサフミ]
1937(昭和12)生。広島大学大学院修了。広島大学助手、広島大学教育学部附属中・高等学校教諭、佐賀大学教育学部講師・助教授・教授を経て、2003(平成15)年退官、佐賀大学名誉教授。1985(昭和60)から1年間、中国南開大学大学院招聘教授(日本語学)。現場教師の方々と毎月勉強会の継続
権藤順子[ゴンドウジュンコ]
長崎大学教育学部卒業、小学校教諭、教育センター研修員、附属小教頭を経て、現在、川上小校長。『小学校作文の単元―個人文集への誘い』のワークシート作成時から作文教育研究会会員、佐賀童話仲間の会「ブランコ」会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
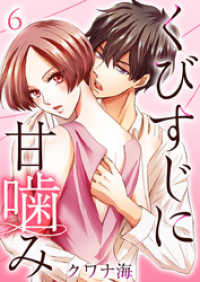
- 電子書籍
- くびすじに甘噛み 6巻 ティアード