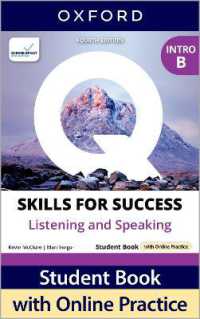内容説明
保高徳蔵の熱意によって、多くの作家を輩出し、文壇を支えた雑誌の全貌に迫る。
目次
『文藝首都』―文壇を支えた同人誌
第1部 文壇への期待/文壇からの期待(文学懸賞が生んだ同人誌―『改造』懸賞創作と『文藝首都』の関わり;『文藝首都』の“批評”のモード―保高徳蔵・青野季吉を軸として;「素朴な、人間本然の心」を詠う―“林芙美子”の文壇における生存戦略;大原富枝「女流作家」への道―『文藝首都』から「婉という女」へ;作家が語る・作家に聞く1 勝目梓)
第2部 居場所のきしみ(金史良の日本語文学が生成された場所としての『文藝首都』―「土城廊」の改作過程を中心に;台湾植民地作家龍瑛宗の『文藝首都』を通じたアジア作家との交流;実作者ナカガミケンジの覚悟―『さんでージャーナル』と『文藝首都』を中心として;作家が語る・作家に聞く2 紀和鏡)
第3部 労働とペンの力学(「沃土」とは別の仕方で語ること―『文藝首都』における和田伝;「あけくれ」から「峠」「糸の流れ」へ―『文藝首都』のなかの早船ちよ;国鉄勤労詩論争の周辺―『文藝首都』と労働者;医師がペンを執るとき―なだいなだと宗谷真爾;作家が語る・作家に聞く3 飯田章)
第4部 例外状況を生き抜く(上田広「黄塵」と文学の“大衆性”への欲望―『文藝首都』から『大陸』への転載をめぐる問題系;「創作指導雑誌」という姿勢―戦時下における『文藝首都』の位置;金達寿「塵芥」におけるパラテクストの可能性;「小野京」としての林京子―『文藝首都』発表作品の位相;作家が語る・作家に聞く4 佐江衆一;『文藝首都』年表)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わい
1
図書館で「和田伝」で検索したら出てきて、「わ、和田伝て文芸首都だったのー!?」という驚きと共に予約。拾い読みしかしてないんだけれど、戦前の文芸首都に和田の写真が載ってたり、評論が載ってたりして感動しちゃった。私が「文芸首都」を知ったのは中上からで、そこから津島佑子とかを知る。「キューポラのある町」の作者が文芸首都だったのも、これで初めて知った。なだいなだの職業作家に関する話も面白い。しかし、そんな文芸首都が、主宰者夫妻の力で維持していたものだったとは…。私は主宰の名前も知らなかった。記録、だいじ。2021/08/30