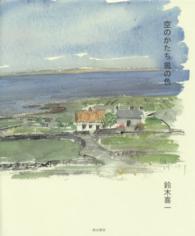目次
「鏡」という技術
第1部 表象の体系としてのアンソロジー(明治三五年版『透谷全集』―その「商品」性と流通ネットワーク;明治三〇年代後半、“文学”化されゆく手紙―「透谷子漫録摘集」を起点として;成型される透谷表象―明治後期、“ヱルテリズム”の編成とその磁場;透谷を“想起”するということ―昭和二年、『現代日本文学全集』刊行をめぐって)
第2部 日本浪曼派と“透谷”(中河與一の“初期偶然論”における必然論的側面―小説「数式の這入つた恋愛詩」の分析を通して;戦時下日本浪曼派言説の横顔―中河與一の“永遠思想”、変奏される“リアリズム”;彷徨える“青年”的身体とロゴス―三木清“ヒューマニズム論”における伝統と近代;“偉大な敗北”の系譜―透谷・藤村・保田與重郎)
著者等紹介
黒田俊太郎[クロダシュンタロウ]
昭和53(1978)年生まれ。京都府出身。慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、鳴門教育大学大学院・准教授。日本近代文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件