内容説明
新劇がもっとも新劇らしく輝いた1930年代に活躍した代表的な劇作家たちは、その劇作の基本としてのドラマトゥルギーを、吹き荒れる転向問題に直面しつつどこまで必然性をもって考え抜いたか。転向が表徴する現実軸と、ドラマトゥルギーの歴史軸が交叉する時代を現代にあらためて問う。
目次
一九三〇年代展望
村山知義―その創作方法
久板栄二郎―ドラマの「中」について
真船豊―徒歩でたどる
山本有三―筋・ものがたり
久保栄(『火山灰地』二部作;描ききれなかったこと)
三好十郎(ドラマの「終わり」;転向とドラマトゥルギー)
飯沢匡―喜劇の姿勢
森本薫―日本文学報国会委嘱作
木下順二、加藤道夫―出口を求めて
著者等紹介
宮岸泰治[ミヤギシヤスハル]
1929年生まれ。演劇評論家
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のほほんなかえるさん
0
1930年代の劇作家たちの苦悩がわかる。2010/12/29
mstr_kk
0
筆者は、葛藤・対立と必然的な劇的行為によって構成される西洋的なドラマの基準から見て、日本の1930年代新劇の戯曲のほとんどにはドラマが欠如していると主張します。ではなぜ欠如しているのか。非転向者は、「死守すべき抵抗の一線」をもたなかったから、葛藤と変化のあるドラマを書けなかった、ということでしょう。しかし村山知義のような転向者は? 結局、日本には西洋的ドラマが根づいていない、というだけかもしれません。そうとう昔気質の左翼の筆による論だと感じましたが、しかし、迫力はあります。2022/11/05


![いぬいさえこ きみのことがだいすきカレンダー 卓上 〈2026〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47562/4756260470.jpg)


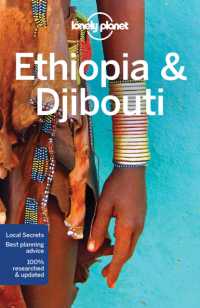
![ホースマンカレンダー 〈2009年〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48790/4879000108.jpg)


