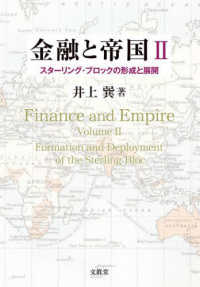内容説明
ビザンツ帝国は、「文明の十字路」コンスタンティノープルを帝都に、約千年にわたる長いあいだに徐々に独自の文明を形成してきた。専制皇帝の絶大な権力、宦官の活躍で整備された官僚制、戦いに明け暮れながらも必要悪としか考えない戦争観―ここには、古代ギリシア・ローマの都市文明を継承しつつも、明らかに異なった文明への変容がみられる。この過程を、社会構造と人間類型の転換として描く。
目次
世界史のなかのビザンツ文明
第1部 都市の変貌―ギリシア・ローマ文明からビザンツ文明へ(ローマ都市とビザンツ都市;都市自治の終焉;「パンとサーカス」のゆくえ;都市からみたビザンツ文明の起源と特徴)
第2部 皇帝・宦官・戦争―ビザンツ文明の諸相(皇帝―「神の代理人」;宦官―「皇帝の奴隷」;戦争―必要悪)
ビザンツ文明と現代
著者等紹介
井上浩一[イノウエコウイチ]
大阪市立大学大学院文学研究科教授。専門は西洋史。1947年、京都市出身。71年、京都大学文学部卒業。76年、同大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。大阪市立大学文学部助手・講師・助教授を経て、現職。ビザンツ帝国の政治と社会を研究し、皇帝・貴族から農民・市民にいたる諸階層が織りなす歴史の解明をめざしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
7
若い頃は文明論なんか面映いと思っていたけど、年を取ったらどうにか書けるようになりました、という著者あとがきの述懐が味わい深い。都市文明・皇帝・宦官・戦争を切り口に、ビザンツを一つの文明として俎上に載せるダイナミックな試み。終章の環境問題云々は筆が滑った気がしないでもないが、ビザンツ流「消極的平和主義」の方は考えさせられる内容だった。2022/12/27
Mana
3
著者はアンナ・コムニナの伝記を書いた人で、ジョナサン・ハリスの翻訳もしてる。ビザンツ帝国について色々本出してる専門家の人。この本はビザンツ帝国を歴史の流れではなく、色々なキーワードで切り出して分析していて、正直まだビザンツ帝国の歴史がきちんと頭に入っていない状態だと分かりにくかった。西欧のビザンツコンプレックスの話は面白かった。2020/08/04
MUNEKAZ
3
ビザンツ帝国のことをもうちょっと知りたくなったので、読んでみた一冊。ローマ帝国を親文明とするビザンツ帝国が、その親から受け継いだものを化石化、儀式化して独自の文化に変容させていく姿は大変興味深かった。キリスト教や戦争感についても、同じローマ帝国を親とする双子文明である西欧文明と対比させることで、その独自性が良く分かった。2016/02/25
壱萬参仟縁
3
A.J.トインビー『歴史の研究』を紐解きながら、東ローマ帝国が約1千年に及んで継続した秘密とは? と思いながら読んだ。皇帝の権力や、官僚制が強固なこと。宦官というと、中国史でも出てくる(隋まで去勢は死刑に次ぐ重刑)が、ビザンツ帝国では、高級官僚は特権階級だが「皇帝の奴隷」(p.207)だというので、現代日本と比較すると? とも思った。天下りがあるために、特権は特権だと思える。東西南北の文物の交流地点であったという、地政学的な場も影響していると思う。2012/06/07
denken
3
こういう外交は中国史でよく出てくるな,とか。自分とこが唯一の文明世界で,他は野蛮だという発想なら,そういう外交になるもんなのかな。皇帝の奴隷と言えば,オスマン帝国を思い出したり。でもビザンツ皇帝とオスマンのスルタンは違うんだなあと,気づいたり。自治都市が直轄都市に移りゆく様には,おおうっ,と感じ入ったり。まったく別の本で覚えた「劇場国家」という概念を使うなら,日本にとっての唐のように,日本にとっての西洋のように,ローマにとってのローマは,政治力の源泉なのだろうなあ。2011/12/08