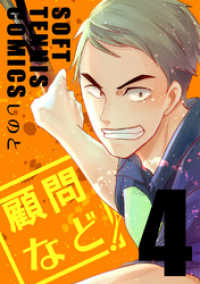目次
第1部 近代化学の完成へ(近代化学への道―18世紀までの化学:原子・分子の科学の曙;近代化学の発展―19世紀の化学:原子・分子の概念の確立と専門の分化)
第2部 現代化学の誕生とその発展(19世紀末から20世紀初期の物理学の革命―X線、放射線、電子の発見と量子論;20世紀前半の化学―原子・分子の科学の成熟と拡大)
第3部 現代の化学(20世紀後半の化学(1)―分子の観測・分析と創製における進歩
20世紀後半の化学(2)―分子に基づく生命現象の理解
20世紀の化学とこれから)
著者等紹介
廣田襄[ヒロタノボル]
京都大学名誉教授。専門:化学(物理化学)。1959年京都大学理学部卒/1963年米国ワシントン大学大学院(博士課程)修了、Ph.D./1963年米国シカゴ大学フェルミ研究所研究員/1965年米国ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校助教授/1967年同準教授/1970年同教授/1975年京都大学理学部教授/1993年京都大学評議員(1995年まで)/2000年京都大学定年退職。京都大学名誉教授/2000年宇宙開発事業団招聘研究員(非常勤)/2003年宇宙航空研究開発研究機構参事(非常勤)(2005年まで)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たかまる
5
ただ純粋に知りたい、より合理的に理解したいという思いが基礎科学の発展を支えてきたのだと改めて思いました。高校化学で学んだ周期表や原子価というアイデアも僅か百年前に作られたもの。分からないものを追い求める気持ちを人間から取り除くことはできない、そうこの本は物語っています。2014/04/11
minochan
2
最新の知見だけ知っても、それを使えるだけ。未来を自分がつくりたいと思うなら、現在のパラダイムに至る過去の流れをよく知っておくべきかなと思うこのごろ2023/08/27
takao
1
ふむ2025/10/11
minochan
1
何度読んでも良い 博士論文のgeneral introduction執筆のため再読2024/12/31
U-tan
1
著者は物理化学特に磁気共鳴,分光学,光化学が専門の研究者.引退後,化学の基礎としての物理,もっとも成功した応用先としての生物まで含めて,物理化学を中心に記述している.僕は(もしかしたら著者も多くの部分で)門外漢なのだけれど,良書なのだと思う. 20 世紀後半以降の理論化学・計算化学・化学反応の動力学研究につき詳細に五倍くらい長さをとって書いてほしかった.ただし現代なので読むべき文献で思い当たるものが多いので自分で読めばよい.2015/12/04