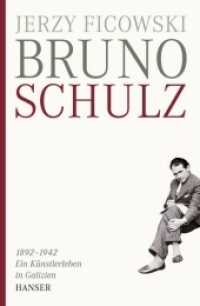内容説明
哲学を学ぶのにどうして哲学史を学ぶのか?現在における問題を考えるだけではどうしてだめなのか?本書は、この素朴な疑問に正面から立ち向かい、哲学史を学ぶ意義を改めて考える。
目次
第1部 哲学史への問い(哲学史と教養―古典を読むこと;最近の二つの哲学史観―問題史と発展史について)
第2部 知にとって歴史とは(歴史と哲学;懐疑論についての歴史的考察―「ものごとを疑う」あるいは「知っている」ということ)
第3部 哲学の古典をどのように読むか(必然性と自由の問題―ライプニッツと共に考える;非物質論とはどのような考え方か―バークリ哲学から見出される多様な意義;超越論哲学の歴史的背景―カントとスピノザ主義)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
masabi
12
【概要】哲学史を学ぶ意義に関連した論考。【感想】歴史を学ぶ意義として先達の犯したミスを避けるという消極的な理由の他に現代と古典の書かれた時代の隔たりを埋めるために自己変革の契機とする積極的な理由が説かれる。ガーダマーの古典論、教養論と併せて展開される。隔たりは歴史的状況や個人の状況でまた変化するので自分がその都度古典を参照する。2022/03/03
文狸
2
実はこれ、一回生のときに受けていた一般教養の授業の先生の本である。その人がおもしろくて買ったのだが、当時は知識がなくて全く歯が立たず、積読になっていたのを5年越しに読んだ(わりあい理解できて嬉しかった)。特に第一章において、一般教養における哲学教育についての著者の危機意識がよく伝わってきた。2020/06/25
水無月十六(ニール・フィレル)
1
大学でのレポート課題として読書。タイトルの問いに関して、スピノザやライプニッツ、デカルトなどの解説を踏まえながら論じたものがまとめられた本。レポート課題を意識して読んだのできちんと読み切れていないところがある。再読対象。2014/07/14
ミツキ
1
自らの思索を、連綿と続く哲学の歴史のなかに置き、かつての哲学者の思索を汲み取りつつ、これからの歴史にその思索を遺すのであれば哲学史を学ぶことは作法として不可欠である。そういう営みを「哲学」と呼んでいるのだと私は解釈した。我思索する以前に哲学あり、と捉えるならばそうだろう。「哲学」への違和感はおそらくここから来る。私の哲学はそうでない。「哲学」の前に私の思索がある。私は「哲学」をやりたいのではなく、哲学でやりたいのである。哲学史に連なることが目的ではない。2014/04/15
里のフクロウ
0
「哲学する」とは「どうする」ことなのかという私の長年の妄想的疑問に答えを含んでいないかと期待しての本でした。直接的な答えはありませんでしたが、古典に接する心構えについて貴重な示唆がありました。曰く、「テキストをできるだけ好意的かつ整合的」に読むというものです。複数の対立思想に対して、それぞれの立場に理解を示し、それを整合する第3の思想を打ち出す「構え」は現代に通じる重要な構えであるというもの。哲学がちょっと読みやすくなったように感じた。2014/02/01
-
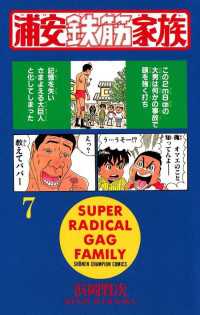
- 電子書籍
- 浦安鉄筋家族(7) 週刊少年チャンピオン