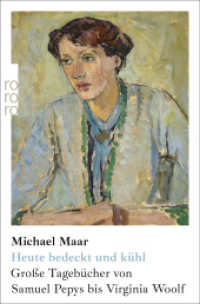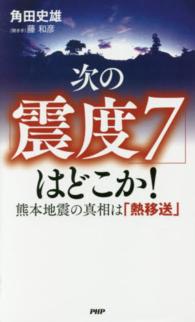内容説明
エントロピー、非可逆性、進化、目的性、…現代科学が語りえていない課題を、ベルクソンはどのように論じたのか。
目次
第1章 持続概念の形成と連続性の問題
第2章 力・エネルギー概念と決定論の問題
第3章 神経系(ニューロン)概念と心身問題
第4章 エントロピー概念と非可逆性(時の矢)の問題
第5章 偶然性概念と階層の問題
第6章 目的性概念と生物進化(器官の構造と機能)の問題
第7章 時空の概念と宇宙論(コスモロジー)の問題
著者等紹介
三宅岳史[ミヤケタケシ]
1972年岡山県生まれ、2004年京都大学大学院博士後期課程思想文化学専攻哲学専修研究指導認定退学、2007年博士(文学)取得(京都大学)。現在、香川大学アーツ・サイエンス研究院(教育学部人間発達環境課程主担当)准教授。専門は、フランス哲学、エピステモロジー(科学認識論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヘンリー八世が馬上試合で死んだことは内緒
1
科学体系にドン・キホーテのように自らの哲学を適応するベルクソン。その世界観はまどマギのようだ。微小な非決定性が神経系により増幅され、宇宙には生命により秩序が上昇する領域と下降する領域とがある。科学的知見により哲学世界を作り出す様はまさにSFだ。2016/09/28
雁林院溟齋居士(雁林)
0
大変素晴らしい研究書。ベルクソン哲学と当時の科学の間の関係に焦点を充てているのだが、前半は力動論と機械論の対決の中で力の問題や測定不可能なエネルギーを巡る彼の立ち位置、中盤は偶然性と目的性という二つの指標における様相の問題が俎上に上がる。最後の第七章は、『持続と同時性』を中心に時空とコスモロジーの章を論じており、ブシネスクの微分方程式による決定論と自由の調和を論じた第三章と並び出色であると感じた。又、彼は規約主義に矢張り親和的で、デュエムやポアンアレを特に科学に関する議論の下敷きにしていると分かる。2013/01/12
ハンギ
0
ベルクソンは哲学者なので、科学は素人のはず。そんな彼が独学の果てにアインシュタインと対話するというのが筋道。ベルクソンに影響を与えた人はデュエム、ポアンカレを特に挙げている。本質的にベルクソンの科学理解はアナクロだけど、その情熱は買いたいし、勉強になりそうな気がした。今更だけど、生命の哲学なんだなあ、と実感した、が目的論的理解は今ではどうなのでしょうね。ベルクソンは揺れている気も。。この時代は連続性というのがキータームになっていた事は初めて知った。いろいろ教えてもらった気がするが、手堅い本ですね。2012/10/31
-

- 電子書籍
- 異世界商人 スキル<異世界渡航>を駆使…
-

- 洋書電子書籍
- ラウトレッジ版 海洋資源管理ハンドブッ…