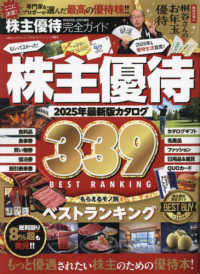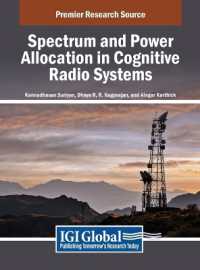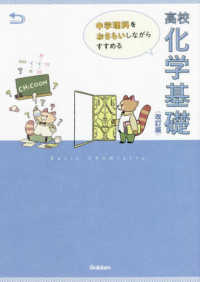内容説明
前411年から前362年までのギリシア史(原題は『ヘレニカ』)。トゥキュディデスが筆をおいたペロポネソス戦争末期から語り始め、コリントス戦争、「大王の平和」を経て、テバイ軍がラケダイモン・アテナイ等の連合軍と対抗した「マンティネイアの戦い」に至るまでが語られている。哲学者でもある著者の筆は、戦争の経緯のみならず、諸ポリスの内部事情や将軍たちの利害までも如実に描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
10
大晦日に読み始めて元旦に読み終わった今年の一冊目冒頭、イキナリ「その後幾日も経たぬうちにアテナイからテュモカレスが僅かな艦船を率いてやってきた」と言う記事から始まるのですが、その後って何の後?テュモカレスって誰?どこにやってきたの?と言う感じで、何の話かさっぱり分からない。やっとアテネとスパルタの相克に時々、ペルシャが絡むんだな、と分かり初めたものの、地図を見ながらお話を追っかけるのが大変。追っかけきれないところも一杯あるけれど、とにかく必死に追いすがる感じでした。2025/01/01
みのくま
5
奇想天外なヘロドトス、緊迫感漂うトゥキュディデスと比較すると、本書はかなり見劣りする。文章表現全般が平板で、ヘロドトスやトゥキュディデスにあったポリフォニーはない。著者クセノポンの声しか聞こえないのだ。ただこの二者とは違い、クセノポンが描いた時代は分かりやすく痛快な戦争ではなく、アテネの敗退と内紛、そしてペルシア王の支援を取り付ける事にあくせくするポリス国家群の行状を描いているため、比較するのは酷なのかもしれない。しかし、それならば著者自身のもどかしさや怒りのようなものが行間から読み取れたらいいのにと思う2023/11/19
roughfractus02
5
トゥキュディデス『歴史』続編として読むと、傭兵としてスパルタ側で戦った著者の記述に偏りがあると指摘される(確かにクラティッポス、テオポンポスと比較するといつくかの出来事が欠落しているという)。が、テバイによるスパルタの衰退を目にした著者が諸ポリス全体のシステム変容を記したと捉えると、民主制のアテナイから独裁的な僭主政治が出現する過程が見えるようだ。第4巻までを収録した本巻はペロポネソス戦争からコリントス戦争までを主に謀略や戦術面から記述する。今回は著者が思いを馳せるかつてのスパルタ体制の崩壊を念頭に読む。2022/06/24
ヴィクトリー
3
トゥキュディデスが物凄く中途半端なところで未完に終っているので続きとして読む。「アナバシス」に出て来る人も居て、あの話が歴史のどの辺りに位置するのかが実感として分かってちょっと嬉しい。ただ、簡潔と言うか素っ気ないと言うか、時々分かりにくいところがあるせいか、トゥキュディデスよりは面白くない気がする。あと、アゲシラオスかっこ良過ぎ。2013/01/20
ハルバル
2
トゥキディデス「戦史」で書かれなかった部分の補完的なペロポネソス戦争末期の記述からアテナイの内乱、コリントス戦争途中まで。 淡々とした記述が続き、資料的価値は高いものの読んで面白いものではない。地図がないのも困った。 クセノポンも「アナバシス」後にアゲシラオス軍に編入され共に戦っているはずなのに、なんなんだこの生彩の無さは?(基本的に小競り合いが多いせいなのか…)トゥキディデスのような深い考察や巨視的視線はないものの、当時のギリシャ世界の動向を知りたいなら必須の書2015/08/07