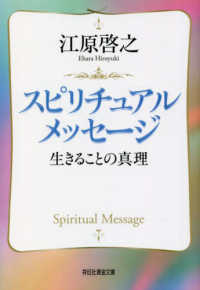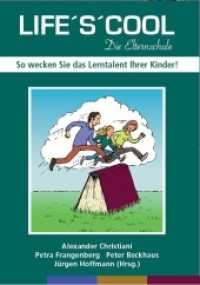内容説明
「図書館の自由」は難しい、でも面白い!
目次
第1部 沖縄ノート(こんな本を授業で紹介していいのでしょうか?―自殺マニュアル本をめぐって;沖縄の高校生が『図書館戦争』を読んだら ほか)
第2部 自由ノー1 利用者の秘密を守る(本を借りたら一ポイント?―量目的化する読書指導;バラエティ番組と「図書館の自由」―プライバシー・レコメンド、怒り心頭? ほか)
第3部 自由ノート2 資料収集・提供の自由を有する(領土と歴史、国家と個人―『国旗のえほん』と『20年間の水曜日』の共通点;ホテルに聖書がある理由―学校図書館に『はだしのゲン』しかない理由 ほか)
第4部 読書ノート(図書館と貧困―「陽だまりここよ」・ホーレス・ワーキングプア;全国OPAC分布考―オーパックなのか?オパックなのか? ほか)
著者等紹介
山口真也[ヤマグチシンヤ]
1974年、鹿児島県生まれ。1998年3月、図書館情報大学大学院修士課程図書館情報学研究科修了。1998年4月、東京家政学院筑波女子大学図書館司書(1999年3月まで)。1999年4月、沖縄国際大学専任講師、2003年4月、同大学助教授、2007年4月、同大学准教授、2013年4月、同大学教授。2014年度より日本図書館協会図書館の自由委員会委員を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナディ
33
『沖縄から「図書館の自由」を考える』という副題のつくエッセイ。確かに沖縄の抱える問題も採り上げているが、それだけではない。報道の自由、知る権利なども考えさせられた。少年による残酷な犯罪が起きた時の世間の反応なども思い出した。映画などの年齢制限などが一気に始まり、世界が変わっていく気がした。そんなことも思い出された。実はもう図書館戦争をフィクションだと思える時代はとっくに終わっているのかもしれない。2017/01/15
キビ
22
貸していただいた本。「図書館戦争」についての記述が気になり読んでみた。司書を目指す学生の考えを知るための課題本にしているそうだ。…なるほどね。図書館って身近にあって、私はとても好きな場所。図書館は、それぞれに違いがあって面白い場所。学校の図書館や地域の図書館には「えー⁈」と思う古い本が残されていることも多々ある。普段、図書館に行く際に、中立性とか図書館の自由とか難しい事を考えてはいないけど、社会人としてたまには考えてみることも必要なのかも…と思った。2018/06/17
ruki5894
11
沖縄の高校生が『図書館戦争』を読んだ感想文が面白い。自由宣言の中の我々って誰?「我々」の中に「図書館員以外の一市民」が含まれるという解釈には、心が動いた。「バトル・ロワイヤル」をリクエストすることにSOSを感じ取る学校図書館司書。マンガの中の図書館『陽だまりここよ』opacの読み方について。検索できない大学生の変なキーワード。考えさせられものもあり、クスッと笑える話ありで面白かった。2018/02/07
charmy hitomi
6
もしまだこの本を読んでいない司書がいるのなら、何の躊躇なくどうぞ読んでください!1エピソードにつき1研修会(または2研修会)に参加するくらいの価値があると断言いたします。そしてこれがまた全く堅苦しくなく、図書館員以外の人が読んでもおそらく興味深く読める内容なので不思議です。山口さんの人柄なのでしょう。意見に偏りがなく、的を得ていて、今後もストークしていきたいです!2018/12/20
くにお
6
沖縄の大学に努める図書館情報学者の連載コラム。話題は多岐にわたるが図書館の資料収集と開架にまつわる「自由」に関する問題が主軸。図書館における自由とは、公平とは何か。実際にニュースにもなったような図書館にまつわる出来事からこの奥深い問題を考える。容易に結論に持っていかず、オープンなまま問いの深みを残す著者の姿勢に好感。「読書冊数」の評価化や基地・沖縄戦に関する図書など沖縄特有の問題も豊富で面白い。最後はわりとどうでもいい軽いエッセイ集で閉じられており(OPACの読み方問題は笑えた)爽やかな(?)読後感。2018/01/04