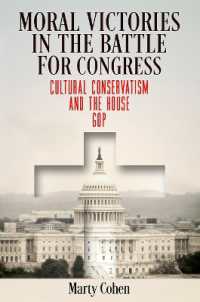目次
第1章 中国学の通り道
第2章 中国学―老いの細道
第3章 中国学の寄り道
第4章 中国学の曲り道
第5章 中国学の畦道
第6章 中国学の離れ道
第7章 中国学―易への近道
第8章 中国学の横道―詩才なき者の独語
第9章 中国学の野道(講演)
著者等紹介
加地伸行[カジノブユキ]
昭和11年(1936年)大阪市生まれ、愛媛県出身。京都大学文学部卒業(支那哲学史専攻)。高野山大学、名古屋大学、大阪大学、同志社大学を歴任し、現在、大阪大学名誉教授、立命館大学フェロー。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひよピパパ
13
儒教の宗教性に着目した論考でも知られる加地氏が、これまで各方面で述べたり記したりされたものを一書にしたもの。中国学、とりわけ儒教や儒教経典を基軸にしながら、文字学や軍学、健康学や詩学など、様々な領域の話題そして魅力が豊富に詰まっている。最終章の「中国学の過去・現在・未来」では、哲学を旨とする東大と、哲学史を主軸に据えた京大の学問の性格の違いがよくわかった。中国学に関わりをもつ人たちへのエールの書ともなっている。2023/12/30
ふみ乃や文屋
1
中国をめぐる小文集。第三章一節の「必ず原典を見る」というのは、当たり前のことのようで意外とできていない人が多い気がする。私には耳の痛い話でした。とはいえ、そういう小難しい話ばかりではなく、とっつきやすい話もあるので好きなところをつまみ読みしてもいいかも。2016/03/02
さとうしん
1
加地氏の学術エッセーというか雑文集。個人的に考えさせられたのは、伝世文献での『詩経』の引用は、特定の詩篇や詩句に限られているのではないかとする第三章の「『詩経』からの引用」と、現代中国語の発音で漢詩や漢文を音読することの非を説く第八章の「漢詩指導についての覚書」。第九章の講演録では、中国学が資料の調査と分析を重視する分野であると説くが、別の言い方をすると、「ブラック体制」が養われる分野ということになるだろうか。2015/12/11