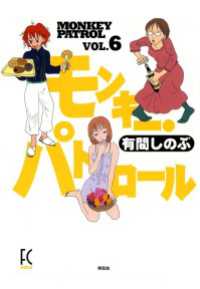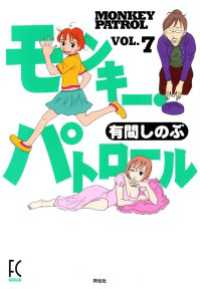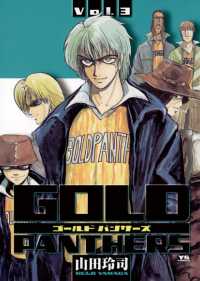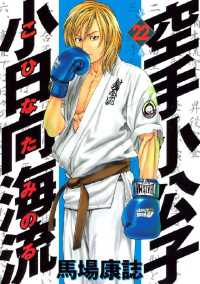内容説明
あやしい「食育」が多すぎる!「旬」だからおいしい?「日本型食生活」だから健康?「食卓の団らん」が日本の伝統?―教育現場にしのびこむ怪しい「和食」賛美を、膨大な文献資料をもとに検証。痛快な近代日本食文化史!
目次
第1章 “生きのびる”ための食育(食費ひと月九〇〇〇円の真実;食生活の「欧米型」と「日本型」 ほか)
第2章 “体にいい”を科学する食育(米食礼賛に待った!;食中毒で死なない、打たれ強い食べ方 ほか)
第3章 “伝統”のウソをつたえる食育(「昔は○○だった」を鑑識する;鯨食は伝統食なのか? ほか)
第4章 “旬”と“鮮度”を考える食育(「旬のもの」食育の大勘違い;保存食の食育 ほか)
第5章 “食べる”を考える食育(食の支えあいを学ぶ;お手軽食と危険ドラッグに関する食育 ほか)
著者等紹介
魚柄仁之助[ウオツカジンノスケ]
1956年、福岡県生まれ。食文化研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
11
図書館にて。社会学風味の表紙だが、著者が魚柄氏のなので、いつもの食エッセイであった。雑誌掲載の連載エッセイをまとめたもんだと思うが、初出なし(注や参考文献もなし)。牛乳を扱った章によると、牛乳の冷蔵輸送体制ができる前には山羊の乳を使ってたところもあると知った。小学校の山羊飼いはその名残りなのかもしれない。あと、アニメ『ハイジ』では山羊の乳を搾ってたっけ…2024/11/01
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
6
1990年代のブレイクからずっと活動してるのだから、需要はそれなりにあるのでしょう。久々に読んだら至極まっとうなことばかり。わかめ洗ってその塩を使え、なんて極端なことは書いてない。衝撃だったのは「アメリカにおける稲作の始まり秘話」というとこで、紅茶やらスパイスやら西側が力にものを言わせ食材を世界中で漁って食い尽くすって図式にうんざり。地産地消ですら贅沢。あるものをいかに食べれるようにするか、ってことにつきるようです。他レビューで文体に不快感を示されている方が多いのは意外でした。2019/06/21
Sumiyuki
5
調理技術。5回作る。日本食の特徴は鮮度が落ちても味の密度が上がる食べ方。伝聞ではなく根拠が大事。昆布締め、塩蔵、乾物活用。腐るのは細菌のせい。75℃で死滅。強火で温めても、じゃがいもの中心は60℃にしかならない。弱火でじっくり温める。薄味と咀嚼。筍真薯。トロが嫌われたのは、腐りやすかったから。米が食べられなかったからコナモン文化が発達。明治維新後も日本人全員が牛肉を食べられるようになったわけではない。牛の餌は輸入品。2018/12/06
ganesha
4
「伝統」や「昔ながらの」という言葉に惑わされずに、正しい知識を持って食べられるようにという一冊。文体になじめずに斜め読みしたが、よく噛んで食べることを心がけたいと思う。2021/01/28
Kuma
3
添加物、原産地などを気にして国産、有機、無添加無漂白の食材を使いこなせないのに買って廃棄させるより、安くても使いこなして食べ続けることが大切。 筆者特有の口語が不快。〜でしょか、ありまっせんとか。バッタを倒しにアフリカへのMr.前野の口調はすごく好きだったのに合う合わないってあるんだなと。2019/02/01