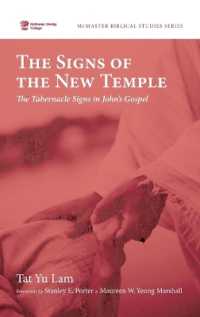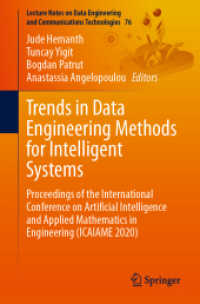内容説明
トヨタ生産システム(TPS)で、私たちはどのように働かされるのか。「ムダ」排除が社会に広がることの意味を、現場から問う。
目次
序章 先行研究の整理と本研究の課題
第1章 実践
第2章 トヨタ本体におけるTPSの開発―解体と「再生」
第3章 一次下請企業の定着活動―強要と教育
第4章 二次下請企業への導入事例―格差と包摂
第5章 「進化」―管理・協力体制の完成と「独り立ち」
第6章 地域社会への広がり―新自由主義時代のカイゼン
第7章 TPSの限界を乗り越える
終章 TPSを読み替えて、“無理のない社会”を展望する
著者等紹介
伊原亮司[イハラリョウジ]
1972年生まれ。一橋大学商学部卒業。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了、社会学博士(2004年)。現在、岐阜大学地域科学部准教授。専攻、労働社会学、経営管理論、現代社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tkokon
3
【不賛成】Can't disagree moreな主張。TPSは現場に負担を強いる、やっても必ずしも経営は良くならない、工夫を続けないとやがて行き詰まる、だからTPSは高く評価できないという主張。TPSをやめて販売や開発に注力して復活した会社の話が出てくるが、TPSはマーケティングや開発の代わりになるわけがない。TPSに取り組む社員の「満足度」を論じているがTPSをやっていない同規模製造業と比べてどうなのか?「TPSは万能ではないからダメ」という主張に見え、説得力がない。TPSは酒井崇男の著作がオススメ。2018/01/07
ksmh
0
トヨタ生産方式(TPS)の生まれや広がった背景、それによる影響を考察し、それらを踏まえた提案を示す本。 自社への徹底はもちろん、取引先や市場のコントロールが効かなければTPSの実現は難しく、導入半ばで折れた事例はたくさんある。もちろん、導入できた事例もあるが、現場への強制・衝突は免れない。そのため、目先の利益を追求するのではなく、今現在抱えている「ムダ」をどこまで抱えるかを明確にし無理をしない方が長続きするのではないか、という主張。地域社会まで言及してTPSの問題点を述べる論調が新鮮だった。2024/02/21
kaz67956370
0
カイゼンの良さをリアルな名前、数字を含んでみれるのに加え、カイゼン等の弊害も載っており、この現実を知れたことに感謝します2021/03/31
-
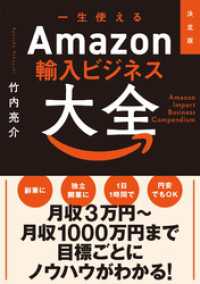
- 電子書籍
- 決定版 一生使えるAmazon輸入ビジ…
-
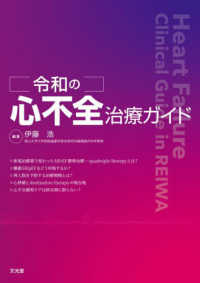
- 和書
- 令和の心不全治療ガイド