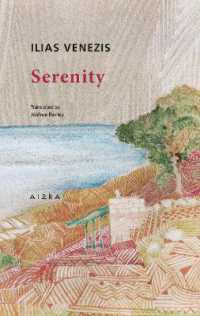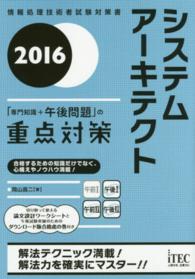内容説明
会津藩の教育の出発点とは何か。「藩士の制度という人間秩序をみがきあげたその光沢の美しさにいたってはどの藩も会津におよばず…芸術品とすらおもえる」と司馬遼太郎は絶賛し「最高の傑作」と位置付けた。しかしそれが皮肉にも会津藩の悲劇の原因(戊辰戦争)となった。旧会津藩士たちは苦難の戦後、どのような人生を歩んだか…多くは教育者となった。高等師範学校の校長に、東京帝国大学総長に、同志社の創設にと奔走した。「フクシマ」の再興のみならず日本の未来のために、自立した人間の育成をめざした彼らの教育への情熱と取り組みを、今日、学ぶ必要があるのではないだろうか。
目次
会津の教育のはじまり
蒲生氏郷による若松の建設
徳川幕府と儒教教育
保科正之の政治と朱子学研究
藩校・日新館の誕生
会津の藤樹学
水戸藩の教育との比較
幕末における幕府の教育
京都守護職と幕末の日新館
戊辰戦争
明治維新
「学制」の制定―儒教は排除される
斗南藩と若松県の教育
明治を生きた旧会津藩士たち
明治を生きた旧会津藩士の子弟たち
キリスト教主義教育―山本覚馬と井深梶之助
フクシマの真の再生を願って
著者等紹介
荒川紘[アラカワヒロシ]
1940年、福島県に生まれる。東北大学理学部卒業、東洋大学、東京職業訓練短期大学校、静岡大学、愛知東邦大学に勤務、科学思想史専攻。静岡大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 洋書
- Serenity