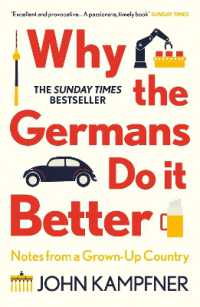出版社内容情報
最先端技術のナノテクノロジーを支えるナノサイエンスが,どのような経過を経て生まれてきたか.そもそも化学は,冶金,醸造,染色,薬品など生活に深く根づいて孵化し,19世紀以後,金属,食品,染料,繊維,製薬などの産業をささえる科学として発展し,それらがナノサイエンスへの道を用意したといえる.ナノテクノロジーは複合的,学際的である.その最も重要な点は,生命系技術の影響が色濃い点である.その過程をたどることは,科学・技術・社会(STS)の視点からナノの世界が開かれるまでのプロセスを眺めることでもある.
化学の世界が,工夫と創意に満ちた確かな目標をもった希望のあふれる分野であることを,後続の挑戦的研究者たちに切々と説き起こした力作.
序章
1章 有機化学の芽生えと実験化学教育の確立
2章 石炭の産業廃棄物から生まれた化学染料産業のシーズ
3章 原子をつなげて天然染料をつくる:アリザリンとインジゴの合成
4章 人類の科学・技術史上最大の成果:染料から始まった化学療法剤
5章 分子を数える:分子実在の証明
6章 マルサスの人口論から生まれたアンモニアの合成:化学理論と金属触媒の威力
7章 分子を表面に並べる:水や固体表面にできる単分子膜
8章 DDTが引き起こした農薬産業イノベーションとその影
9章 分子をつなげる:人工高分子の光と影
10章 分子を集める,組み立てる:分子集合体化学と超分子化学
11章 分子を視る,操る:走査型顕微鏡の登場
12章 ナノテクノロジーブームの到来
13章 総括
あとがき
(「あとがき」から)ここ10年,科学・技術の急速な進化により市民と科学技術者のコミニュケーションを高めようとする試みや文理融合の新しい動きが現れてきた.例えば,相容れないと考えられてきた「テクノロジー」と「マネージメント」を融合させ,それらを学ぶことで事業や経営,技術の革新を推進できる人材の育成を目指すMOT(Management of Technology)も生まれ,経営系の学部や大学院でその重みが増しつつある.サイエンス・ショップの考え方も急速に日本にも拡がりつつある.これは産業科学とアカデミズム科学に独占されてきた研究・開発の資源を市民に開放しようとしたオランダの学生運動をルーツとし,市民社会から提示されるサイエンスについての疑問や不安に対して大学などの研究機関が研究・調査して答える市民参加型科学を目指している.
私(五島綾子)は長年,経営情報学部や教養課程で化学・技術をベースとした講義を行ってきたが,講義の度にそのむずかしさに直面してきた.私の経験上,学生の興味と問題意識を高めるためには,ある一つの化学・技術のテーマがどのように芽生え,展開したかを歴史的に追うことが有効ではないかという考えに至った.これが本書を書く最大の動機で
内容説明
ナノとは10-9mを意味するが、1mを地球の直径にまで拡大しても、1ナノはやっとビー玉の直径に相当する程度の、気の遠くなる小さな世界である。この最先端技術のナノテクノロジーを支えるナノサイエンスが、どのような経過を経て生まれてきたかを本書は明らかにする。
目次
有機化学の芽生えと実験化学教育の確立
石炭の産業廃棄物から生まれた化学染料産業のシーズ
原子をつなげて天然染料をつくる:アリザリンとインジゴの合成
人類の科学・技術市場最大の成果:染料から始まった化学療法剤
分子を数える:分子実在の証明
マルサスの人口論から生まれたアンモニアの合成:化学理論と金属触媒の威力
分子を表面に並べる:水や固体表面にできる単分子膜
DDTが引き起こした農薬産業イノベーションとその影
分子をつなげる:人工高分子の光と影
分子を集める、組み立てる:分子集合体化学と超分子化学
分子を視る、操る:走査型顕微鏡の登場
ナノテクノロジーブームの到来
総括
著者等紹介
五島綾子[ゴトウアヤコ]
静岡県立大学経営情報学部、同大学院経営情報学研究科教授。薬博・博士(理学)、ETH(スイス)客員教授(1994)、IUPAC Fellow(USA)(2002)、The Innovation Foundation Fellow(UK)(2001)
中垣正幸[ナカガキマサユキ]
京都大学名誉教授、東京帝国大学理学部化学科卒(1945)、理博、京都大学教授(1960)、日本薬学会学術賞受賞(1970)、日本膜学会会長(1978‐1988)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。