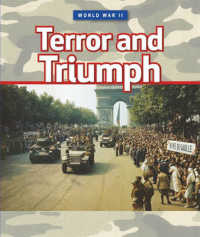出版社内容情報
目次
序 漁師はなぜ、海を向いて住むのか?
1 来訪神空間としての漁村
1-1 住宅と集落はどこからきたのか?
1-2 丹後・伊根浦の研究・序
1-3 漁村空間における漁港の役割
1-4 日本の沿岸地域における信仰と生活形態
1-5 漁村の人々はなぜ海を向いて住むのだろうか
2 しなやかな家族
2-1 輪島市・海士町の海女家族
2-2 漁村の生活と婦人労働の役割
2-3 漁村の生活と環境を考える
2-4 囲い込まれ、放り出される子どもたち
3 発見的方法
3-1 壮大なる野外講義:大島元町復興計画
3-2 発見的方法
3-3 逆格差論
3-4 沖縄振興のもう一つの視点
4 エトスの表現としての農村空間
4-1 エトスの表現としての農村空間──安佐町農協町民センター
4-2 山城を築きて国家と對決致し候──幻の蜂の巣城を復元する
4-3 環境と建築──他力本願の住宅づくり
4-4 草葺の家・私的体験から
4-5 棚田の米づくり体験から「水の社会資本素」を考える
4-6 日本はクラインドルフ政策を
4-7 吉阪研究室と中国研究
5 島と本土の防災地政学
5-1 三陸津波被害とその復興計画
5-2 天災は覚えていてもやってくる──淡路と奥尻と伊豆大島と
5-3 島と本土の防災地政学
5-4 しまなみ海道とポスト架橋の地政学
5-5 中山間地・水源地域と都市の共生
5-6 島―国土の〈入れ子〉構造と島嶼地政学の課題
6 人類の海への三度目の旅
6-1 拝啓 大前研一様「21世紀の海を拓くために」
6-2 人類の海への三度目の旅
付録 都市のORGANON──現代建築への告別の辞
解題 地井昭夫の漁村研究・漁村計画 幡谷純一
解説 地井昭夫の仕事=海村へのオマージュ 重村力
内容説明
高度成長の波にのって日本の都市空間が激変しつつあった一九六〇年代半ばより漁村に魅せられ、漁師や海女たちのダイナミックな暮らしぶりに共感を寄せた建築家・地井昭夫。海の彼方から訪れる神を迎えるための場所を中心とした街づくり、「核家族」や「プライバシー」といった枠にとらわれない集住スタイル、浜辺の環境保全や防災ネットワークとしても機能する自律システム…。丹念なフィールドワークにより経済至上主義とは一線を画すしなやかな生き方・住まい方の可能性を明らかにする。
目次
序 漁師はなぜ、海を向いて住むのか?
1 来訪神空間としての漁村
2 しなやかな家族
3 発見的方法
4 エトスの表現としての農村空間
5 島と本土の防災地政学
6 人類の海への三度目の旅
付録 都市のORGANON―現代建築への告別の辞
著者等紹介
地井昭夫[チイアキオ]
1940‐2006。北海道室蘭市生まれの漁村研究者、地域計画家、建築家。早稲田大学理工学部建築学科、大学院修士課程・博士課程に学び、建築家・吉阪隆正(1917‐80)に師事。大学院在学中に伊豆大島の元町復興計画を手がけ、「発見的方法」を主唱するとともに、舟小屋で名高い丹後伊根浦の漁村空間に魅せられ、漁村空間・社会の研究を開始。広島工業大学工学部建築学科(69‐82)、金沢大学教育学部(82‐91)、広島大学学校教育学部・同教育学部(91‐2004)、広島国際大学社会環境科学部(04‐06)などで建築学や住居学を教える(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Daimon
takao