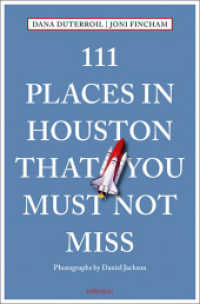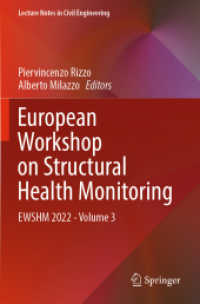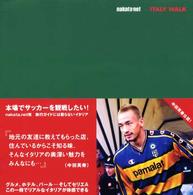出版社内容情報
天狗、数珠、刺青、身振り…。日本文化のさまざまな「かたち」を読んで見て楽しむ事典登場。金子務、小町谷朝生、水木しげる等総勢66名の執筆陣が、項目200余を読み解く。図版満載、1000点超!
■目次より…………………………
1―かたちのことば
1・000 形/ 形質
1・01 かたちの見取図
形体/ 形態◎表面◎
色/ 色彩/ 色彩論◎明暗/ かげ
硬軟◎感覚/ 知覚/ 認知
心象/ イメージ◎虚実◎構造
システム◎モデル◎系統
1・02 かたちと方法
構成/ 構築◎調和◎省略◎変換
翻訳/ 造語◎分類◎パラフレーズ
コラージュ◎作図/ 投影
設計◎遠近法◎プロポーション
自己組織化◎錯視/ だまし絵
装飾
1・03 世界をかたどる
宇宙/ 世界◎間/ 空間/ 時間◎場
次元◎無限◎縁起◎混沌/ 無秩序
人工/ 自然/ 天然◎天地
左右/ 上下/ 表裏
2―かたちのかたち
2・000 民族芸術学
2・01 天象と地象
星座◎天文学◎風◎雪◎雪形◎霞
火◎水◎流れ/ 蛇行◎渦/ 螺旋
花/ 桜◎富士山◎洲浜
2・02 物怪と異界
妖怪◎天狗◎鬼◎龍◎地獄/ 極楽
2・03 道具と暮らし
風呂敷◎旗/ 幟◎火消◎武器
数珠◎てまり◎折り紙◎水引
しめ縄/ 御幣◎千木/ 鰹木◎凧
ものさし◎文房四宝◎和紙◎螺子
車◎橋◎家◎柱◎庭/ 借景
垣/ 生垣◎墓石
2・04 遊芸と芸道
能◎文楽◎歌舞伎◎香道
喫茶◎茶道◎剣道◎囲碁/ 定石
2・05 文字と数と謎
漢字◎書/ 書体◎書道史◎花押
数/ 数字◎和算◎算額
パズル/ 考え物◎魔方陣
継子立◎タングラム
2・06 図形と象徴
点/ 線/ 面/ 立体◎円◎三角形
方形◎菱形◎五角形◎六角形
八角形◎フラクタル◎多義図形
充填
2・07 記号と文様
陰陽◎+と×◎巴/ 卍◎星/ 九字
青銅器文様◎銅鐸文様◎石垣刻印
寺院刻印◎呪符瓦◎鹿子
唐草/ 唐花◎吉祥文◎香之図
島/ 縞◎○△□
2・08 メディアと様式
仏画◎屏風絵◎絵巻◎浮世絵
本◎絵本◎看板◎暦◎地図
唐様/ 唐物◎キリシタン
阿蘭陀好み◎象篏◎俗悪趣味
朦朧体◎縮み志向◎流行
2・09 からだと衣装
頸◎耳◎舌◎腕◎指◎腹◎脚
刺青◎衣装◎袖◎裾◎衿
被り物◎下駄
3―ひととかたち
3・000 身振り
あそぶ◎あるく◎いのる
いわう◎うつす◎えがく
おどる/ おどけ/ まう◎かく
かこむ◎かさねる◎かざる
かなでる◎からす/ かれる◎きく
きる◎くむ◎けす◎けず(づ)る
ころす◎さとる◎すかす◎すく
すてる◎する◎すわる◎たたかう
たたく◎たつ◎ちぎる◎つっこむ
つなぐ◎つむ◎とく◎とぶ◎なく
なぞる/ なぞらえる◎ぬく
ねじる◎のろう◎ひく◎ふく
ぼかす◎まく◎まぜる◎まとう
みる◎もやす◎やく◎やぶる
やる◎わく◎わたる
わらう◎わる
■内容より…………………………
◎理解できない言葉をありがたいと思うのは、「意味」とは別に価値が生まれているからである。
◎日本人は、3 次元空間に住んでいることを、明治維新まで気づかなかった。
◎四畳半にも、左勝手と右勝手がある。
◎シデあるいは御幣は、天の声としての雷つまり「紙なり」を表現する。
◎日本の庭では、水は流れていなければならない。
◎大文字山の大の字も魔除けの星形五角形である可能性がある。
◎×は悪そのものであるとともに、悪を払うものである。
◎唐草風呂敷の歴史は浅く、明治30 年代にはじまった。
◎江戸時代の「わくわく」は、肝が潰れる寸前の状態を表していた。
◎「みる」という意味を表す漢字は約200 に及ぶ。
◎日本では、ひもは神の力を呼び込む生命的存在とされていた。
◎東洋では、空を飛ぶために必ずしも翼を必要としない。
◎「ぼけ」の振る舞いは、「つっこみ」があってはじめて進展し、構造性を持つ。
◎殺生のもともとの意味は「生かすか殺すか」だった。
◎建物の組み方を最も簡素に、また厳粛に表しているものが鳥居である。
◎我々は積極的に無常、虚無に身を投じ、味わい続けてきた。
◎平安時代には髷を露出することは恥ずべきことだった。
◎浮世絵に見る限り、日本女性は深爪型が好みのようである。
■執筆者紹介…………………………
◎特別寄稿
阿部楽方+ 井上隆明+ 伊部京子+ 岩渕 輝+ 遠藤八十一+ 岡田保造+ 鹿島 享+ 河本英夫+ 木村重信+ 佐々井 啓+ 白石晃子+ 須賀崇江+ 高木茂男+ 高橋美矢子+ 竹迫祐子+ 田中秀隆+ 寺山旦中+ 中山 茂+ 西垣安比古+ 畑 正高+ 原 秀三郎+ 広井 力+ 牧野和春+ 三倉克也+ 水木しげる+ 村松俊夫+ 安田容造+ 吉田柳二+ 米今由希子+ 和田直人
◎形の文化会会員(執筆時)
相田武文+ 荒川 紘+ 粟野由美+ 一戸良行+ 今井祝雄+ 大形 徹+ 岡本正志+ 金子 務+ 楠本健司+ 小町谷朝生+ 小山清男+ 笹本純+ 清水達雄+ 末房由美子+ 関 三平+ 高木隆司+ 高橋理喜男+ 竹沢攻一+ 田淵晉也+ 辻元よしふみ+ 中川素子+ 羽鳥昇兵+ 花岡永子+ 一松 信+ 前田富士男+ 三田村〓(俊の「にんべん」を「たへん=田」に)右+ 三井直樹+ 三井秀樹+ 宮崎興二 + 向井周太郎+ 村井俊子+ 桃谷好英+ 森 貞彦+ 森 毅+ 柳父 章+ 山口義久
◎形の文化会
数学者、森毅を初代会長に、1992年発足した学際的な学会。文化諸領域に見られる「かたち」を科学的・文化的・歴史的視点に立って総合的に研究し、研究者、芸術家、技能保存者などが一堂に会し、学際的、広域的、創造的対話を図ることを趣旨とする。 現会長はアインシュタイン研究で著名な金子務。小町谷朝生(文星芸術大学教授/色彩論)、宮崎興二(京都大学教授/図形科学)らも編集委員に名を連ねる。『形の文化誌』はこの会の会報誌(年刊)として、1993年から2004年まで全10号を刊行。
内容説明
かた(型)+ち(魂)で、かたち…。縄文から現代まで、天皇から町人まで、暮らしも信仰も、芸能も物語も、季節も争いも、政治や経済さえも、いつも「かたち」に寄り添っていた。ひとつの「かたち」に万感を込め、「かたち」のかけらに万象を観る。日本の謎は「かたち」で解ける。
目次
1 かたちのことば(かたちの見取図;かたちと方法;世界をかたどる)
2 かたちのかたち(天象と地象;物怪と異界;道具と暮らし;遊芸と芸道;文字と数と謎;図形と象徴;記号と文様;メディアと様式;からだと衣装)
3 ひととかたち
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しぇるぱ
芋餡饅ぢう