内容説明
地球もふくむ6つの惑星は、調和音を奏でながら太陽の周りを運動する。処女作『宇宙の神秘』(1956)で提唱した5つの正多面体による宇宙モデルと、ティコ・ブラーエとの共同研究により第1・第2法則をうち立てた『新天文学』(1609)の成果を統合し、第3法則を樹立した歴史的名著。ラテン語原典より本邦初の完訳。
目次
第1巻 調和比のもとになる正則図形の可知性と作図法から見た起源、等級、序列、相異
第2巻 調和図形の造形性
第3巻 調和比の起源および音楽に関わる事柄の本性と差異(協和の原因;弦の調和的分割;調和平均と協和の3要素 ほか)
第4巻 地上における星からの光線の調和的配置と気象その他の自然現象を引き起こす作用(感覚的調和比と思惟でとらえられる調和比の本質;調和に関わる精神の性能はどのようなものがいくつあるか;神もしくは人が調和を表現した感覚的もしくは非物質的対象の種類と表現 ほか)
第5巻 天体運動の完璧な調和および離心率と軌道半径と公転周期の起源(5つの正多面体;調和比と正多面体の親縁性;天の調和の考察に必要な天文学説の概略 ほか)
著者等紹介
ケプラー,ヨハネス[ケプラー,ヨハネス][Kepler,Johannes]
1571年、ドイツのヴァイル・デァ・シュタット生まれ。テュービンゲン大学で学んだ後、グラーツの神学校で数学・天文学を教える。処女作『宇宙の神秘』(1596)に示された数学的才能を評価したティコ・ブラーエに招かれ、プラハで共同研究した成果を『新天文学』(1609)に発表。いわゆるケプラーの3法則のうちの楕円軌道の法則(第1法則)、面積速度一定の法則(第2法則)を確立。さらに本書『宇宙の調和』(1619)で第3法則(惑星の公転周期の2乗と太陽からの平均距離の3乗が比例する)を提示し、近代科学の基礎を築く。またガリレオが発見した木星の「衛星(satelles)」の命名者、星形多面体の発見者、最密充填問題の予想者としても科学史に名を残している。1630年、レーゲンスブルクにて客死
岸本良彦[キシモトヨシヒコ]
1946年生まれ。1975年、早稲田大学文学研究科博士課程修了(東洋哲学専攻)。現在、明治薬科大学教授(史学・医療倫理・薬学ラテン語担当)。上代中国思想史および古典ギリシア語・ラテン語による哲学・医学・天文学関係の著作の翻訳研究に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
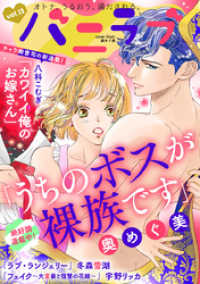
- 電子書籍
- バニラブvol.13 バニラブ







