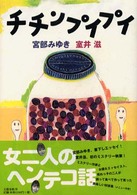内容説明
ルーマニア出身の学生ルイは、古い修道院蔵書の中で発見されたライプニッツの知られざる弟子アロイシウス・カスパールの手稿に魅せられる。「実体とは鏡自体をも映し出す凹面鏡のようなものではないか」―。アロイシウスのライプニッツへの問いが、ルイを「可能的世界」の迷宮に連れ出して行く…。ライプニッツの迷宮をめぐる幻想哲学小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rinakko
12
再読。5冊の架空の書物が登場し、可能的世界をめぐる連作の幻想哲学奇譚5篇。そもライプニッツの「可能的世界」とはなんぞ…と踏み入る。“神はすべての可能的世界の中から最善なものとしてこの現実世界を選択した、はず”(訳者あとがきより)…とな。ところが、思弁上の問題として導入された可能的世界という考え方が、登場人物によってまったく違う文脈で語られだすのでややこしい。その迷宮の眩暈感と、設定と題材でひき込まれる。今回は、表題作と「異端審問教程」が面白かった。2017/11/16
刳森伸一
2
ライプニッツの「可能世界」をモチーフにした連作短篇小説。架空の書物に対する考察や、未完の小説内小説とその考え得る結末のバリエーションなど。各短篇は短いのだが、すべて開かれた構成となっており、様々な結末が可能で、それが「可能世界」を表すという入れ子構造となっており、どこまでも知的遊戯に満ちている2015/08/03
minota
1
帯にあったルーマニアのボルヘスというのは納得いかないけどこういう小説は子供の頃夢中で読んだ本を思い出す。そしてこれを読んで千夜一夜物語を読もうと決意。さあ、何版に手を付けるかな。2013/11/29
rinakko
1
ライプニッツの迷宮、と。架空の書物をめぐる設定も内容もとても面白いが如何せん話が短く(一話完結)、もっと広げて欲しいなぁ…と思わずにはいられない、いけずな哲学小説だった。主人公ルイは暇があれば古文書調べをしている。古い要塞や朽ちかけた修道院には、酷く傷んだ本が山を成していた。とある学院蔵書のことを知ったルイは、そこで発見されたライプニッツの弟子の手稿を読むことに…。合わせ鏡を覗きこむ眩暈感のとば口から、一歩二歩踏み込んだところでふっと物語が終ってしまう。嗚呼、面白かったのに。ルイの〆の言葉が憎いじゃないか2012/07/07
wanted-wombat
0
ライアンを読んで以来、ライプニッツに興味が湧き、その過程で知った小説。ライプニッツの「可能世界」を題材にしたもので、ある種のメタ性を持つ。訳者も書いているように、現実とそうでない世界の垣根が曖昧になってくる。非常に短い短編が五編のみだが、理解がとても難しい小説です。2012/10/27


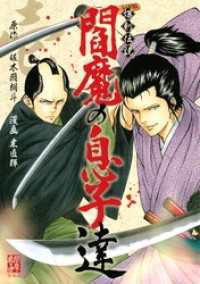
![わくわくパネルシアターキット変身おばけちゃんのはらぺこ大冒険 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44153/4415320686.jpg)